みんなこれまでの人生の中で1度や2度、入試を体験したことがあるよね。高校や大学、人によっては小学校や中学校に入るために入試を経験している人もいるかもしれないね。
入試の世界では独特の造語がいろいろとあるよ。これから自分が、人によってはわが子が入試を体験することになった時のために覚えておくといいよ。
入試問題に関する造語
入試問題に関する造語はいろいろとあるね。例えば入試問題でどれだけの点数が取れたかは、受験生にとっては最重要問題だ。
入試問題の点数次第で、自分が志望している学校に入れるかどうか決まるから。実は入試問題の点数では、独特の造語がいくつかあるよね。
基準点
例えば基準点。基準点は受験生は十分意識しないといけないね。というのも基準点とは特定の強化や科目に設定されている、合格するための最低点のことなんだ。例えば総合点が合格ラインを越えていても、どれか一つでも基準点に達していないと不合格になってしまうね。
基準点の取り扱いについては、学校によってまちまち。事前に公表しているところもあるし、平均点に対して何パーセントという形で算出しているところもあるね。
傾斜配点
傾斜配点も入試問題以外ではあまり目にしない言葉かもね。傾斜配点とは教科間で配点に差をつける方式のこと。大学入試の時に採用されることが多いよね。
通常はその学部や学科と関連の深い教科については他よりも重くする傾向がみられるね。中には解答時間が全く一緒でも、教科によって特典が2倍つくといったこともありうるよ。
素点
素点という言葉も入試の世界ではしばしば聞かれるよね。これは各教科の本来の点数のことを指しているよ。例えば大学入学共通テストの場合2022年現在、外国語と国語は200点でそのほかは1教科当たり100点になっているよ。
実はこの大学入学共通テスト、大学ごとでこの配点を自由に変更できるんだ。もちろん素点そのままに評価する大学もあるし、大学共通テストの配点を圧縮したり変更したりする大学もあるよ。
2次試験との得点比率調整のために変更するのが目的だね。これもある意味さっき紹介した造語の傾斜配点ということになるね。
自己採点
大学入学共通テストを行った後で解答を見て、自分で採点したことのある人もいるだろうね。これを入試の世界では自己採点というよ。国公立大学の場合、足切りがあるから自己採点をして2次試験に申請できるかどうかの判断基準になるね。
自己採点を正確に行わないと、2次試験の志願先も影響を受けるので慎重に行ったほうがいいね。
得点調整
得点調整という言葉もあるね。これは複数教科や科目間で差の調整を行うことだね。教科や科目間で問題の難易差はどうしても生じるよね。そこで調整が必要になる場合があるんだ。
基本的には平均点を基準にして調整するのが一般的だ。大学入学共通テストの場合、理科2・地歴B・公民が対象になるよ。もし受験者数が1万人以上の科目で、平均点が20点以上開きがあった場合に調整される可能性があるね。
ただしその平均点の差についてだけれども、試験問題の単純な難易度の差によるものでないと得点調整が行われないのが原則だよ。
入試スタイルにも専門用語が
入試っていうと、一般的には複数科目のテストを受けて、一定の合格基準に達するかどうか考査するものと思うよね。でも入試問題について、学校によっていくつかのスタイルがあるよ。
アラカルト入試
例えばアラカルト入試。複線入試とも呼ばれているよ。一般的には大学入試の場合、3教科がオーソドックスだよね。でも大学によっては1教科ということもあれば、大学入学共通テストを利用している学校もあるよ。
さらに英語外部試験を採用したり、特定科目配点重視型などいろいろなスタイルがあるよ。アラカルト入試の場合、このような入試問題のスタイルを複数用意するんだ。そして受験生はその中から一つ、自分にとって有利なタイプを任意で選択して受験するわけだ。
アラカルト入試は私立大学では結構すでに導入されているよ。さらに近年では国公立大学でも複線化の動きが高まってきているね。もしかするとアラカルト入試が今後大学入試では主流になるかもしれないよ。
一般選抜、一般入試
一般選抜とか一般入試といった言葉はよく使われるよね。一般選抜とは、特別選抜を除く選抜方式のことだね。特別選抜についてもここで紹介しておくと、学校推薦や社会人、帰国子女の入試などが該当するね。
一般選抜が入学者選抜の中でも最も割合が多いよね。学校で多少の差はあるものの、大体国公立大学で8割・私立大学でも5割くらいが占めているんじゃないかな。
特別選抜、総合型選抜
特別選抜の中には、総合型選抜というものもあるよ。「AO入試」という言葉を聞いたことがあるかな?実は総合型選抜ってAO入試のことなんだ。従来のテストを解く方式ではなく、書類審査を詳細に行って、面接などを組み合わせることで採用するかどうか判断する方式だね。
志願者の能力や適性、学習に関する意欲、目的意識と総合的に判断して入学させるかどうか判断するための入試だね。AO入試はすでに導入されていたけれども問題点があるといわれていたね。それは「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」の評価が不十分だという指摘だ。
このため実質、学力不問の入試になっていることが問題だったんだ。そこで2021年から学力を確認する評価方法の実施が必須になったよ。
具体的には小論文やプレゼンテーション、口頭試問、実技などで評価するのが一般的かな。試験は実施せずに資格や認定試験の成績で考査する場合もあるよ。大学入学共通テストの受験を義務化することで対応している大学もあるね。
英語外部試験
入試方式として、英語外部試験を導入している学校もあるよ。これは文字通り、外部で実施されている英語試験などで入学の合否を判断する方式だね。具体的には実用英語技能検定やTOEFLなどを採用している学校が多いよ。
取得しているスコアや英検の場合、級などで判断しているね。2022年の一般選抜試験で英語外部試験を導入している割合だけれども国公立大学で12%、私立大学では38%というデータも出ているよ。まだ少数派だけれども、徐々に導入を検討している大学も見られるよ。
共通テスト過年度成績利用
共通テスト過年度成績利用を導入している大学も一部見られるね。これは造語の通りで過年度に受験した大学入学共通テストの成績を利用する方式だね。最大で過去3年間の成績を利用することが可能だ。
ただしすべての大学で共通テスト過年度成績利用を認めているわけじゃないんだ。全体的に見ると、共通テスト過年度成績利用を認めているのは一部の大学に限られているみたいだね。
主体性評価
入試の中には、主体性評価と呼ばれる方式を採用している大学もあるね。これは生徒が主体性をもって多様な人々と連携して学ぶ態度があるかどうかを評価する方式だね。こういわれてもピンとこない人もいるだろうから具体的な方法についてみていくと、面接や小論文で考査するのが多いね。
そのほかにも調査書などを提出してもらって、それを数値化することで合否を判断する学校もあるみたい。このような主体性の評価はこれまで、総合型選抜や学校推薦型選抜では重視されてきたけれども一般選抜ではそこまで重視されてこなかったね。
しかし大学入試改革の一環で一般入試でも主体性評価を積極的に導入するよう求められていることから、大学も変化の兆しがみられているよ。特に国公立大学を中心に、面接の導入や調査書の数値化を試みているところも少なくないね。
また活動報告書など志願者本人が作成した資料を加味して、合否を決める方式も見られるよ。
学校推薦型選抜
さっき学校推薦型選抜という話が出たけれども、いわゆる推薦入試のことだね。出身学校の校長が推薦して、選抜を行う方式だよ。学校推薦型選抜はさらに2種類のスタイルに分類できるよ。
指定校制と推薦
まずは指定校制といって、大学が指定する高校の生徒を対象にした推薦があるね。もう一つは公募制だね。こちらは大学が提示する出願条件をクリアしている生徒であれば推薦を受けられるというものだね。
公募制
公募制の場合、別に出身校は不問だ。公募制推薦の中にもいろいろなタイプがあって、有資格者推薦やスポーツ推薦、一芸一能推薦などの形式があるね。
私立大学と国公立大学の違い
私立大学の場合、結構推薦入試を導入しているところも少なくないね。
一方国公立大学の場合、原則公募制のみとなっているね。しかも推薦を受けられる基準も厳しめに設定されているよ。学校推薦型選抜はいろいろな大学で導入しているね。
あまり知られていないことかもしれないけれども、東京大学や京都大学のようないわゆる難関の国公立大学でも実施しているんだ。
前期日程と後期日程について
大学入試では前期と後期っていう言葉がよく使われるよね。学生時代に前期とか後期といった言葉を使ったことのある人も多いだろうね。これは試験日程のことを指すよ。国公立大学では前期日程と後期日程で試験が実施されるよ。
前期日程
前期日程とは2月下旬に実施されることが多いね。全体の日程の中でも最も多くの学生を募集する試験になるよ。ちなみに前期日程に合格して入学手続きをした場合、そのほかの日程の合格の権利が無くなってしまう。だから一般的には第一志望校を前期日程で受験することになるよね。
後期日程は3月中旬に行われる国公立大学の入試だね。募集人員を見ると、前期日程よりも少ないのが一般的だから前期と比較して倍率が高い、すなわち競争率が高いというわけ。ただし学校によっては、実際の倍率ほど難易度が高くないという場合も。
というのも前期日程に合格した学生は後期日程には参加しないから。後期日程そのものは3月中旬に実施されるけれども、出願期間は1月下旬から2月上旬と、前期日程と一緒。この点には注意が必要だね。
後期試験
ややこしいのは、「後期試験」という言葉もあるよ。こっちは私立大学が実施する試験のことだね。2月下旬から3月にかけて実施されていて、「2次試験」や「3月入試」と呼ばれることもあるね。こちらも募集人員が少なめで、人気の大学になると高い倍率になることもあるよ。
中期日程
国公立大学の中には、中期日程で試験を実施しているところもあるね。中期日程は例年、3月上旬に実施されるよ。出願期間は前期と一緒で、前期日程で合格して入学手続きをした場合、合格の権利が失われるのは後期と一緒。
ちなみに中には中期日程と後期日程の両方で合格する学生さんもいるかもしれないよね。その場合には中期と後期の合否結果を確認した後で、どっちに入学するか決めることができるよ。ちなみにこのようにあとで入学する大学を決める方式のことを、「事後選択制」っていうよ。
試験日自由選択制
入試スケジュールの中には、試験日自由選択制と呼ばれる方式をとっているところもあるね。これは私立大学で導入されている入試方式で、志願者が都合の良い日を選択して受験できるのが特徴。
同一の学部・学科・入試方式の試験日が2日以上設定されている。学校の中には複数日受験することを認めているところも結構あるよ。
偏差値についても理解しておこう
入試の際に切っても切り離すことのできないものが偏差値だよね。偏差値のレベルによって、どこを受験するか決める学生も多いんじゃないかな。偏差値とは母集団の中で、自分の学力がどの辺にあるのか相対的にわかる数値だね。
平均点の偏差値が50になるから、50より上なら半分よりも上、50より下であれば平均よりもしたということになるよ。複数の偏差値を比較する人もいるかもしれないけれども、母集団に対する相対的な数値だから母集団が異なっていると単純な比較にはならないから注意が必要だね。
入試問題独特の造語に注目
入試問題の世界ではここで紹介したように、ほかではあまり目にしない造語がしばしば使用されているよ。特に入試方式については近年様々な方式が導入されていて、多角的に生徒を採用する大学も増えてきているね。また入試の日程もいろいろな選択肢があるから、スケジュール調整しながらどの大学を受験するかいろいろと検討したほうがいいね。
また入試方式によって自分の能力が発揮できるかどうかも変わってくだろう。一般選抜以外に、自分の長所を発揮できる入試スタイルはないかチェックするといいよ。
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。
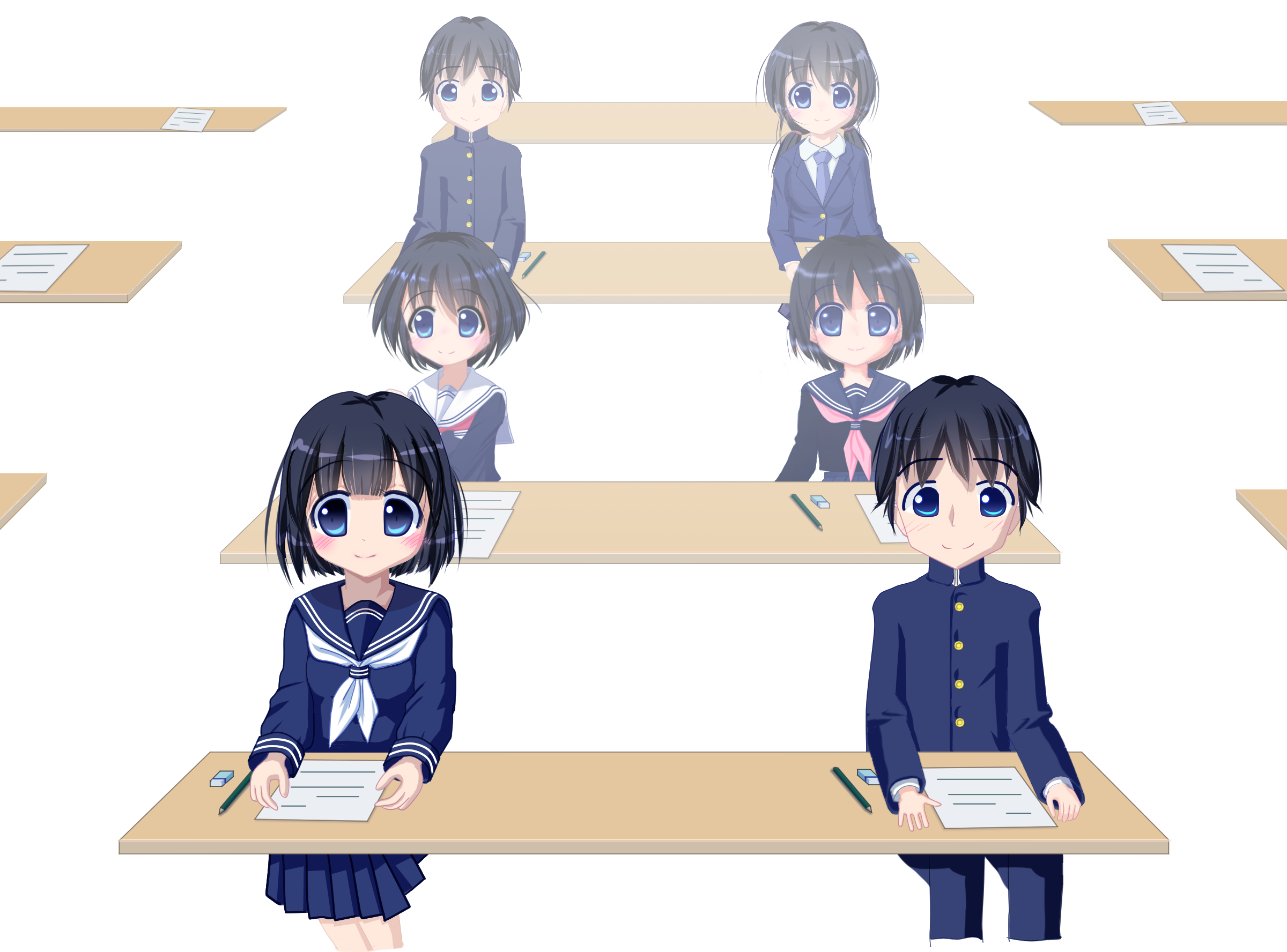



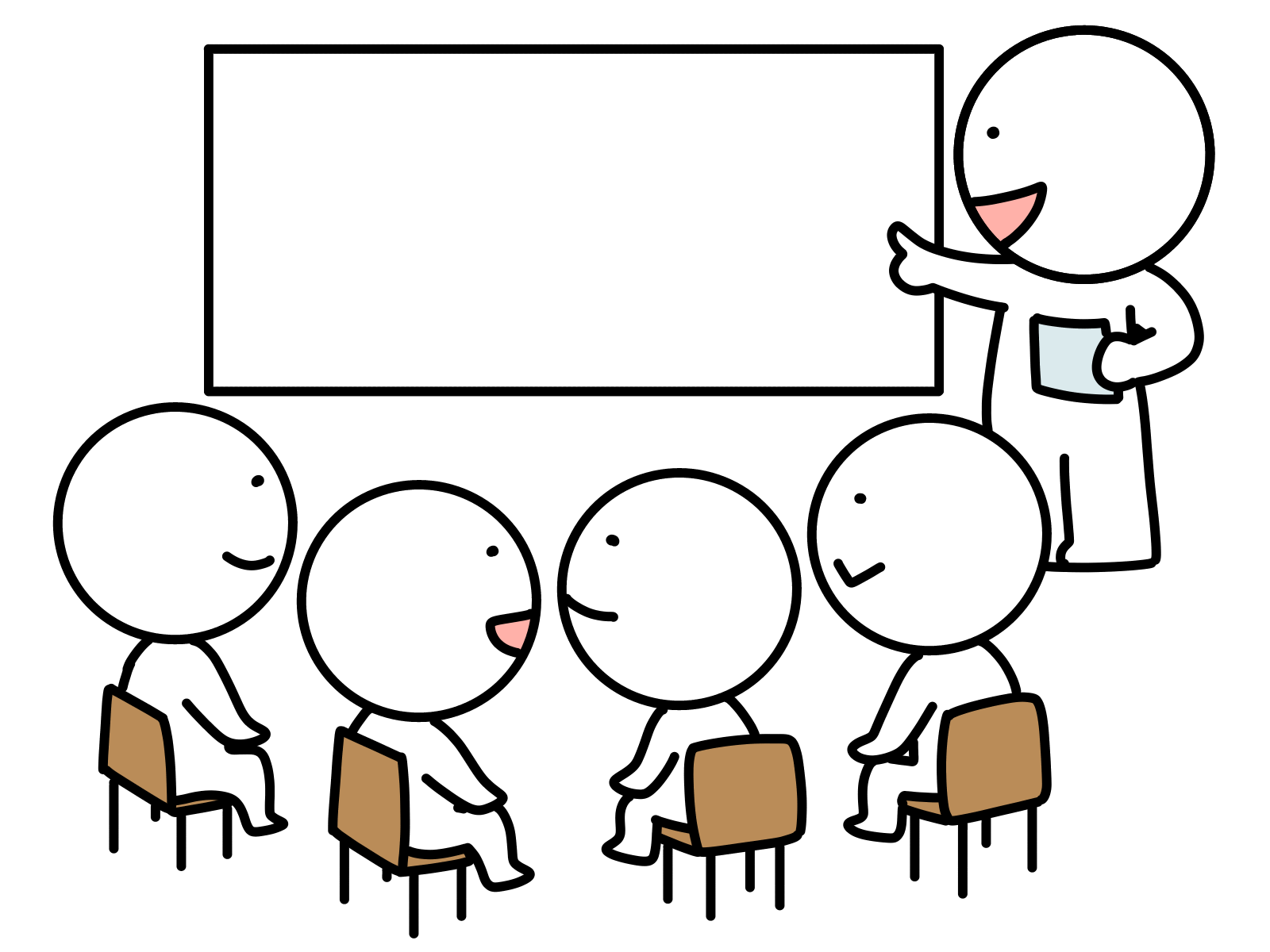
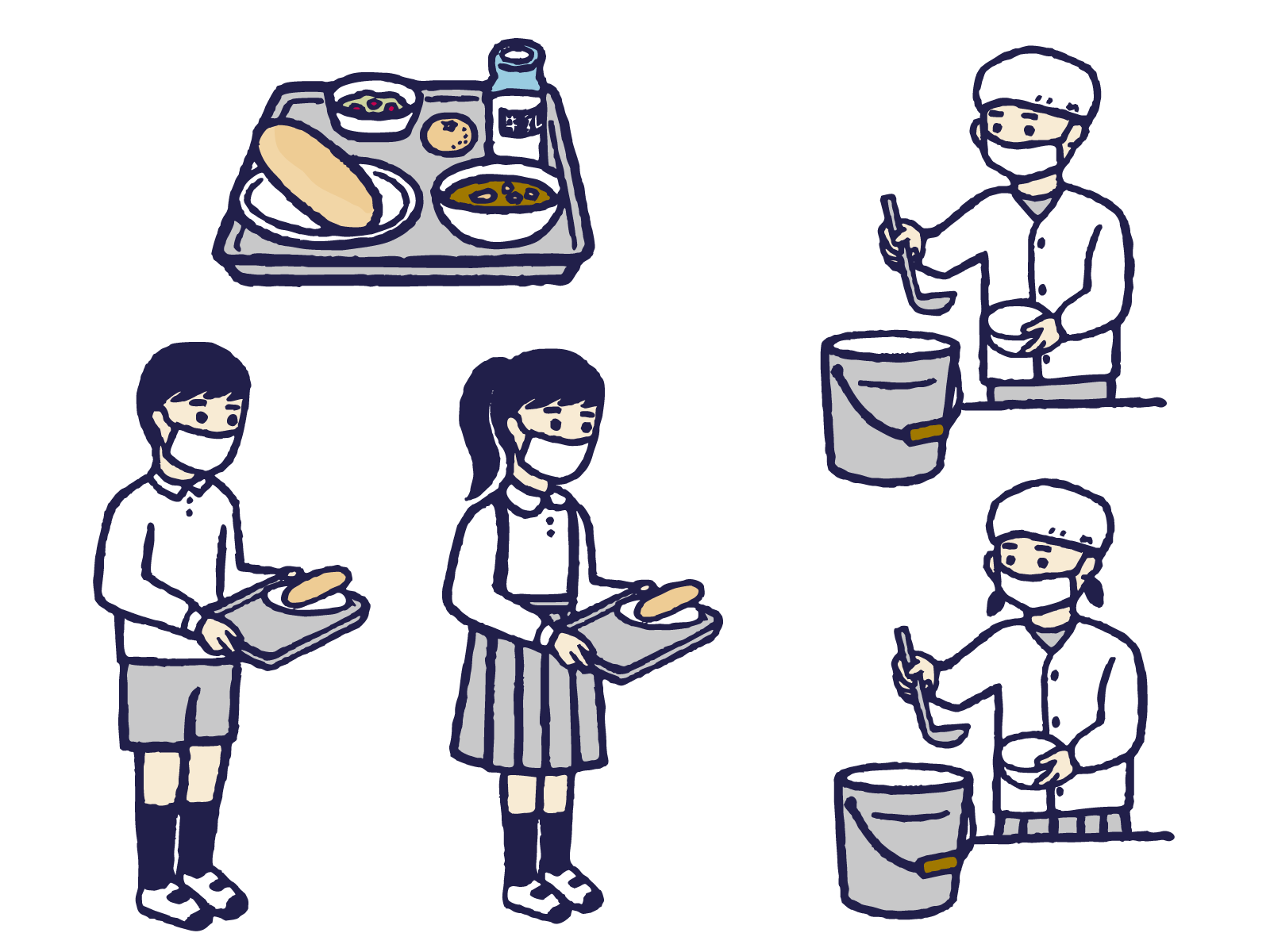
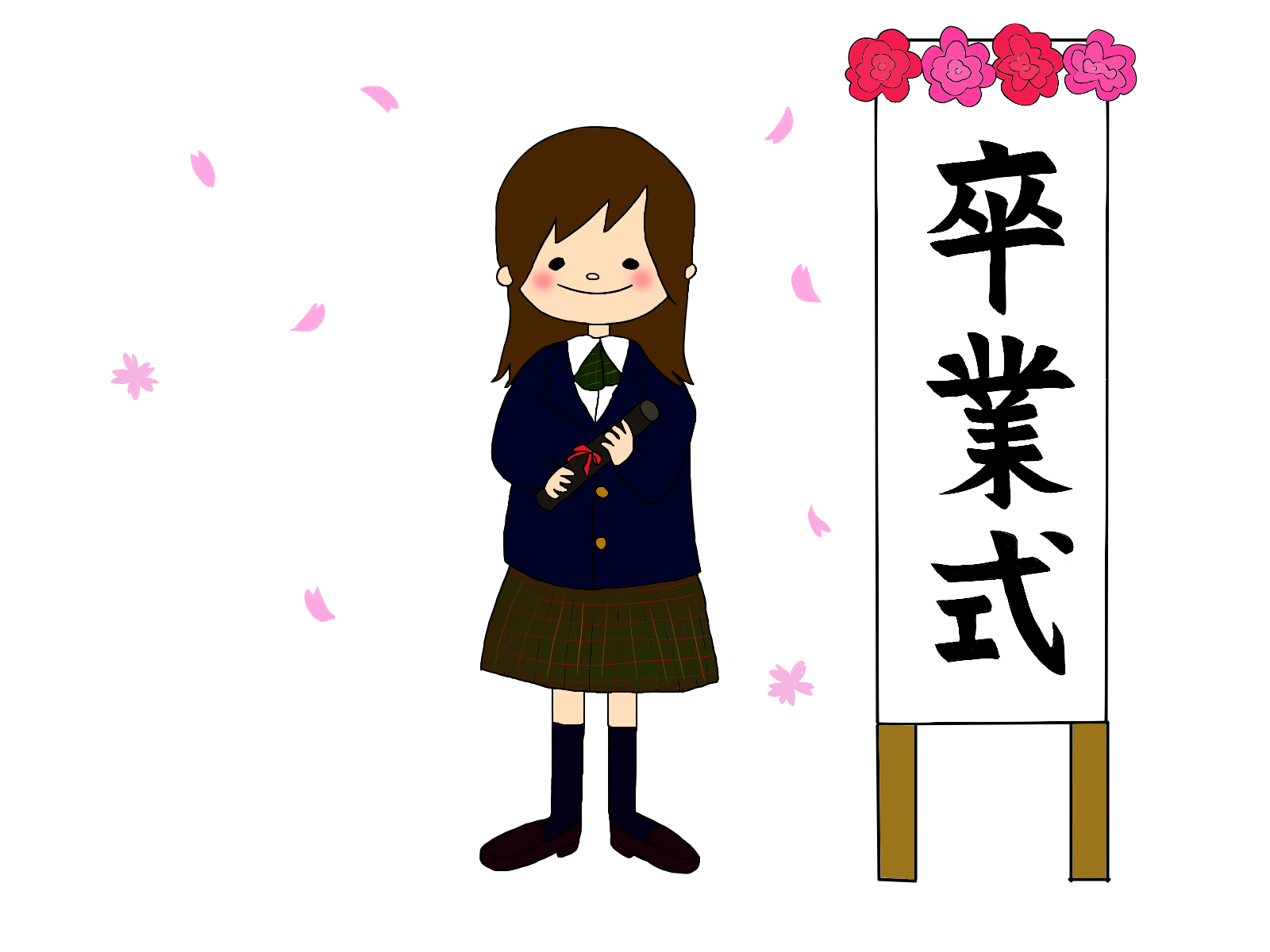

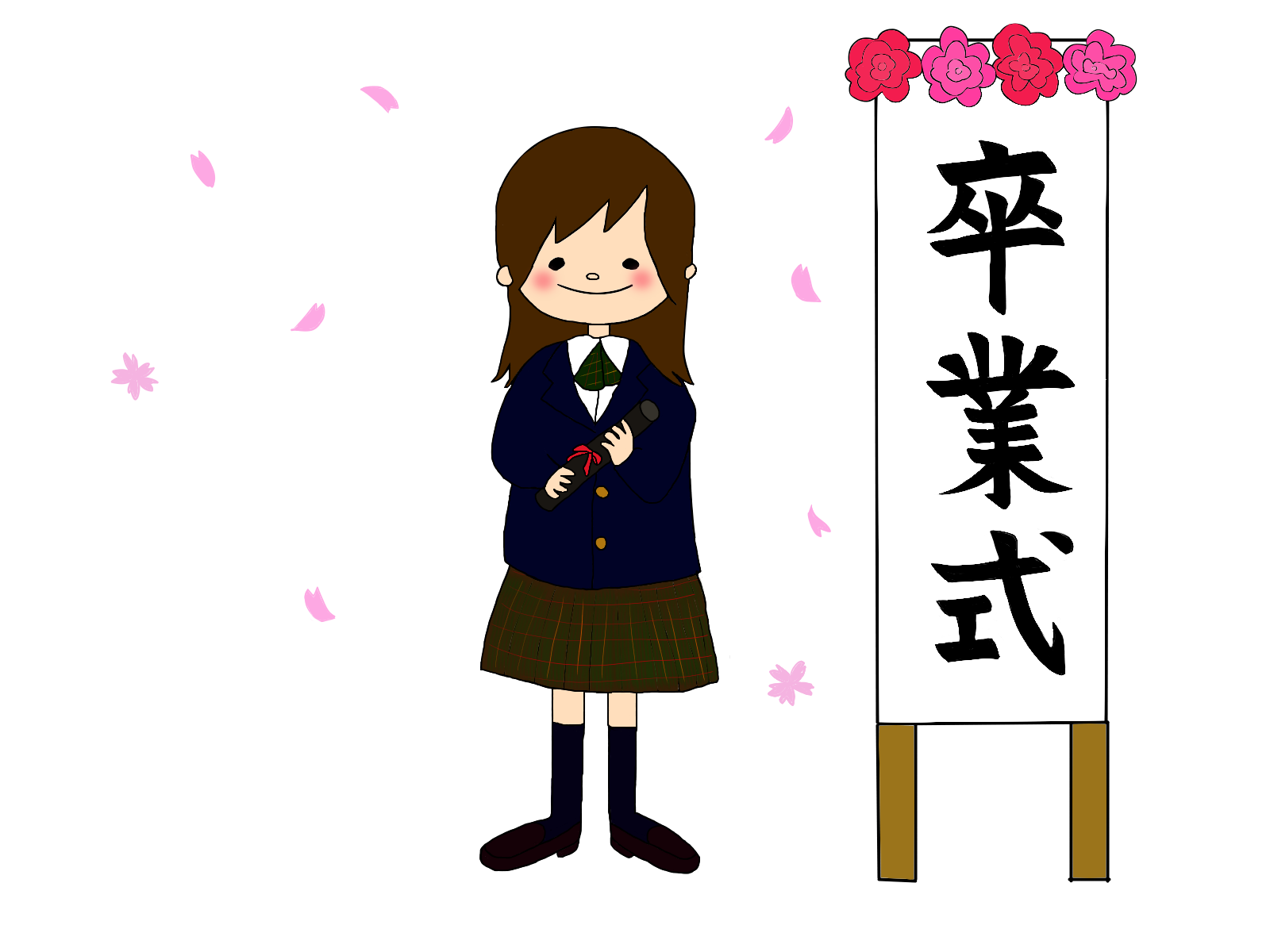
コメント