造語の成り立ち
造語と聞くと堅苦しい印象を持つ人もいるかもしれないけど、造語は意外とそこまで堅い言葉じゃなくて、私たちが日常生活で使っている言葉の延長線上にある言葉遊びに過ぎないよね。
だから、造語の成り立ちと言っても、たいそう立派な歴史があるとかいう訳ではないよ。言うなれば、流行語の派生系のような位置づけが造語なんだよね。
造語の時代背景
歴史を遡ると、造語は明治時代ごろから広く社会に流行し始めたんだって。それ以前にも造語自体はあったけれども、近代政府の樹立と文明開化とともに、外来語が日本へ到来したことによって、造語が社会に浸透して現在に至ったんだね。
写真
有名なところでは、「写真」という言葉があるよ。これは「写す」と「真に」といった言葉の合成による造語だよね。ちなみに、写真技術は幕末ごろに日本に到来して、明治期に広く一般化したんだよ。
テレホンカード
それに、造語は時代の流れを映す象徴のような役割もしているよね。例えば、「テレホンカード」という造語は、「テレホン」と「カード」を掛け合わせた、合成による言葉だよね。
テレホンカードと言えば、偽造テレカなどが世間を騒がせたこともあったけど、今や全くの過去の遺物になってしまったね。最近の子どもに「テレホンカード」や「公衆電話」と言っても通じないし、理解できない子が多いよ。
携帯電話やスマートフォンの普及で、公衆電話やそこで使われたテレホンカードの存在感が薄くなってしまったのが、時代背景として挙げられるんじゃないかな。
だけど、東日本大震災などの携帯電話の回線がダウンしたときには公衆電話の強靭性が再認識されたし、いざというときに役目を発揮するものだと言えるよね。
造語とコミュニケーション
合成語、「る」をつけて動詞化|造語の作り方
造語には、主に合成語と、「る」などを付け加えて動詞化した言葉が存在しているよ。合成語なら、例えば「青函」トンネルに見られる、「青森」と「函館」の言葉があるね。動詞化には、「ググる」など、「グーグル」に「る」を付け加えたものがあるよね。いずれにしても、これらは端的に分かりやすく伝えようとして、造語が作られたと言えるんじゃないかな。
青函トンネルを「青森函館トンネル」なんて言ったら、長過ぎて面倒くさいなと感じる人が多いんじゃない?それに、「ググる」ことを「グーグルという検索エンジンで調べてください」と生真面目に話すのは面倒くさいと思うはず。「青函トンネルを越えるよ」とか、「この資料の分からないところはググっといて」と伝えることができると、便利であることが分かるよね。
造語はコミュニケーションを円滑に進めるために作られてきた
造語の成り立ちは、コミュニケーションをいかに円滑に端的に進めていくかということを追求していく過程で作られてきたと言えるよ。造語と聞くと、私たちの日常生活には関係ない、学術的な使い方をする用語じゃないかって疑問視する人もいるかもしれない。
でもね、意外にも、私たちの生活に深く関与する、ファストフードのような言葉遊びじゃないかな。それぐらい、私たちに近く寄り添った庶民的な言葉遊びが造語だよ。
自発的に作られる造語
女子高生が「プリクラ」や「タコパ」といった造語を気軽に使っている様子からも、これらが自然発生的に生み出された言葉ではなく、何らかの言葉の造語として作られたということがよく分かるじゃないかな?
ちなみに、プリクラは「プリント」+「クラブ」、タコパは「タコ焼き」+「パーティー」の合成語なんだけど、プリクラはクラブという女子高生たちのギャル文化と密接に関わって発展をしてきたんだよね。
国語教育における造語
造語力は国語教育で養われる
さっき、造語が若者文化とともに発展してきたと言ったけど、それなら、教育的にも強い影響を子どもたちに及ぼしていると言えるんじゃないかな。若者言葉がいくら学術的には研究に値しないと決めつけても、それらの言葉を作り上げる能力、つまり造語力というのは学校での国語教育で養われたものなんだからね。
ということは、国語教育において造語を行うことって、とても有意義な教育的効果があるんじゃない?ちなみに、新しい漢字を作ってみるといった授業も、教育的指導の観点からは造語と同様にとても効果があるんだってよ。
造語も、教育において高いクリエイティブセンスを養う手段として、効果的な教育ツールの側面も持ち合わせているんだね。
国語教育の本質からずれている教育現場
義務教育課程で国語教育というと、その本質がどうしても軽視されがちなのが実情。教育困難校であればそもそも国語教育に生徒が関心を示さずに成り立っていない場合があるし、逆に進学校であれば受験対策において影が薄い科目として問題を解く能力に特化していて、残念なことに、国語教育の本質からはズレているというのが教育現場の状況になんだよね。
造語教育でクリエイティビティを伸ばす
そういった困難な状況にある国語教育に新しい風を吹かせるのは、造語じゃないかな。自分は造語症だというぐらい、造語に長けた人材を国語教育で育成できれば、その子のクリエイティブセンスは大きく向上するだろうね。
学校教育の最も目指すべき目標はクリエイティビティを伸ばすことにあって、輪切り型の大量生産で同じ学力や同じ思考回路を持った生徒を養成しても、社会ではキラリと輝く人材にはなれないよ。
ある一定の最低ラインをクリアするだけの学校教育では、あまり意味を成さないんじゃない?学校は社会知識のセーフティネットと呼ばれることもあるけど、本当に目指すべき姿は豊かな創造力と斬新な思考力を持つ人間の養成だよ。
造語はコミュニケーションの創造
そういった教育目標を達成するのに、造語は強い力を発揮するよね。造語を作り上げるという作業は、今まで使われてこなかった組み合わせの言葉を作り上げる行為に他ならないし、言うなれば新しいコミュニケーションの創造だよ。
そうした造語の作業を通じて、子どもたちは豊かな言語力とコミュニケーション技術を身につけていくはず。
造語などのクリエイティビティが求められるアドミッションオフィス試験
近年は大学入試においても、アドミッションオフィス試験などが行われているよね。推薦入試の名前の付け替えではないかと批判されることもあるけど、造語などで養われたクリエイティブセンスが評価される試験であれば、アドミッションオフィス試験には大いなる意義があると言えるんじゃない?
ただし、こういった国語教育と造語を上手く組み合わせて生徒たちのクリエイティブセンスを向上させていけるどうかかは各々の教員にかかっているよね。
単に俳句大会のように、作って終わりじゃ意味がないし。造語を作って、その背景を深く推察することで、新しいコミュニケーションの価値観を追求していくことができるようになるんだから。そうすれば、造語を作り上げるという作業が、個々の人間的表現力の向上に役立つよね。
造語作成で測れる能力
個人のセンスと知識を計測できる造語力
近年は、入試問題に思考力テストを導入するところが、私立の中高一貫校を中心に増えているんだって。なぜ、造語作成という、悪く言ってしまえばおじいちゃんたちの俳句大会のようなことで、志願者のポテンシャルを測ることができるのかと疑問に思う人も多いかもしれないね。
でも、造語には個々人のセンスと知識を測ることができる、大いなる力があるんだよね。
例えば、全くニュースを見ない子や新聞を読まない子であれば、漢字を使った造語はまず作れないんじゃないかな。作れても、稚拙で深い意味が捉えられていない、荒唐無稽で滅茶苦茶なものになってしまうはず。また、日ごろからコミュニケーションがあまり得意でない子も、あまり造語を作ることは得意としないだろうね。
造語は社会常識や時事ネタを基礎に作られる
造語というのは、個々人のコミュニケーション能力と、その基礎となる社会常識や時事ネタなど、社会人基礎力となり得る能力の育成に必要な、最低限のスキルを表しているよね。そうした意味において、入学試験で造語の作成を課すことにはとても意義があると言えるんじゃないかな。
子どもたちが作り上げる造語は、大人の考えにはない、全くしがらみのないクリアな視野から作られていて、そこには1つ1つに異なるキラリと光る価値が感じられるよ。
オリジナリティを見破れる造語
また、自分で考えたのか、他の人間が考えたものを暗記しただけなのか、直ぐに見破ることができるのが造語でもあるよね。そうした観点において、積極的に意味を込めた、攻めた造語を作り上げられる子どもは、クリエイティブセンスが優秀な子どもであると言えるわけ。
ギョーラーチャ
例えば、ギョーラーチャという造語を聞いて、その意味がすぐにひらめく人は少ないんじゃない?ちなみに、この造語はギョーザ+ラーメン+チャーハンの合成語で、ラーメン屋や中華料理店などで常連になると、「ギョーラーチャちょうだい」と頼むだけで、ギョーザとラーメンとチャーハンが迅速に出てくるんだよね。
造語の作り方に正解はない
造語って、必ずしも正解があるものじゃないよね。例えば、造語の作り方といった教科書があるとしても、そのハウツーに沿って忠実に作られた造語なんて、おもしろくないのは言うまでもないよね。
分かりやすく言うなら、作家の宮部みゆきを好きな人が、その作品に基づいて作家養成のテキストブックを作ったとするじゃない。そうしたら、それを学んで作家を目指す人たちは、宮部みゆきの二番煎じにしかならないってことと同じだよね。
要するに、造語とは1つの作り方にとらわれることなく、個々人の能力を測ることができるツールであるということ。そのため、入試問題に造語を使った設問を、または造語作成を指示する設問を置けば、受験者の秘めたる感性を引き出して、評価することができるかもしれないね。
入試問題に出たらおもしろい造語
入試問題において、造語は個々人のクリエイティブセンスを測るのに大いなる効果を発揮しそうだよね。それと同時に、造語を出題して意図を考えさせることで、受験者の中にあるクリエイティビティを測ることができるよね。
「上意下達」を選ぶところを「潮位下達」
どのような造語が出題されているとおもしろいと感じるかは人それぞれだけど、例えば「上意下達」を選ぶところを「潮位下達」なんて選択肢があったらおもしろいかもしれないね。
センター試験が実施されていたころは毎年ネタ問題が数題組み込まれていたものだけど、こうした造語を使ったネタ問題は、受験者の緊張して凝り固まった脳みそに刺激を与えて、ほんわかとした気持ちにさせてくれるね。
設問『「文人」という言葉を用いて造語を作れ』
設問に『「文人」という言葉を用いて造語を作れ』なんてものがあってもおもしろいかもね。学生が作りそうな答えとしては、「妄想文人」だとか、天神という教育ソフトウェアのコマーシャルに掛けて「文人文人文人」なんて造語もあったら、なかなかセンスがある学生だよ。
天神のコマーシャルの放送時間から、その学生は、アニメ・ドラえもんを良く見ていたんだろうということがわかるね。
設問「解いてニャン」
設問に「解いてニャン」などと、猫言葉を造語として付け加えてみるのも良いかもね。「ニャン」は実際に、ヤマト運輸などのインターネットサービスで実用化されているよ。ニャンとあれば、例えば難し過ぎて分からない数学の問題に遭遇した場合であっても、「解けないニャン」と落ち込むことなく次の問題に進むことができるかもよ?
だいたい、あまりにも難しい問題は大概、他の志願者も落としているので、合否に影響することはないだろうしね。
造語で心をマッサージする
こんな造語による心理的に温かいマッサージ効果は、受験者の心を包み込む力強い手助けとなるよね。クスッと笑ってしまう受験者もいれば、「何だ、この学校はふざけてるのか」と呆れてしまう志願者もいるよね。
呆れた人は、不合格だった場合の心理的負荷が小さくなるかも。そうした造語による学校独特のメッセージを挟むことで、敢えて学校の目指す方向性に沿うような志願者を選抜することができる面もあるね。
造語で有意義な人材を育成していこう
入試問題におもしろい造語を出題することで、その学校にはそれを良しとするユーモアセンスにあふれる生徒で埋め尽くされるかもよ。
ユーモアセンスに熱い人って往々にして心の優しいおもしろい人間だから、そうした有意義な人材を育成していくことにより、学校の価値を大きく底上げすることにつながるかもね。
入試問題に出てきておもしろいと感じるような、笑いのある造語を使った問題を作れば、出題者も解く学生も心豊かになるという効果がもたらされるんじゃないかな。
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。



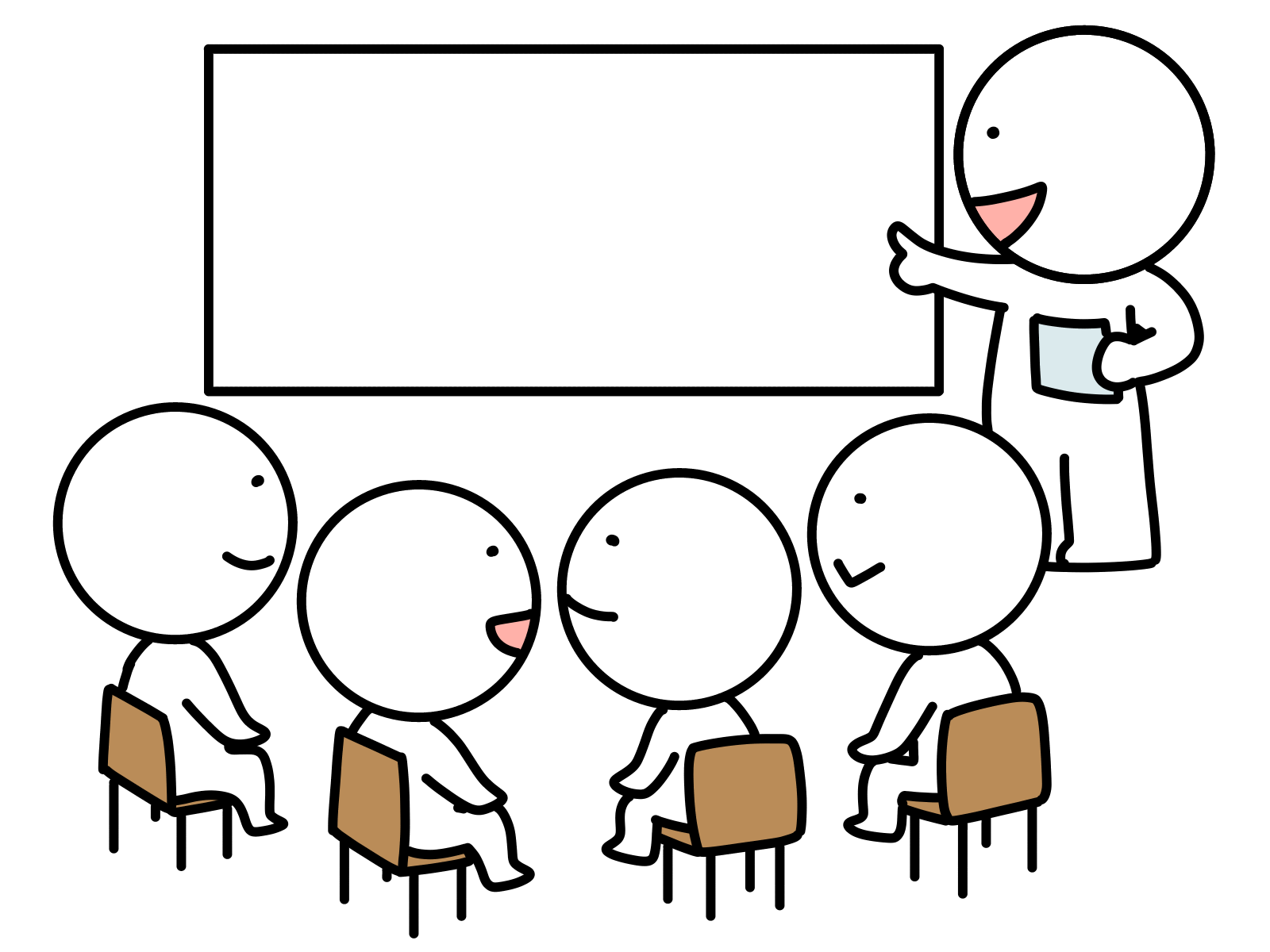
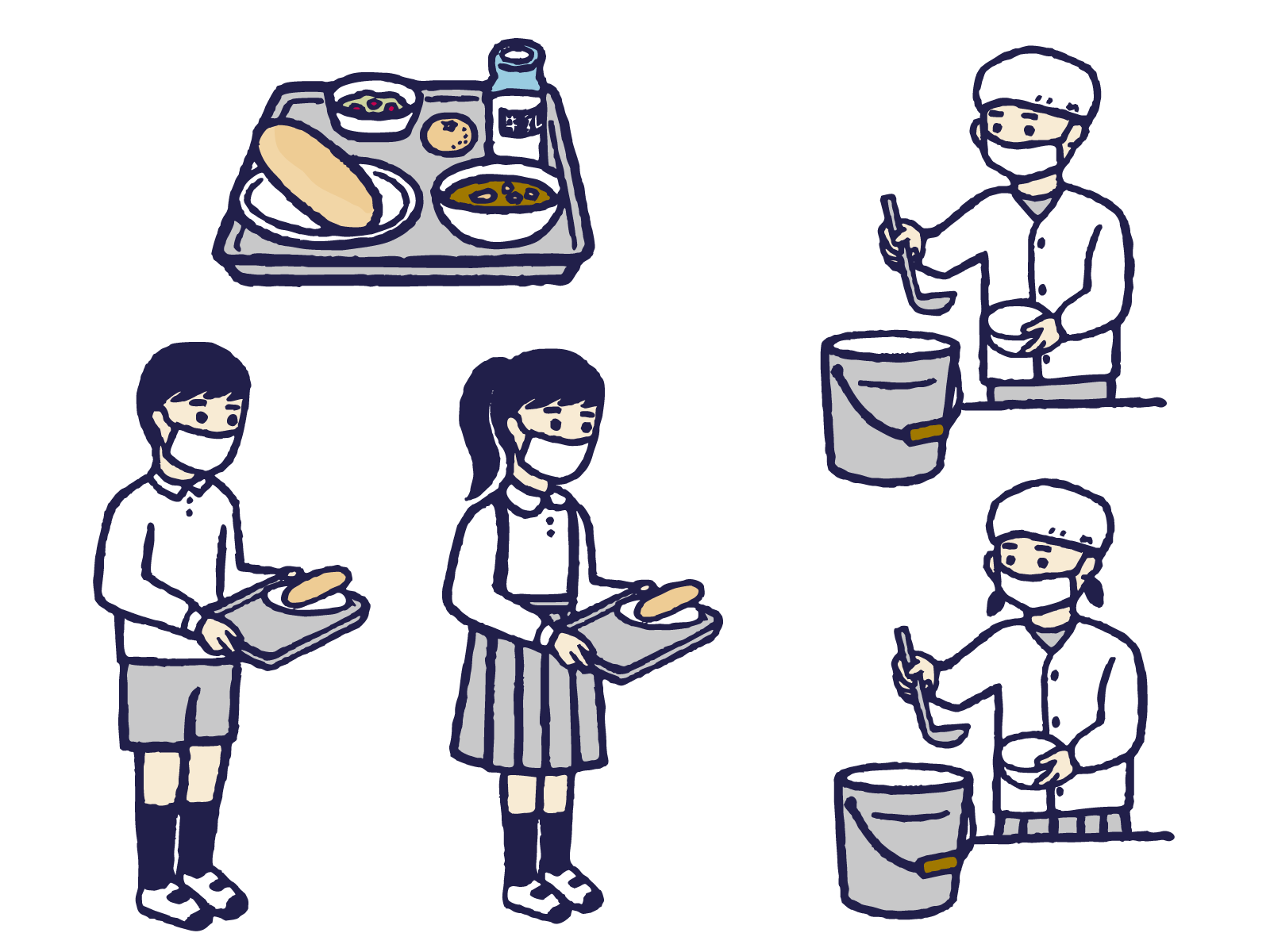
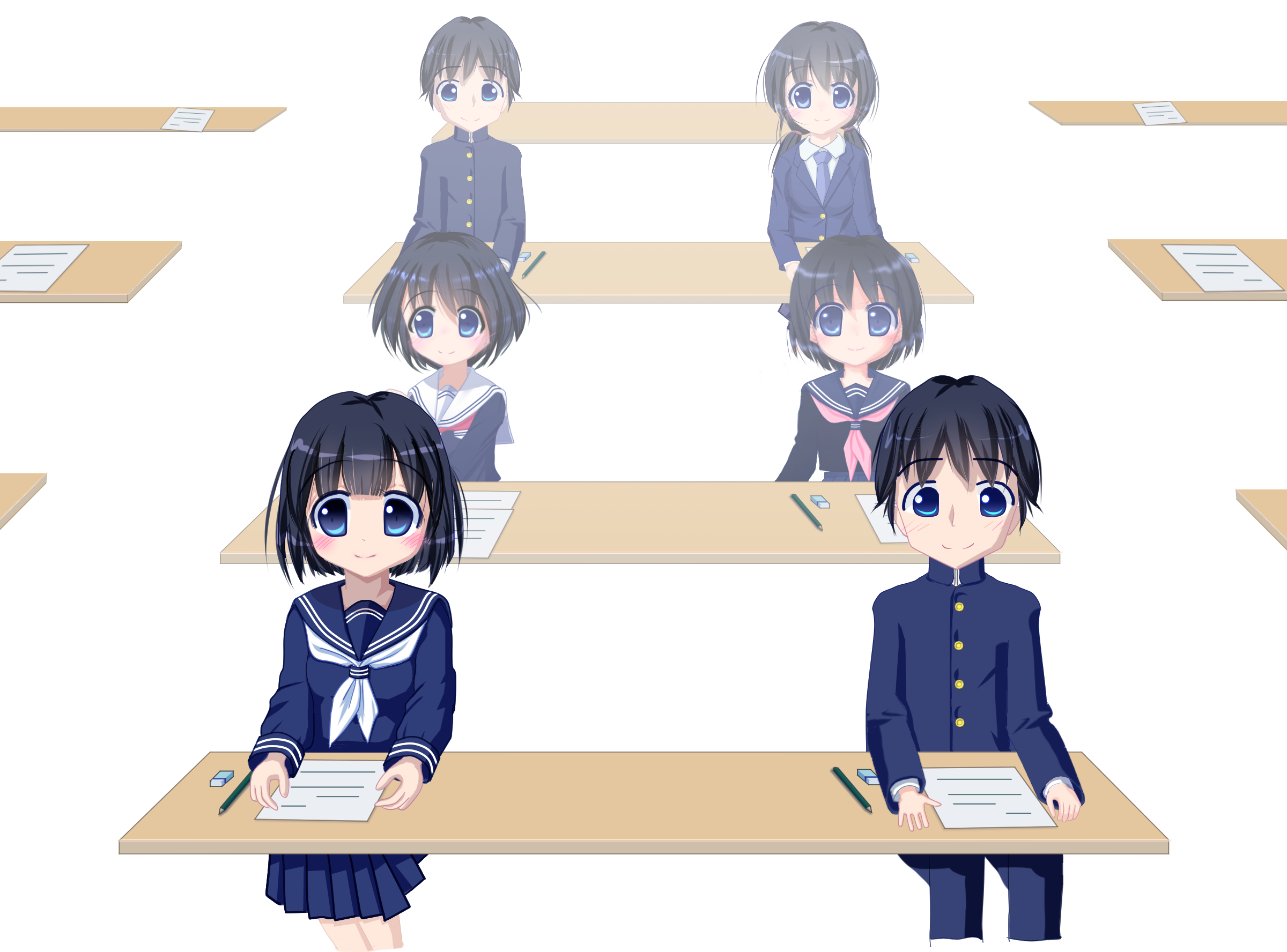
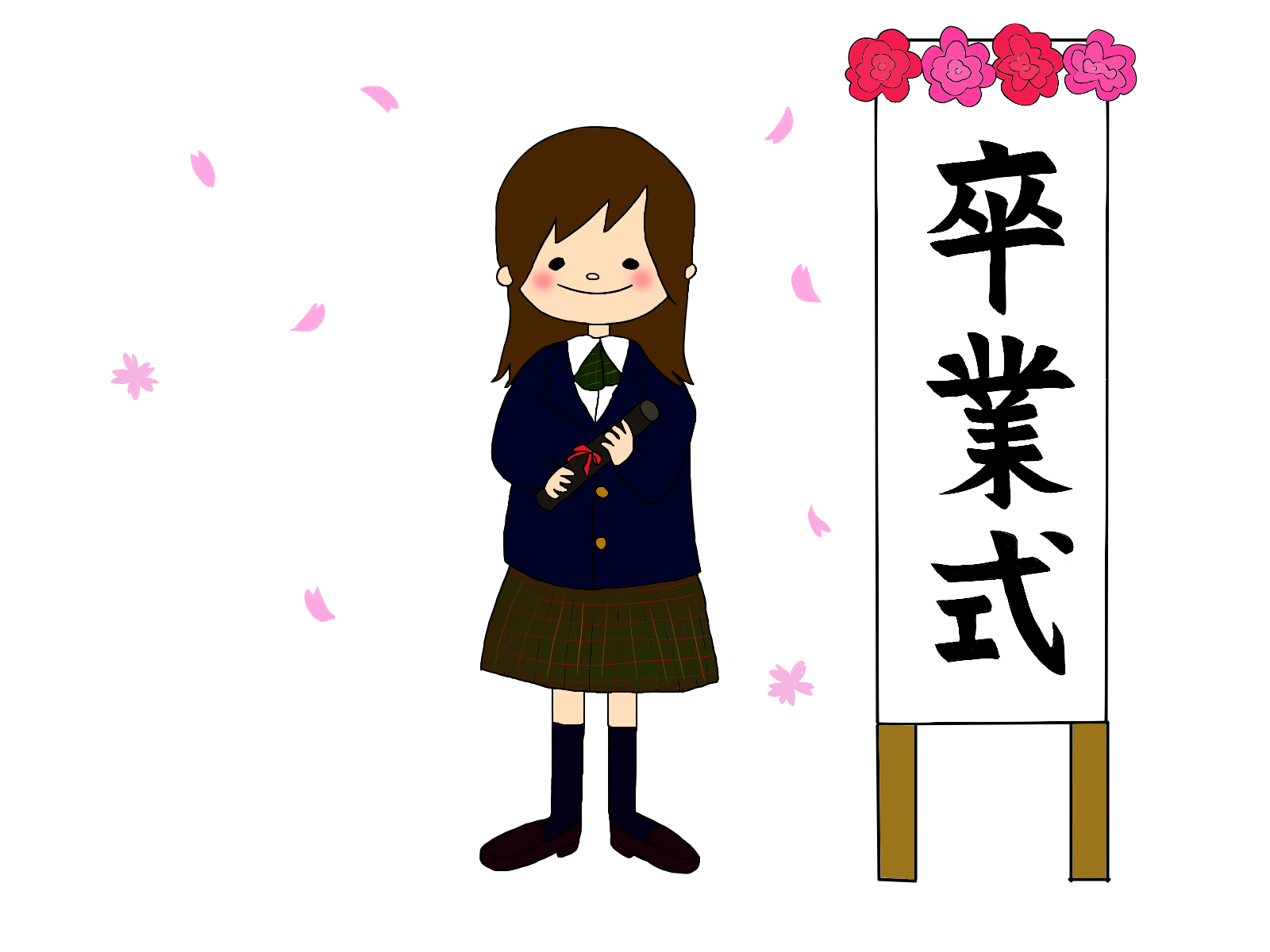

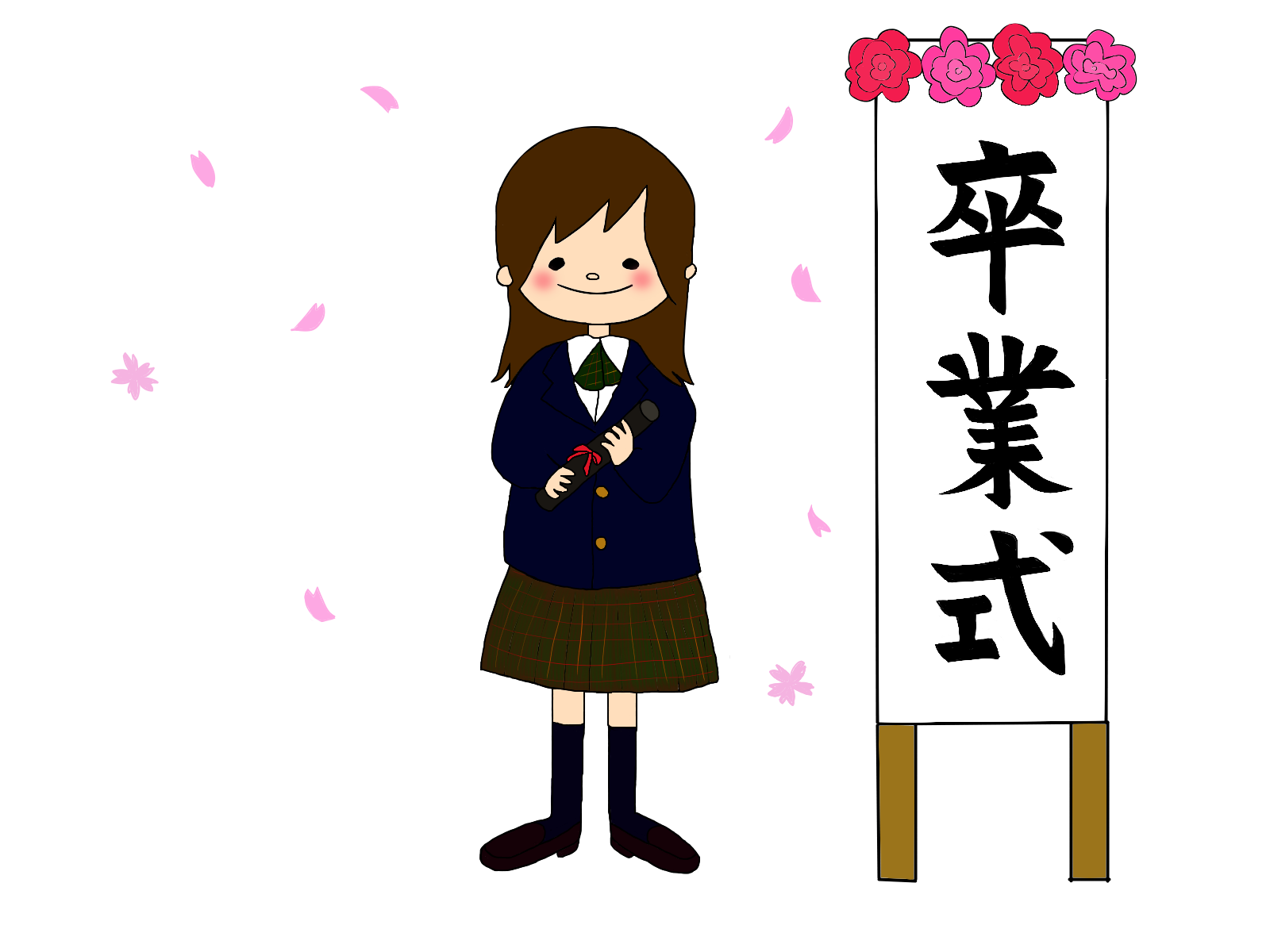
コメント