どの国でも、言語の研究にたくさんの時間とお金を費やすよね。言葉の起源や変化、成り立ちなどを調べていくと、その言語を使う文化や思想などに大きな影響を与える事実が判明することもあるんだ。
でも、言語学は考古学とは違って、今も現在進行形で変化しているもの。その変化もまた文化を知る上では重要な研究材料なんだ。その変化の中でも、「若者言葉には、」たくさんの研究者が注目しているんだ。
若者がもともとある言葉をつなぎ合わせたり、変化させたりして作る造語には、若者が置かれている境遇や心情が見事に反映されていることが多くて、文化を理解する上での重要な研究材料になっているんだ。
中には大学の卒業式に必要な論文の題材にする学生もいるほどだよ。ただの若者の流行りと軽視しないで、若者言葉を紐解いていくと、思わぬ気付きがあるかもしれないね。2022年の時点で注目されている若者言葉にはどのようなものがあるのかな。
tosツイ
「tosツイ」はTwitterで使われる用語で、@tosにリプライする行為のこと。「リプライ」とは特定のユーザーに向けてコメントを送る機能で、「@+ID名」の後にコメントを書いて送信すると、そのユーザーにのみ見えるようになるんだ。
つまり@tosにリプライすると、tosのアカウントにだけ届くメッセージとなるわけ。しかしtosというアカウントはユーザー不在の凍結アカウントでだから、@tosをつけたコメントは、実際は誰にも表示されないんだ。
それを利用して、自分だけが見ることができるメモ帳代わりにしたり、誰にも言えないけど吐き出したい愚痴などをツイートしたりするのに使われているんだね。
でも2022年11月現在では、tosのアカウントの凍結が解除されているから、誰かに見られる可能性が出てきているよ。
限界オタク
「言動が行き過ぎて周りがついていけなくなったオタク」という意味。具体的な例では、自分が好きな物事について話すときに、必要以上に熱が入ってしまったり、言葉にならずに叫び声をあげてしまったり、といった奇怪な行動をする人のことを差すよ。
限界オタクという言葉が生まれたのは2003年頃だけど、その後廃れることなく生き残り、ここ数年でSNS上で使われるようになったんだ。もともとはネガティブな意味で使われていたけど、最近では愛情表現の最上級として、ポジティブな意味で使われることもあるよ。
ちいかわ構文
まず「ちいかわ」は、イラストレーター・ナガノさんによるマンガ作品だね。Twitter上で公開され人気になり、グッズやアニメも話題になったんだ。そして「ちいかわ構文」とは、そのマンガに出てくるセリフをマネした文章のこと。
例を挙げると「…ってコト?」「こんなんさァッッ絶対アレじゃん」などです。特別変わっているわけでは無いけど、何となく使い心地が良い言い回しが多く、SNSなどで使われているよ。
母胎ソロ
「母胎から出て来て以来ずっとソロ」つまり、生まれてから一度も恋愛経験が無い、という意味だよ。2019年に初回が始まった韓国ドラマ「愛の不時着」で使われた言葉だね。
母胎ソロという言葉が生まれてから「年齢=恋人いない歴」が不名誉なことではなく、ピュアで初々しいこと、というような印象に変わり、韓国の芸能界でも母胎ソロであることを公表する人が増えたんだ。
はにゃ?
驚きを表す感嘆詞で、「えっ?」「あれ?」と同じ意味だよ。「はにゃ」という言葉自体は昔からあったけど、2020年にモノマネ芸人の丸山礼さんがネタで使用したことにより、一般的に使われるようになったんだ。
メッセージだけでなく、口頭の会話でも使われるね。驚きの他にもとぼけるときなどにもよく使われる言葉だよ。また、2022年現在ではその使用頻度は下がり始めていて、あまり多用すると時代遅れに感じられることがあるので注意しようね。
チル、チル友
「落ち着く、くつろぐ」という意味の英語の句動詞「Chill Out」から派生した言葉だね。そのまま形容詞として使われることもあるし、「チルする」のように動詞として活用される場合もあるね。
使い方は、休憩時間にコーヒーを飲んでゆっくりしたり、休日にのんびり過ごしたりすることを「チルする」と言った感じ。また音楽のジャンルで、ゆっくりとしたテンポの落ち着いたダンス音楽を「チルアウト系の音楽」と呼んだりもするよ。
その他では、「チル友」という、一緒にくつろぐことができる友人を差す派生語もあるね。
ニシパ
紳士、主人、金持ちなどを意味するアイヌの言葉だね。明治末期の北海道を舞台にしたマンガ「ゴールデンカムイ」の中で使われ話題となったんだ。マンガに登場する男性キャラクターが、頻繁にニシパを敬称としてつけられて呼ばれていることから、マンガファンの間で日常会話で使われるようになったんだね。
また、マンガの舞台となっている北海道では、この言葉の流行りにちなんで「ニシパの恋人」というトマトジュースを販売し人気となっているよ。
領域展開
「領域展開」はマンガ「呪術廻戦」に出てくる技の名前だね。キャラクターがその技を発動すると、ある一定の領域において戦闘相手を自分の空間に取り込むことができて、戦いを有利に進めることができるんだ。それから転じて「日常生活において自分が理想としていた空間を創り出すこと」という意味で使われるようになったんだ。
例えば「今日は部屋の領域展開をした」と言うと、部屋の掃除や模様替えをしたという意味になって、「領域展開した服のコーディネートしてみた」と言ったら、自分の思い通りの服を着てみた、という意味になるよ。
きまZ
きまZは「気まずい」を変化させた言葉。読み方は「きまずぃー」ではなく「きまぜっと」になります。使い方に変化球は無く、気まずい状況になったときに「きまぜっと」とっ呟く感じだよ。
ラインやSNSなどでも「きまZ」と表記されるね。もともとはYouTuberの「うちら3姉妹」が動画の中で使い始め、テレビなどでも取り上げられたことで、若い世代を中心に広まった造語っだよ。
言葉に合わせた決めポーズなども作られ「JC・JK流行語大賞2021」のコトバ部門で第1位を獲得したんだ。しかし2022年になってからは、使用頻度はやや落ちてきているね。
アセアセ
「アセアセ」のアセは「汗」のこと。何かミスをしたり、慌てているときなどに汗をかいたりすることを、文字で表現しているんだ。「授業遅刻しそう、アセアセ」と言ったように、文末で使われることがほとんどだね。
発祥はYouTuberの中町綾さんと言われているよ。
今も生き残る過去の若者言葉
若者言葉や流行語は、時間と共に廃れていくものがほとんどだけど、中には日本語に定着して、その先ずっと使われるものもあるよ。今も日本語に生き残っている過去の流行語にはどんなものがあるのかな。
ダサい
「カッコ悪い」という意味で使われる「ダサい」だけど、実は1970年代の若者言葉なんだよ。関東地方の女子高生が使い始めて流行ったんだ。
語源ははっきりとは分かっていないけど、「どんくさい」がなまったという説と、「田舎者」の「田舎」を「だしゃ」と読んで、これが転じたという説が有力だよ。
五月病
環境が変わる5月に、精神的な負担が重なってうつっぽくなってしまう症状を差す五月病。1960年代に使われ始めた言葉だよ。受験戦争が厳しかった1960年代の学生が、受験を終えた後に、その反動でうつっぽくなってしまうことから、この言葉が流行ったんだ。
シカト
「無視する」という意味のシカトは、1980年代の若者の間で使われ始めた流行語だよ。10月の花札に描かれている鹿の絵が、そっぽを向いて無視しているように見えたことから、10月のシカ、シカ10が、シカトとなったんだよ。
彼氏
男性の恋人を表す「彼氏」という言葉も、実は造語なんだ。1929年に、漫談化の徳川夢声さんが「漫談集」という本に載せる文章を書いていたんだけど、1文字分空いてしまったんだ。
それを埋めなければいけなくて、文章の中の「彼女と彼の会話」という文の「彼」を「彼氏」という言葉に置き換えて乗り切ったんだ。そこから「ボーイフレンド」という意味で使われるようになったんだよ。
OL
「オフィス・レディー」の略で、オフィスワークをする女性のことだよね。この言葉が生まれたのは1963年のこと。それまで働く女性は「職業婦人」や「ビジネスガール」と呼ばれていたけど、これだと娼婦という意味にとらわれてしまうから何か別の名前にしようとしたんだ。
そこで雑誌で募集をかけて決まったのがOLだったんだ。日本で生まれた言葉だから、海外では通じないよ。
がめつい
「がめつい」は欲深いとか、図々しく利益を得ようとする、って意味だね。これも昔からあった日本語じゃなくて、最初に使われ始めたのは1959年のこと。菊田一夫さんが書いた演劇の中で使われたことによって一般的に流行したんだ。
語源は定かではないけど、一度咥えたら離さない習性をもつスッポンの呼び名「がめ」と、「ごつい」を掛け合わせた言葉、という説が有力だよ。
落ちこぼれ
「学校の授業についていけない子供」のことだね。この言葉が使われ始めたのは1970年代のこと。当時はツッパリと呼ばれる不良学生が多くてその人たちのことを落ちこぼれと呼んでいたんだ。
それから、ツッパリじゃなくても授業についていけない子供をみんな落ちこぼれというようになったよ。今では子供だけじゃなく大人にも使われるね。
ノルマ
「一定期間にこなさなければいけない仕事量や成績」という意味で、主に会社で使われる言葉だね。もともとは「基準」を意味する「Norma」というロシア語だよ。
第二次世界大戦中に、ロシア軍の捕虜になって強制労働させられていた日本人が、日本に帰ってきた後に広めたんだ。
ワンパターン
同じパターンを何度も繰り返すことだね。実は和製英語で、1980年代の若者ことばだよ。最初にワンパターンという言葉を使った人は、コメディアンのせんだみつおさんだと言われているけど、はっきりは分かっていないんだ。
しらける
盛り上がっていた気持ちが冷めることだよね。もともとは万葉時代から使われていた言葉で、色が褪せて白くなること。1970年代に起こった学生運動が下火になったあとに、やる気をなくした学生たちを描写するときに使われて、一般的に使われる言葉になったんだ。
脱サラ
会社を辞めて独立するときに使う言葉だよね。この言葉が生まれたのは1970年代だね。この時期を気に「脱○○」という言葉が使われるようになったよ。
ニアミス
惜しい、という意味で使われるけど、本来は「あとちょっとでミスするところだった」という意味だよ。1970年代に飛行機2機が接近しすぎたために起こった事故が話題になったんだけど、そのニュースの中でニアミスという言葉が使われて一般でも使われるようになったんだ。
フィーバー
何かが熱狂的に流行っていたり、調子がいい時に「○○フィーバー」と言ったりするよね。この言葉は1978年に日本公開されたアメリカの映画「サタデーナイトフィーバー」に由来するものなんだ。
その後にパチンコでもフィーバーという言葉が使われるようになって、徐々に日本語に定着したんだね。
ぶりっ子
かわいこぶる女の子を表す「ぶりっ子」は1980年代の流行語だよ。「かわいこぶる子」「いい子ぶる子」の「ぶる」が変化して生まれた言葉なんだ。タレントの山田邦子さんが「かわい子ぶりっ子、ぶるぶるぶりっ子」っていうギャグを使い出してから流行ったんだよ。
「ぶり」を出世魚の鰤に当てはめて、ぶりっ子になりそうな女の子を「はまちっ子」と呼んでいたこともあったけど、そっちは今は使われていないね。
若者のように儚い造語の世界
流行り言葉と呼ばれる造語たちの寿命は、年々短くなってきているね。中にはごくまれに辞書に乗るまでに出世する言葉もあるけど、たいていは2年も持たないよね。
特に中高生の間で使われる造語は、その世代が学校を卒業したと同時に世間から消えてゆくことが普通。その寿命の短さを知っているからこそ、それらの言葉を使う人同士のつながりがより深まるのかもしれないね。
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。
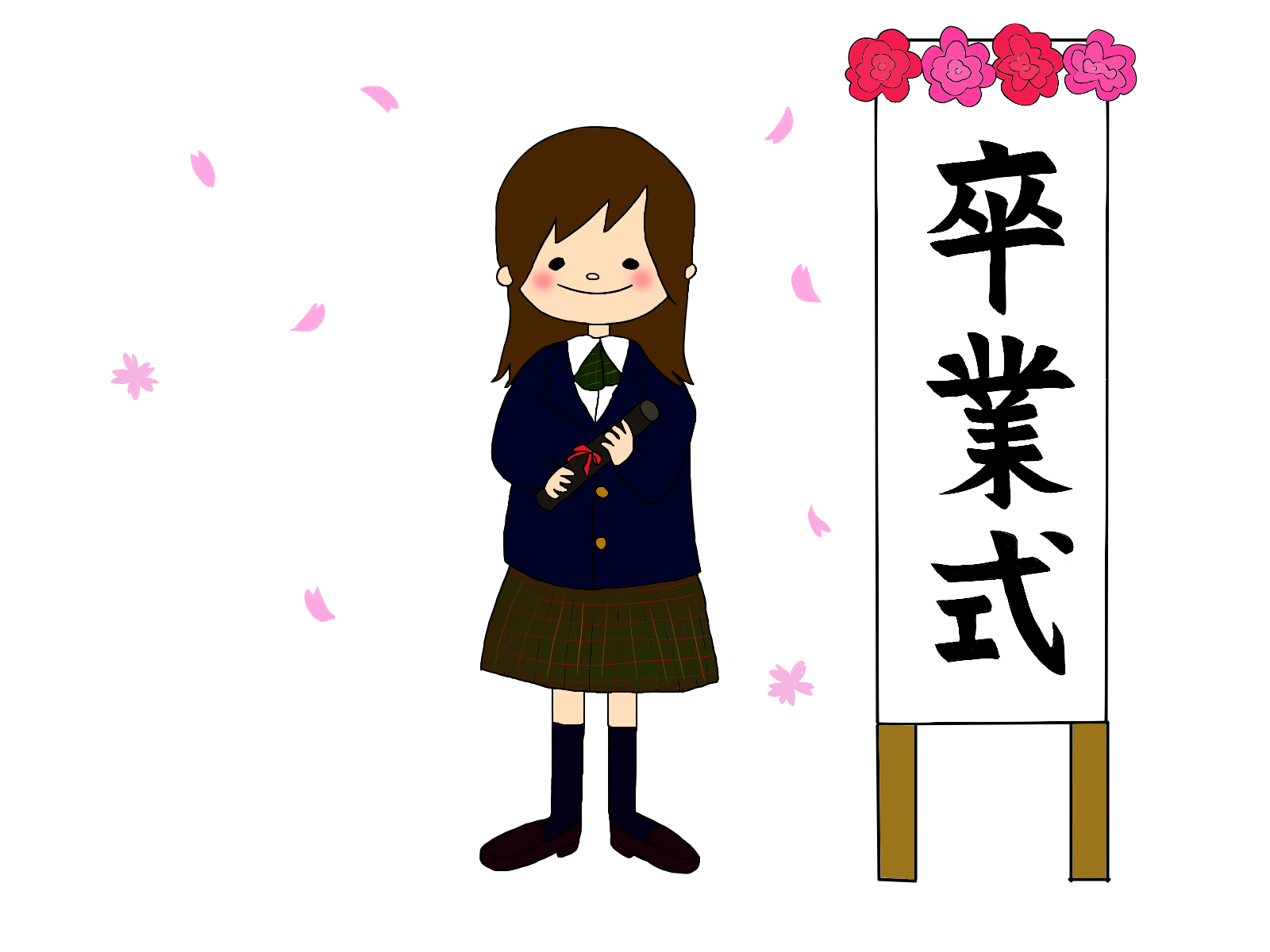





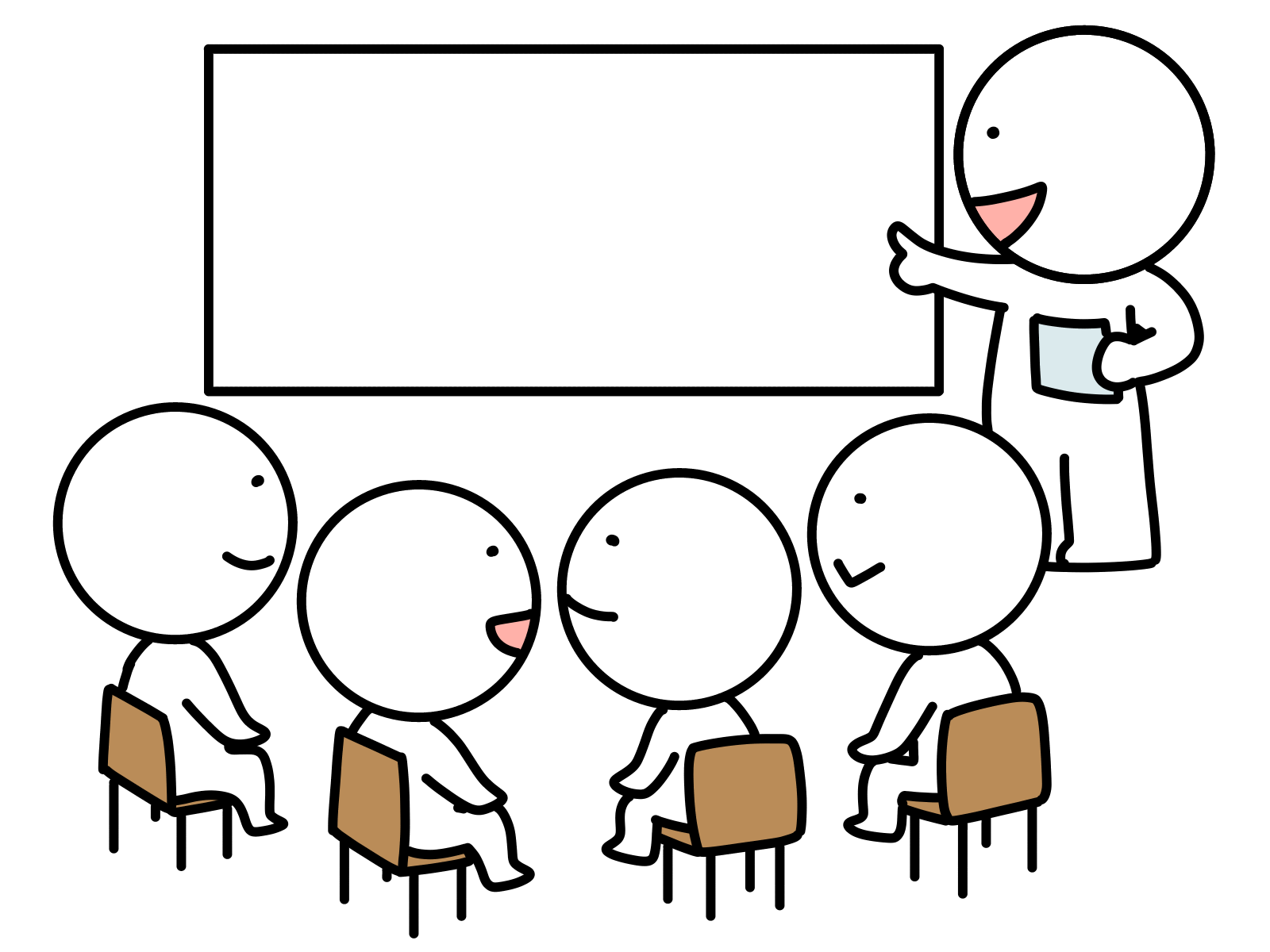
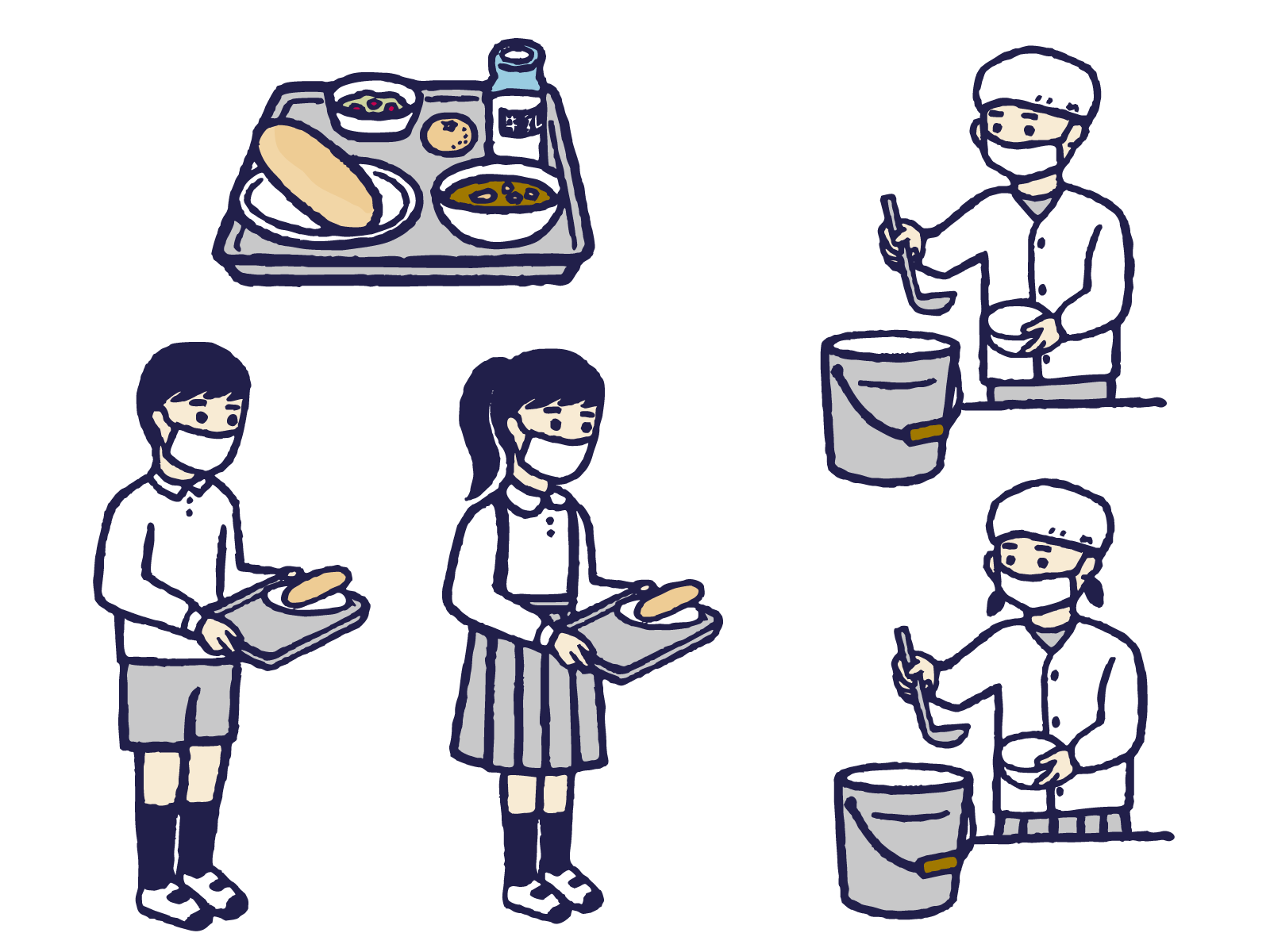
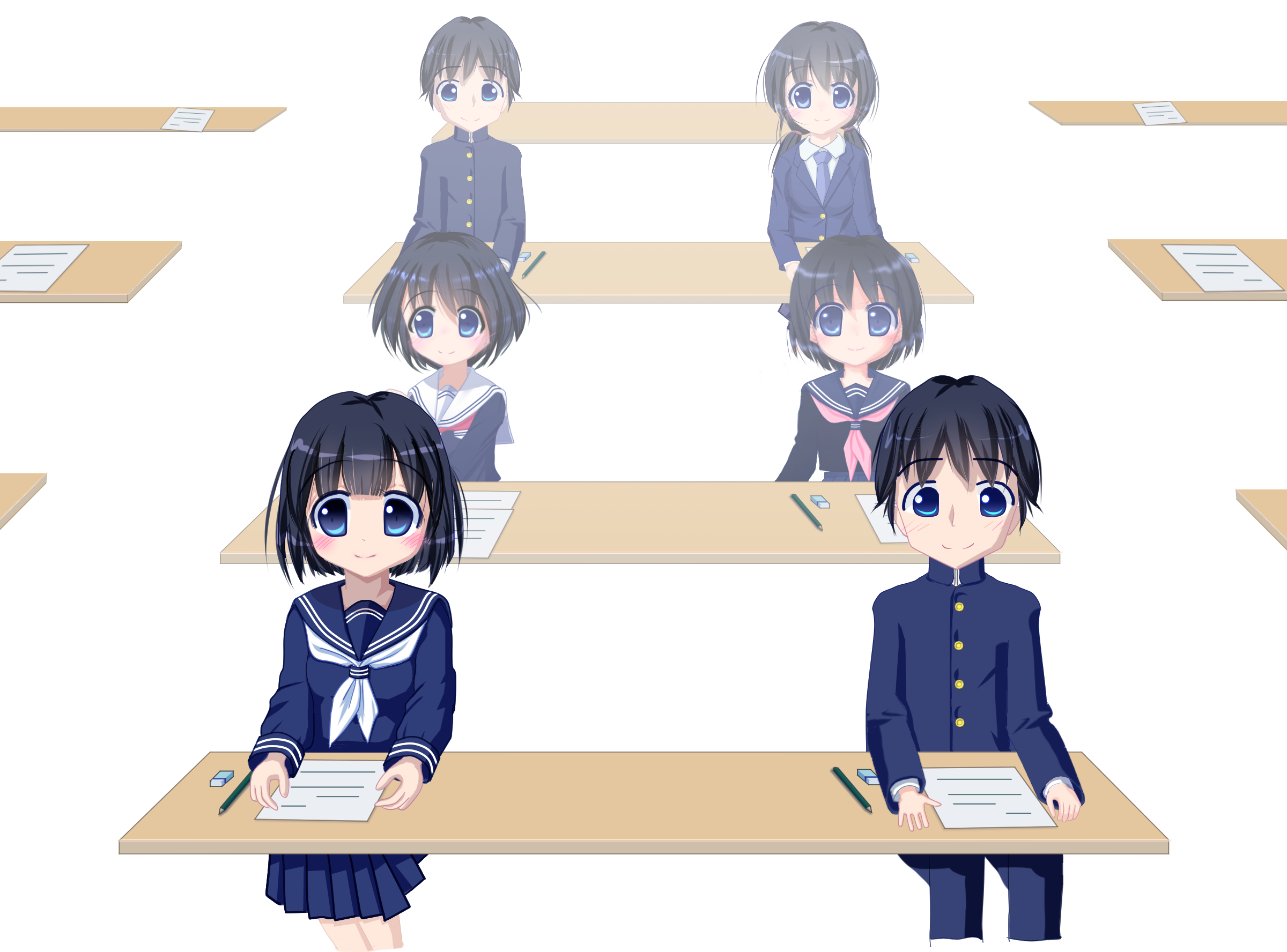

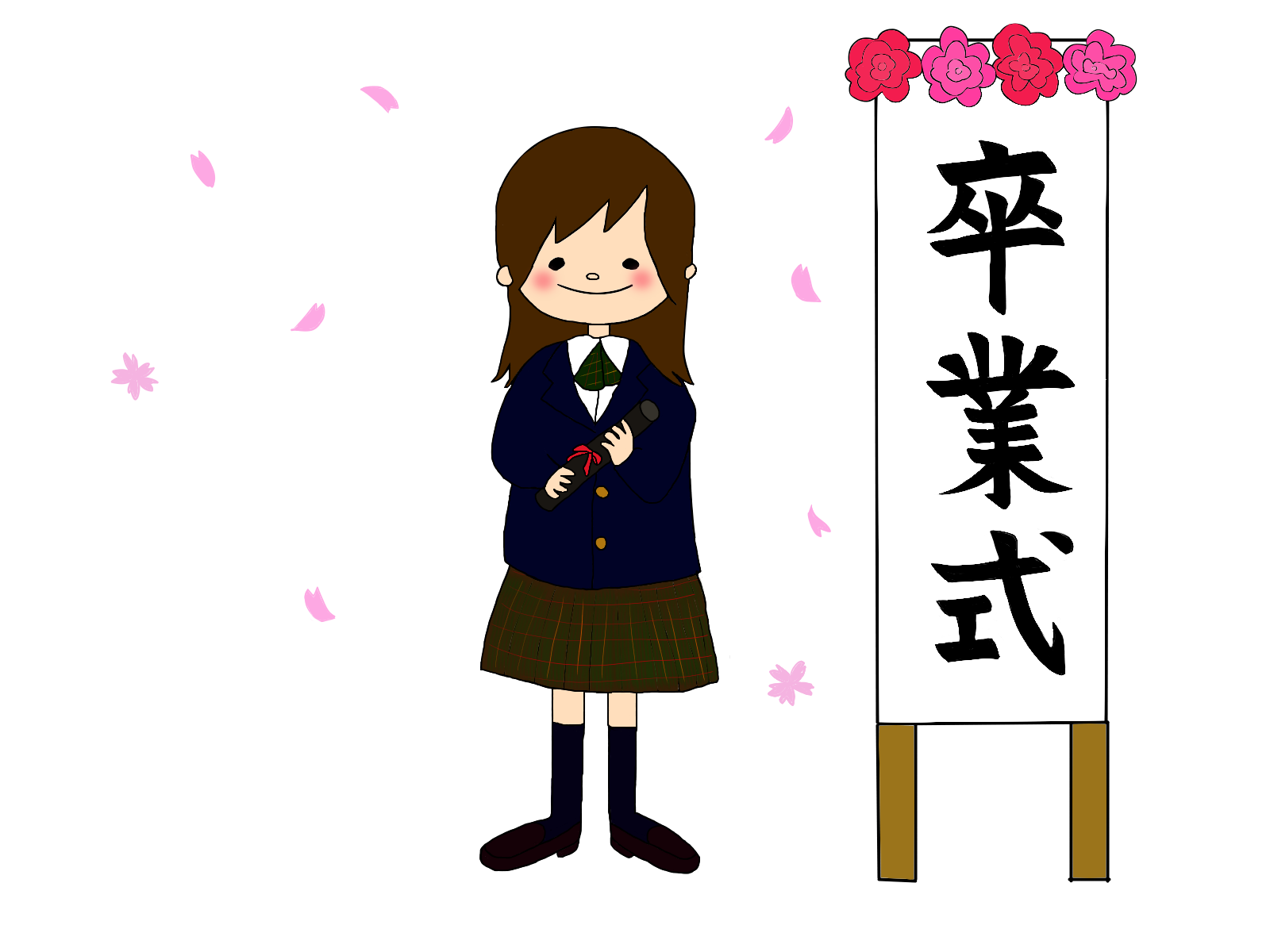
コメント