誰もが人生で何度かは経験する卒業式は、伝統が重んじられ、保護者や来賓もたくさんいるので、カチッとしたイメージが強いよね。先生たちから怒られながら、何度も何度も練習させられた思い出があるという人も多いはず。そんな固いイメージの卒業式を、もうちょっと面白くすることはできないものかと考えたことはない?
知り合いに造語症がいて、その人はいろいろな面白い言葉を使うんだよね。そこで、ふと「造語を使うと卒業式も面白くできるんじゃないかな」なんて考えが頭をよぎったんだよね。
そもそも造語症って何なのか、そして、造語を使ってどうやって卒業式も面白くできるか、ちょっと考えてみるね。
造語症とは
正確には造語症という病気はない
「造語症」という病気を聞いたことある?造語症について厳密に言うと、実は「造語症」という病気はなく、医者からそのように診断されることもないんだよね。造語症というのはアスペルガー症候群や統合失調症の人によく見られる症状のことを指して言うんだよ。
その症状は書いて字のごとく、言葉を作ってしまうことで、精神的疾患を持つ人が、新しい言葉を作ってはそれを使う、という症状を指しているよ。
造語症はアスペの一種
言葉を作るという経験は誰でも1度はしたことがあるだろうけど、造語症の場合は無意識で言葉を作ってしまうんだよね。しかも、作り出した言葉については「みんなも知っている」という態度なんだよね。
アスペルガー症候群や統合失調症における造語症の症状のことが分かっていれば、周りもそこまで気にしないんだろうけど、もし精神的疾患があることが知られていないと、周りからちょっと浮いた存在になっちゃうよね。
造語症診断テストで簡単に診断できる
造語症診断テストなんかもネット(【超簡単】造語症診断、7つのチェック項目答えるだけ)で簡単にできるので、周りから「何を言っているのか、話がよくわからない」とよく言われる人は、一度チェックしてみると良いかもしれないよ。精神的疾患が見つかる可能性もあるので、心配になったらちゃんとした医療機関を受診したほうが良いね。
造語症が作る造語はクリエイティブでキャッチーなものが多い
でも、造語症の人が作る言葉って、意外とクリエイティブでキャッチーなものが多いよ。毎年ノミネートされる新語、流行語もほとんどが造語だから、造語が人の興味を引くということは当然と言えば当然だよね。
造語を使えばいろいろ面白くできる
造語を上手に使えば、基本的にどんなものも面白くすることができるはず。もちろん、何が面白いかと思うレベルには個人差があるから、造語を使えば必ず大爆笑が取れるというわけではないよ。ある程度興味深い内容にできたり、固いイメージを柔らかくすることができるということね。
これは卒業式でも当てはまると言えるんだけど、詳しいことや具体的な内容は後で説明するね。他にも、真面目になりがちなプレゼンテーションなんかも造語を使えば面白く、興味深くすることが可能じゃないかな。
「あいうえお作文形式」で作る
造語は「あいうえお作文形式」で作ることができるよ。「「あいうえお作文」って何」って思うかもしれないけど、どこかで1度は聞いたことがあるはずだよ。
卒業式で例を挙げてみると、「そつぎょうしき」のあいうえお作文なら、
「そつぎょうしき」の「そ」=卒業の朝に、
「そつぎょうしき」の「つ」=募る思い、
「そつぎょうしき」の「ぎょ」=行事や授業で共に過ごした仲間、
「そつぎょうしき」の「う」=麗しい未来に向けて、
「そつぎょうしき」の「し」=出発する、
「そつぎょうしき」の「き」=希望に満ちた日、
みたいな感じね。ちょっとカッコよすぎるか。
造語をあいうえお作文形式で作る場合には、先に内容を考えてから、後で頭文字をくっつけて新しい言葉を作ることができるよ。
GAFAはあいうえお作文形式で作った造語
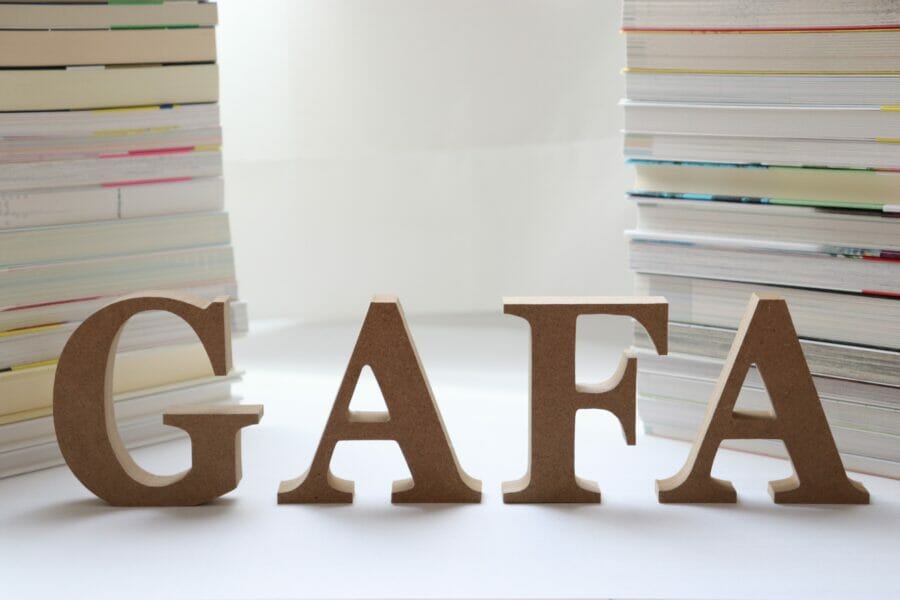
ちなみに、英単語もあいうえお作文形式で造語を作ることができるよ。英単語の例だと、アメリカのIT関連の会社の大手4社、Google、Apple、Facebook、Amazonの頭文字を取ってGAFAとか呼ぶのを聞いたことがない?これも辞書にはない単語で、英語版の造語だね。
「あいうえお作文形式」で要点を覚えてもらえる
プレゼンテーションをする際には「あいうえお作文形式」で要点を覚えさせることができるんだ。これは料理の「さしすせそ」とかを例に考えることができるね。料理に欠かせない調味料の頭文字を取って、
「さ」は「砂糖」、
「し」は「塩」、
「す」は「酢」、
「せ」は「醤油」(昔は「せうゆ」と書いたから)、
「そ」は「味噌」、
これをひとまとめにして「さしすせそ」と言うんだよね(味噌の部分は頭文字ではないけどね)。
造語を使った営業のコツのプレゼンの例
これと同じ手法で「営業のコツ」についてプレゼンをするなら、「営業は『あすにはし』が大切だよ」と始めることができるよ。「営業を成功させる『明日に橋』」としても良いかもね。
営業で大切な5つのこと、
「あ」=「相手のことを第一に考える」、
「す」=「スピード感のある対応」、
「に」=「(顧客の)ニーズを把握」、
「は」=「(顧客の)話をよく聞く」、
「し」は「商談を振り返る」、
と説明するわけね。
最初にポイントを挙げてから、本論ではそれぞれの要点を掘り下げると、わかりやすいよね。
プレゼンの要点をまとめて頭文字で造語を作る
このように、最初にプレゼンの要点をまとめて、それからそれぞれの要点の頭文字をくっつけて造語を作ることができるよ。覚えやすい言葉や発音しやすい言葉になるように意識することは必要だけど、そこまで難しいことじゃないよね。
造語をちょっと入れるだけで、プレゼンをより面白く効果的なものにすることができるよね。卒業式でも同じ要領で造語を作れば、面白いものにすることができるんだ。
別の方法でも造語は作れる
擬音語や擬態語をベースに造語を作る|造語の作り方
あいうえお作文形式以外にも、意外と簡単に造語は作れるよ。例えば、擬音語や擬態語をベースに、新しい言葉を作ることができるよね。
擬音語や擬態語って何かというところから説明すると、擬音語や擬態語は、実際には言葉として存在しないものを言葉にして表したものだよ。
骨がポキっと折れる|擬音語や擬態語をベースに造語を作る
例えば、骨が「ボキッと」折れるとかね。「ボキッと」が擬音語で、実際に骨が折れる時に大きな音は鳴らないけど、折れる時に聞こえそうな音を言葉として表現したのが「ボキッと」という言葉ね。折れる様子がよく伝わるよね。
ガーン|擬音語や擬態語をベースに造語を作る
一方、擬態語は動きや様子を表していて、ショックを受けた時の「ガーン」とかがそうだよね。態度や心の様子などをわかりやすく伝えることができる言葉で、日常生活でもよく使っているはずだよ。
自分が感じたことを表現すればいい|擬音語や擬態語をベースに造語を作る
擬音語や擬態語には明確なルールがないので、自分が思うように、感じるように表現すれば、簡単に造語になるよね。例えば、びっくりしたことを「ハフィー」とか、悲しいことを「チェン」と言ってもOK、意味不明と言われても全く問題ないよ。
既存の造語をアレンジする|擬音語や擬態語をベースに造語を作る
また、既存の擬音語や擬態語をアレンジしても造語を作ることもできるね。例えば、ショックを受けたことを表すための「ガーン」という擬態語をアレンジして「ガーン状態」とか、さらに短くして「ガン態」とか言うこともできるね。こういう類の造語は耳に残るので、印象付けるのにぴったりだよ。
卒業式っていうのは、若い学生がメインの行事だから、こういう擬音語や擬態語ベースの造語は特に受けやすいと言えるんだ。若者言葉には意味不明で何となくのニュアンスで伝えるものが多いよね。
造語で面白い卒業式にするポイント
造語を上手に使えば、固いイメージの卒業式も面白おかしくすることができるよ!しかも、卒業式の中には造語を入れることができそうなポイントがいくつもあるんだよね。
呼びかけ|造語で面白い卒業式にするポイント
卒業式と聞いて、多くの人がまず思い出すのが「呼びかけ」じゃないかな。「呼びかけ」とは、代表者が言った言葉をみんなで復唱するやつね。例えば、1人の生徒が「みんなで楽しんだ、修学旅行」と言った後に、卒業生全員で「修学旅行」と復唱したよね。
他にも、「一生懸命走った、マラソン大会」の後に「マラソン大会!」とか、「工夫を凝らして臨んだ、文化祭」の後に「文化祭!」とか、みんなも経験したことがあるはず。
校長式辞|造語で面白い卒業式にするポイント
卒業式で造語を使えそうな別の場面に、「校長式辞」もあるよね。校長先生の最後のあいさつで、これは校長先生のキャラクターにもよるけど、もともと面白い校長先生なら、確実にウケを狙うことができる場面だよ。
固い真面目な校長先生でも、造語を上手く使えば、爆笑を取ることはできなくても、興味深い式辞にすることが可能じゃない?聞いていて眠たくなるような話ではなく、もっと聞きたいと思わせる話になるよ。
もちろん校長先生の話を代わりに作ってあげることなんてできないから、あくまで希望にすぎないけど。でも、校長先生の話を聞きながら、いろいろな造語を妄想するだけでも面白くはなるね。
卒業生からのあいさつ、在校生からのあいさつ|造語で面白い卒業式にするポイント
さらに、卒業式で造語を使えるシーンには「卒業生からのあいさつ」や「在校生からのあいさつ」もあるよね。どちらも代表生徒がみんなの前でスピーチする場面になるけど、過度にふざけるとか、あまりにもくだけたものにすると、先生から怒られるかもしれないね。
造語を使ってちょっとだけ面白おかしくするのが最適だと言えるね。卒業生代表のあいさつは感動を呼び起こす大切な場面だけど、思い出に残る面白いあいさつにすることも可能だよ。
造語を使った面白い卒業式を考えてみた
では、実際にどんな造語を使えば卒業式を面白くできるのか、それぞれのシーン別に、いくつか例を考えてみたよ。
呼びかけにおける例|造語を使った面白い卒業式を考えてみた
呼びかけの時に、耳に残るキャッチーな造語を入れてみよう。例えば、協力してやったことを「コポる」とかね。コーポレイト(協力する)から作った造語で、この言葉を使う場面としては、「みんなでコポッた文化祭」「文化祭!」など考えられるね。
後に続く生徒がちょっと説明入れたら、さらに良いかも。「1人1人がアイディアを出して、作り上げました」みたいにね。
使う造語がその学校で流行っていたら、さらに良いよね。他の人が知らない言葉だったとしても、学校の、特に卒業生の間で流行ってた言葉なら、すごく印象に残るんじゃないかな。
復唱を使った例|造語を使った面白い卒業式を考えてみた
造語を復唱させるのも面白いかもしれないね。例えば、世紀の一戦を「デカバトル」と言って、「3分団で競い合った、デカバトル」「デカバトル!」とか。「体育祭では遅くまで練習したしました」とここでも補足を入れておこう。そうすれば、保護者や来賓も「あぁ、体育祭のことか」と理解できるよね。
バトルという言葉から、デカバトルの意味も正しく予想してくれるはずだよ。家に帰った後で、お母さんから「デカバトルって何のこと?」「面白い卒業式ね、変な学校」とか突っ込まれれば大成功!
校長式辞における例|造語を使った面白い卒業式を考えてみた
校長式辞で「あいうえお作文」が上手に使われていたら、面白い、印象に残る卒業式になるよね。「卒業したら立派な人になってください」と、校長先生は卒業式のあいさつでよく言うじゃない。その時に、「卒業して社会人として生きていく上で『ひのまる』を意識してください」というエールを送ったら面白いよね。
そして、
「ひのまる」の「ひ」=「人に迷惑をかけない」、
「ひのまる」の「の」=「(人)の役に立つよう努力する」、
「ひのまる」の「ま」=「周りのことに気を配る」、
「ひのまる」の「る」=「ルールとモラルを守る」、
と説明されれば、社会人として生きていく上で大切なことが覚えやすく、ユーモラスに伝わるよね。
卒業生からの挨拶における例|造語を使った面白い卒業式を考えてみた
卒業生からのあいさつでは、卒業生たちが同感できるような造語をいくつか入れてみたよ。みんなが印象に残っているイベントから言葉を作ることができるよね。
京都すること|卒業生からの挨拶における造語の例
例えば、修学旅行で京都に行ったなら、「京都」という言葉に独自の意味を持たせて使っても面白いかもよ。「いつでも京都することを意識します」と言って、修学旅行の時の一致団結やマナーを心がけた行動を「京都」という言葉に集約するわけね。
文化イズム|卒業生からの挨拶における造語の例
他にも、「文化祭イズム」という造語で、文化祭の時の独特の空気感、ドキドキワクワクしながらみんなで協力して作り上げていくことを表現するとか。
「社会人になっても文化祭イズムを忘れずに生きていきます」とか、「就職して仲間と仕事をする時にも、この高校で培った文化祭イズムを活かして頑張ります」とか言うことができるね。文化祭に積極的に携わったみんなにとって、すごく印象に残る言葉になるはずだよ。
固い卒業式を造語で柔らかくしよう
卒業式って固いイメージがあるけど、造語を使えば面白くすることができるよね。くだけ過ぎずに、ちょうどいい感じで面白おかしくすることができるんじゃないかな。
今回、妄想で面白い卒業式を考えてみたけど、実際にやってみてもいいかもしれないね。
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。



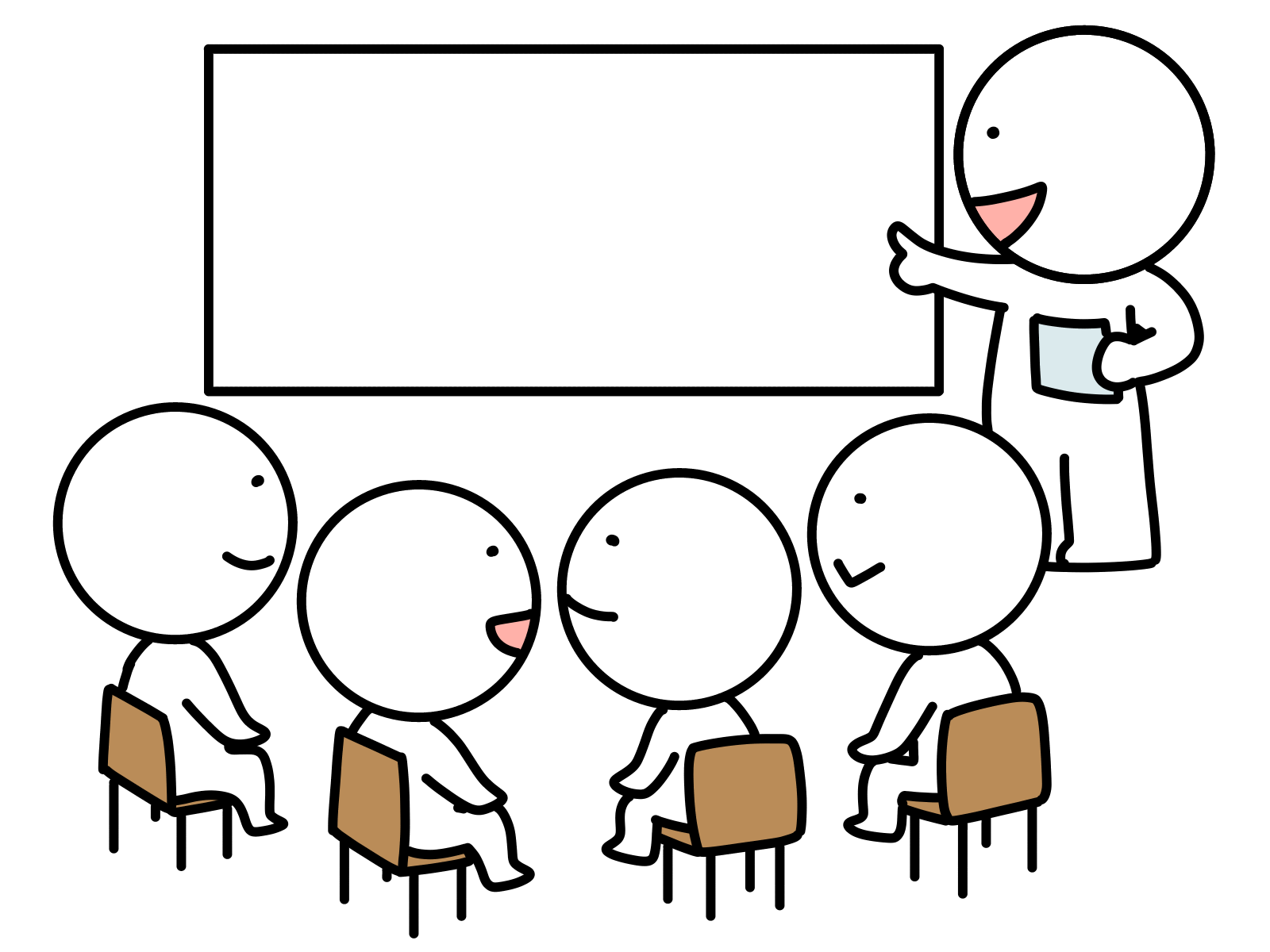
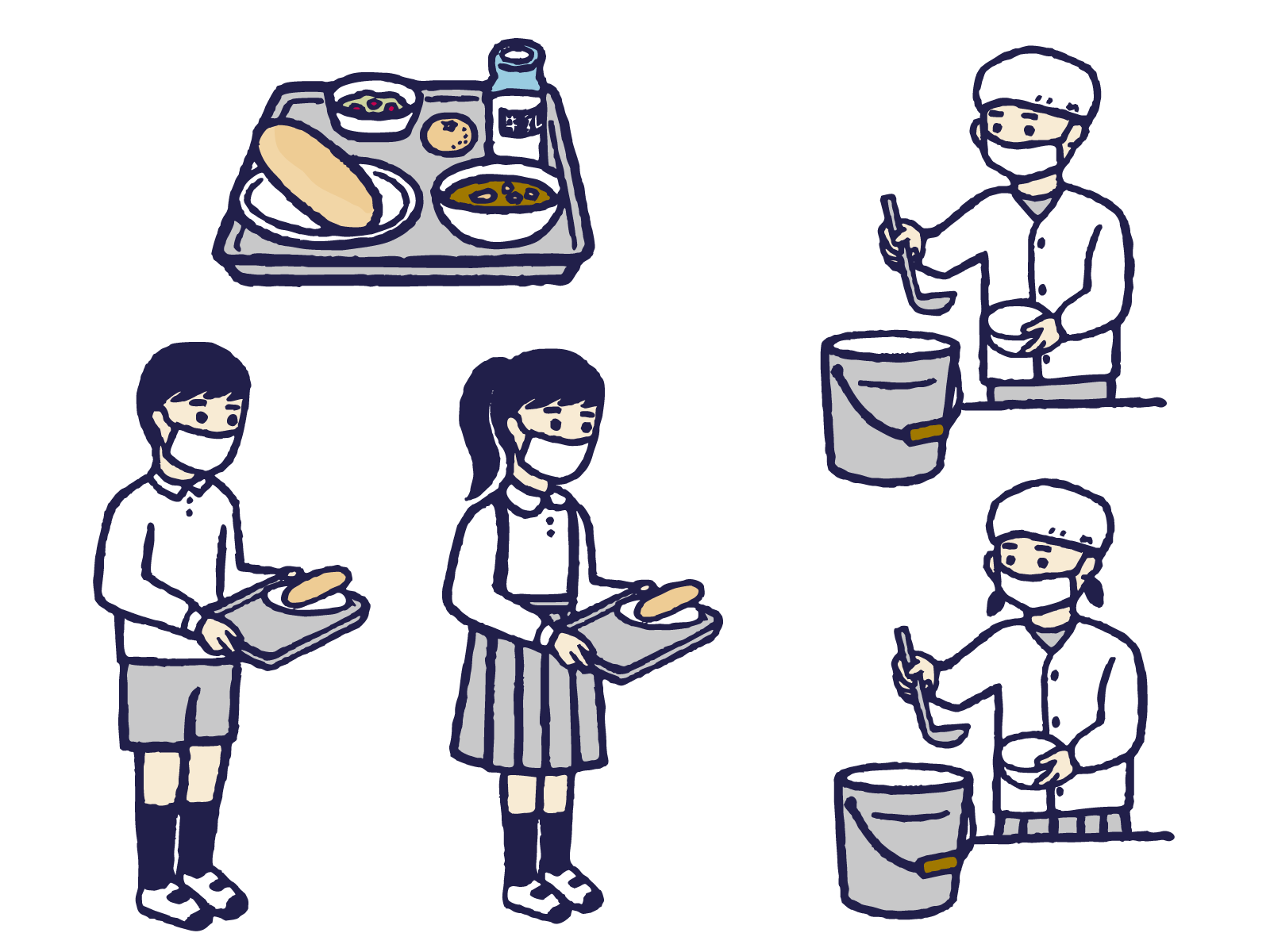
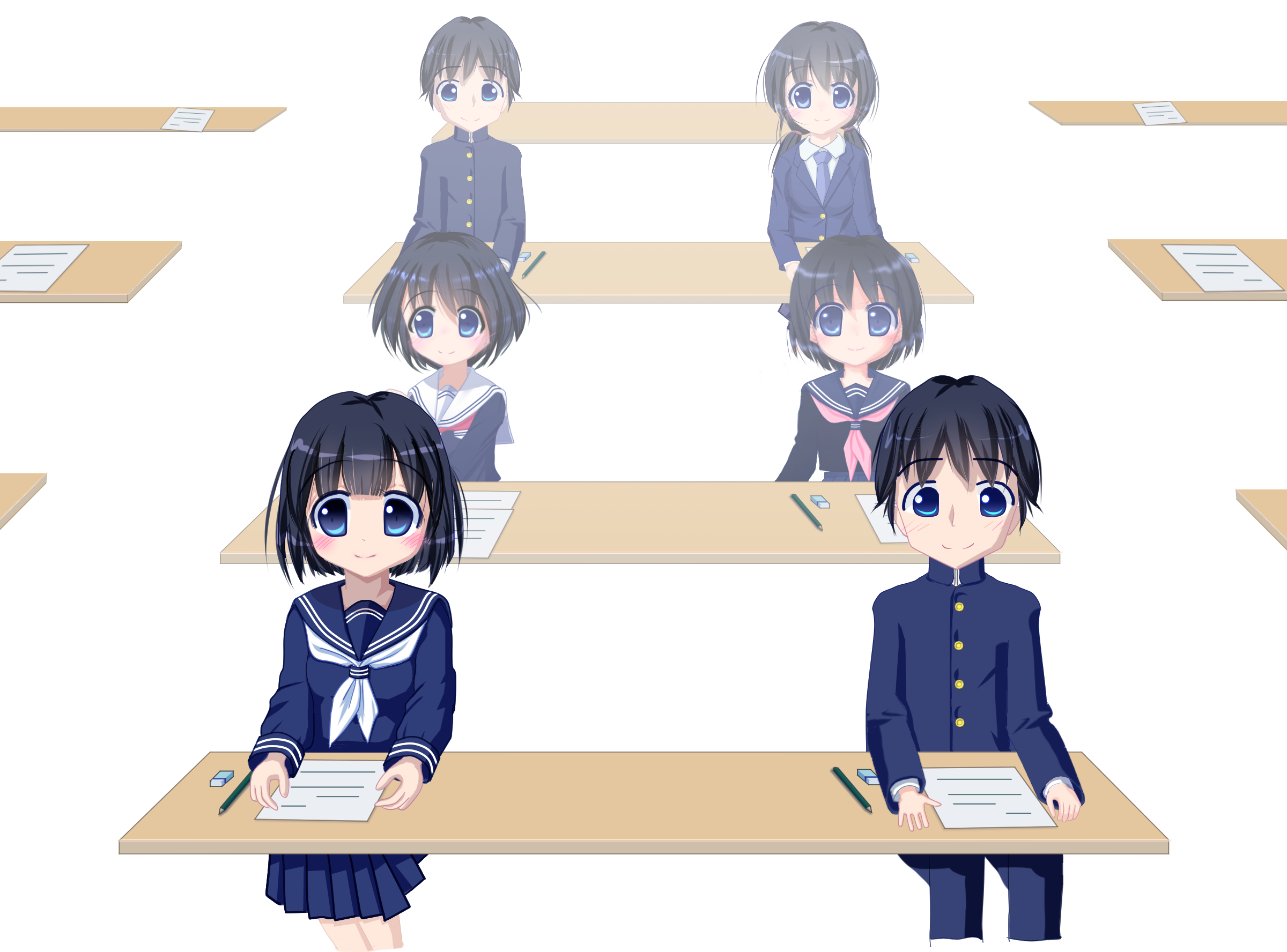
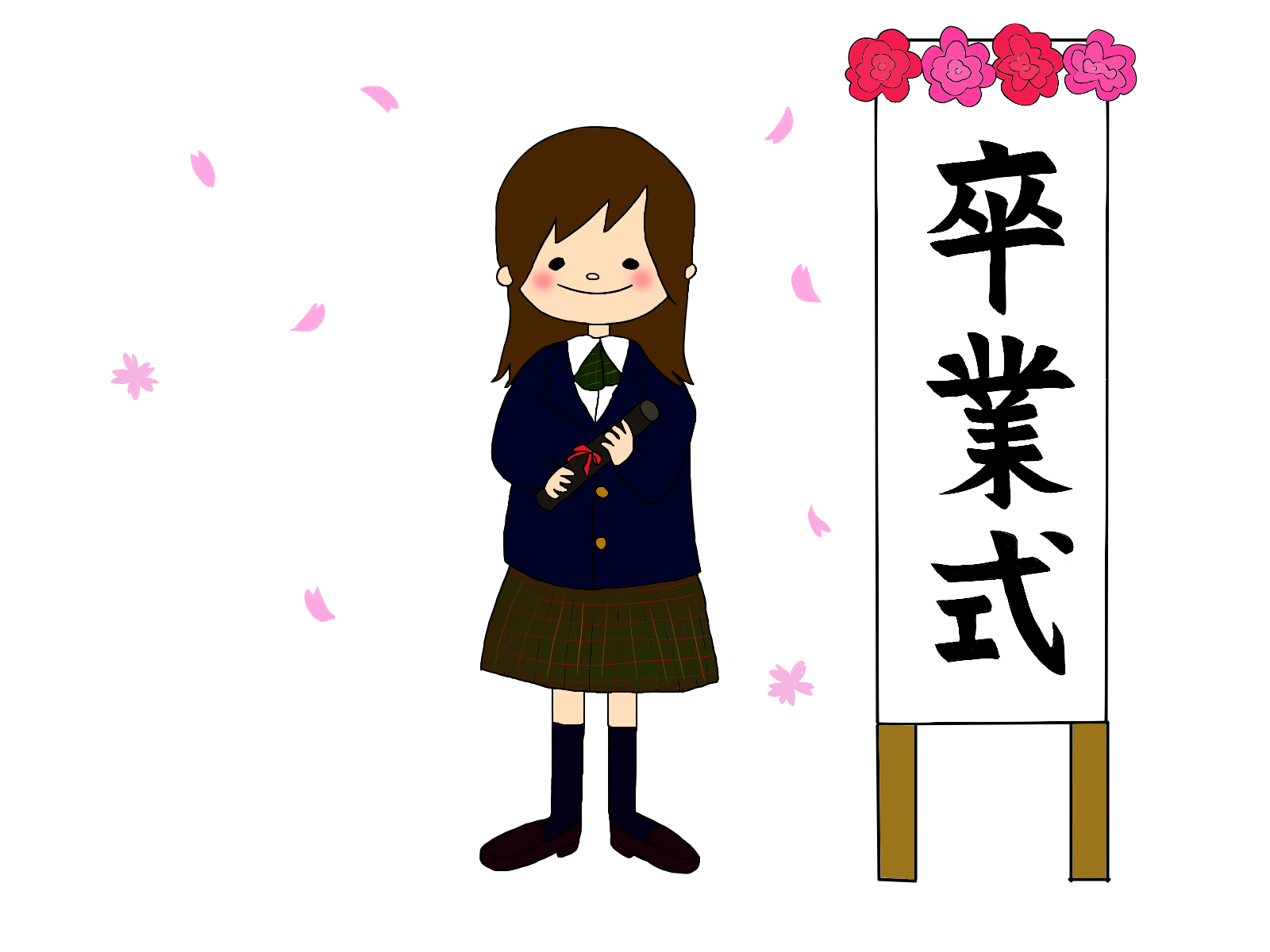

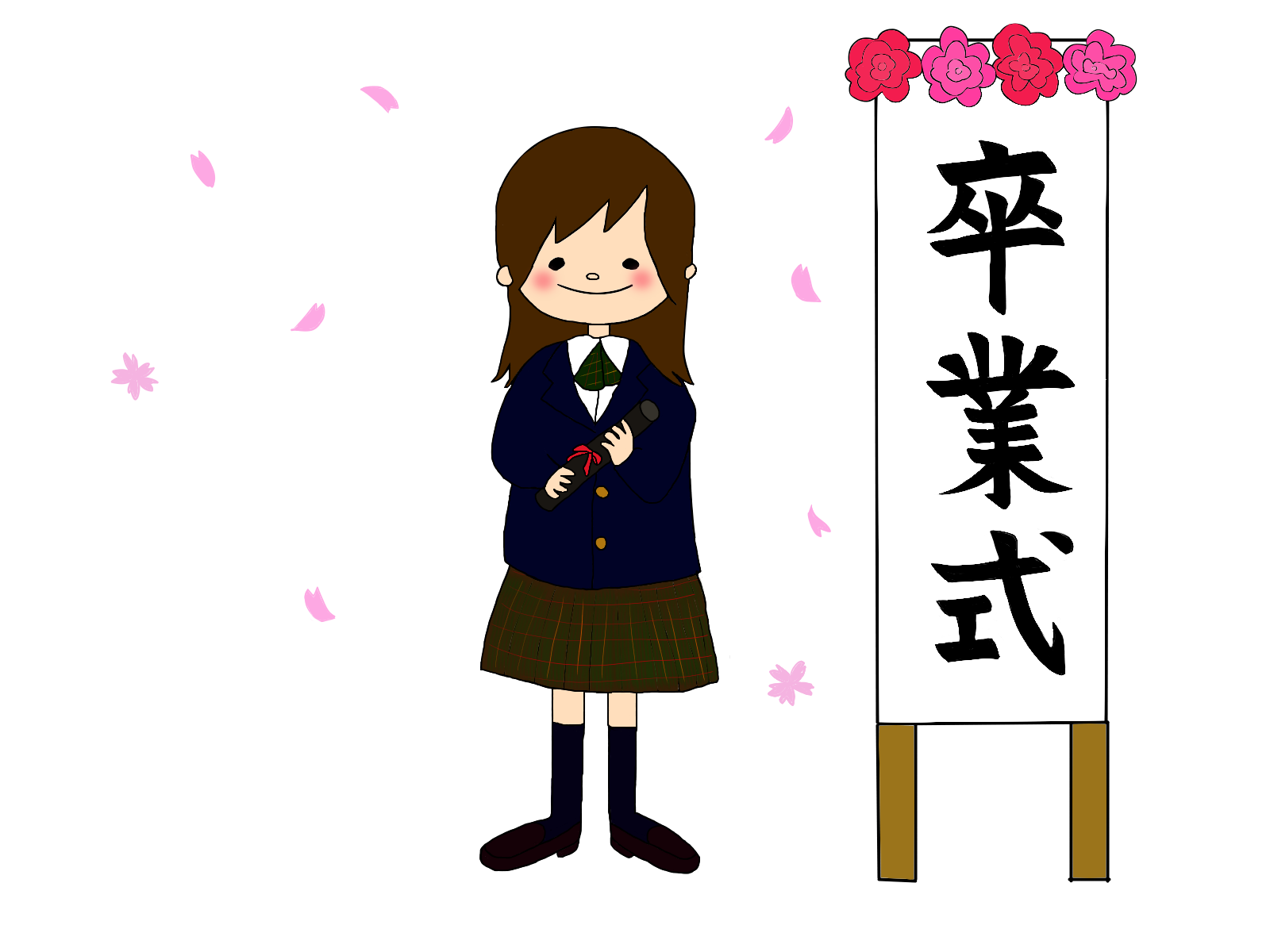
コメント