仏教と聞くと、法話や説法、写経といったいわゆる難しい単語が思い浮かぶよね。日本の伝統的な宗教の1つではあるものの、日常生活でお寺の住職さんと定期的に接するという人はそれほど多くないはず。
修学旅行で京都や奈良などの有名な寺院へ行った経験はあるものの、それ以上は詳しく知らないという人も少なくないよね。面白いことに、仏教に関連した言葉や近年のイベントなどを調べていくと、いくつも新しい造語が生み出されているんだ。
特に、浄土宗に関連した情報を見ていくと、難しい物事をわかりやすく表現するために造語を活用しているケースがよく見られているよ。
浄土宗に関連した造語
サンスクリット語
仏教と深く結びついている言語と言えばサンスクリット語。古代インドやその周辺地域で用いられていた言語で、ヒンズー教や仏教の用語に数多く取り入れられているんだ。浄土宗の機関誌である「季刊かるな」は、サンスクリット語の「カルナー」をもじった造語だよ。
もともと「カルナー」は「慈悲」を意味するサンスクリット語で、苦しい経験をした人は他人のつらい状況を理解してあげられるという浄土宗の教えにも深いつながりを持つ言葉なんだ。
「季刊かるな」という雑誌のタイトルは、浄土宗の持つこうした教えを伝えたいという思いを込めて作られた造語だね。
玄禮和尚が生み出した造語は「聞施」
浄土宗の西山禅林寺派大覚寺で住職をしておられる玄禮和尚が生み出した造語は「聞施」だよ。読み方は「もんせ」で、心に悩みを持つ人が話を聞いてほしいと思うとき、耳を傾けてあげることで施しをするという意味の言葉なんだ。
仏教の代表的な教えに「無財の七施」という表現があるよね。これは
- 「眼施(優しい視線を常に送る)」
- 「和顔施(笑顔でいつも接する)」
- 「言辞施(丁寧な言葉をいつも選ぶ)」
- 「身施(公正な行動をとる)」
- 「心施(正しい思いをいつも抱く)」
- 「床座施(必要な人に場所を譲る)」
- 「房舎施(家を他の人へ提供する)」
という7種類の異なる施しのこと。
玄禮和尚はそこに新たな観点からの施しを提案したということだね。実際、悩みを何でも打ち明けられる友人というのは人生を豊かにしてくれる素晴らしい財産で、「聞施」はそれを仏教的な観点と巧みにコラボレーションさせたとても意味深い造語と言えるね。
てらギャラ
浄土宗の公式サイトなどで近年用いられている造語と言えば「てらギャラ」があるね。「てら」はもちろん「寺院」のこと。「ギャラ」は「ギャラリー」で、これら2つの単語を組み合わせてポップな造語を作ったんだよ。
浄土宗では一般の人を念頭に置いて「開かれた寺院」をコンセプトとしたキャンペーンを展開していて、その名称が「てらギャラ」。このイベントでは長い歴史を持つお寺に保管されている価値の高い掛け軸や宝物などを定期的に一般公開しているんだ。
「てらギャラ」で展示される品々のラインナップは毎回変わるので、いつ行っても新鮮な気分で楽しむことができるよね。「なむちゃん」という浄土宗の公式キャラクターによるイベントも用意されているよ。
この名前もサンスクリット語の「ナマス」に由来する仏教用語の「南無」から来ていることを考えると、造語の1つといっても間違いではないよね。
茶坊えにし
浄土宗の定期イベントに関連した造語としてもう1つ挙げられるのが「茶坊えにし」。これは毎月最後の土曜日に浄土宗の僧侶が中心となって開催しているイベントだよ。「茶坊えにし」という名称は、お茶を嗜む「茶房」と「お坊さん」、そして繋がりや関わり合いを意味する「縁」という3つの言葉を組み合わせた表現なんだ。
「縁(えん・えにし)」という表現が人間関係に関する仏教の教えにたびたび登場しているというのも興味深いポイントだよね。「茶坊えにし」は浅草エリアにある複数の浄土宗寺院で開催されていて、イベントの内容は法要や匂い袋の作成など毎月異なるものが準備されるんだ。
年齢を問わず、お坊さんと文字通りお茶を楽しみながら身近に触れ合えるイベントを開催したいというコンセプトがよく伝わる、堅苦しい雰囲気をまったく感じさせない造語だから、若者にも心地よく響くよね。
寺社コン
浄土宗がコラボレーションしている興味深い企画として「寺社コン」があるね。これはお寺や神社を指す「寺社」と結婚相手を探す「婚活」の2単語を組み合わせた造語で、男女の縁結びをサポートするという企画を指しているよ。
メインターゲットとしているのは神社仏閣めぐりを趣味としている男女で、同じ楽しみを共有できる人たちに出会いの場を提供したいということから、東京都港区にある來迎山道往寺などで開催されているんだ。
近年、歴史にとても通じている女性たち、いわゆる「歴女」がメディアなどでたびたび取り上げられるよね。「寺社コン」では、「歴女」の中でも特に「寺社好き歴女」が多く申し込みをしているよ。
興味深いことに「寺社コン」では、静かに写経を楽しむ「写経コン」をはじめとして、仏教にまつわる様々なイベントが毎回準備されているんだ。感性や趣味が同じ人と一緒にイベントを楽しんだ後は、懇親会で自由に会話を楽しむというのが流れになっているよ。
仏教を知ってもらうため時代の流れに合わせた提案を積極的にしていくという熱い思いが「寺社コン」という造語には感じられるね。
このほかにも、浄土宗のお寺では「安らぎ」を意味するサンスクリット語「サラナ」という単語を使った造語がイベントの名称などによく用いられているよ。
仏教全般に関連した造語
寺庭
宗派に関わりなく、仏教に関連してよく耳にする造語の1つが「寺庭(じてい)」だね。これは住職の配偶者、もしくは家族のことを指す表現で、かなり歴史がある表現だね。妻の役割に関して「家庭を守る」という見方が一般的だった時代に、「住職は家ではなく寺に住んでいるのだから」という理由で「家」を「寺」に置き換えた「寺庭」という言葉が生まれたんだ。
寺庭婦人
最近では「寺庭婦人」という表現が用いられることもあるね。「寺庭」となる人にはお寺の掃除から参拝する人の対応、さらには寺庭婦人たちの会合出席など、裏方としての仕事がたくさんあることから、檀家さんからは尊敬の念を込めて「寺庭」もしくは「寺庭婦人」と呼ばれることが多いよ。
土徳
浄土真宗に伝わる有名な造語と言えば「土徳」があるね。仏教では、周囲の人や世の中のためになる言動を「徳」というよね。「土徳」という言葉は、19世紀末期に活躍した哲学者の柳宗悦が考案したもので、長年にわたって積み上げられてきた風土が人の心や歩みに良い影響を及ぼし、正しい行動を取るように導いているという考えのこと。
特に、富山県南砺市近郊ではこの「土徳」という考えが広く知られているよ。
近年の仏教に関わる造語
「モシュ印」と「コケ寺リウム」
仏教と芸術がコラボレーションして大きな注目を浴びたのが「モシュ印」と「コケ寺リウム」という2つの造語だね。「モシュ印」は「御朱印」と英語の「moss(コケ)」を組み合わせた表現だよ。御朱印は寺院を参拝したときにもらえる印影のことで、最近では日本各地の寺院でユニークな御朱印を集める「御朱印巡り」が話題になったよね。
この御朱印をコケで表現しようというアートの取り組みが「モシュ印」なんだ。白い台紙に緑のコケで形作られた御朱印の文字が見事に映えているよ。いくつもの仏教寺院がこの企画に参加したことからかなり話題になったよね。
「コケ寺リウム」
「コケ寺リウム」は、「お寺」と「コケリウム」の2単語をあわせた造語だね。「コケリウム」はガラスの水槽やアクリルの器などでコケを育てて楽しむこと。器の形や中に置くアイテムをアレンジしながらいろいろな種類のコケと組み合わせることで、芸術的な仕上がりになることもあるよ。
「コケ寺リウム」は、透明なガラスの器にコラボレーションしているお寺のジオラマを設置して、その周りに色とりどりのコケを配置したアート作品のこと。作品はそれぞれのお寺で一般公開されて大好評だったね。時間の経過とともにコケが成長していくので、毎回お寺へ参拝するたびに器の中に広がる世界が変化していく様子を楽しめるよ。
掛け軸や屏風といった印象が強い仏教のアートも、現代美術とコラボレーションすることで新たな広がりが生み出されるね。その過程で新しい造語ができているのも見逃せないポイント!
オテラート
仏教とアートのコラボレーションは石川県金沢市でもおこなわれているよ。2019年に開催されたイベントのテーマは「お寺」と「アート」を直接組み合わせた造語で「オテラート」。お寺をテーマにして彫刻作品や絵画などが制作され、地域のいろいろなお寺に飾られたんだ。どの作品も風格あるお寺の雰囲気と見事にマッチしていたよ。
国内外で活躍するプロの芸術家だけでなく地元の芸大生などもこのイベントに参加したことで、地域全体で「オテラート」を盛り上げようという機運が高まったよ。このイベントで制作された作品は引き続き無料で観賞することができるから、お寺参りへ行く機会を活用して家族で楽しむというのもお勧めだね。
ポーセラーツ
アートを体験する場所としてお寺の門戸を積極的に開放しているのが新潟県上越市にある浄土真宗の浄善寺。ここでは「ポーセラーツ」の体験イベントを開催しているよ。「ポーセラーツ」とは「Porcelain(磁器)」と「Art(芸術)」を組み合わせた造語で、白磁器に自分で好きなデザインをしていくというもの。
国の有形文化財に指定されている歴史ある寺社で厳かな雰囲気に包まれながら芸術を学ぶというのはなかなか他ではできない経験だよね。
寺考香
東京都府中市にある普賢寺で開催されているイベント名は「寺考香」。これは
- 「お寺へ行く」
- 「座禅を組んで深く思考する」
- 「お香の香りを感じながら過ごす」
という3つのアクションから漢字を1文字ずつ集めて組み合わせた造語だね。
非日常に身を置いてじっくりと考えることで、自分の内面を整理したり思考をリセットしたりできるという興味深いイベント。仏教にあまり馴染みのない人でも気軽に参加できると評判だよ。
いとくら
仏教の古い写経は考古学的な文献として高い価値を持っているので、経蔵と呼ばれる場所で大切に保管されているんだ。その写経が持つ意味や内容、また保存方法について詳しく解説しているニュースレターのタイトルが「いとくら」。これは「経蔵」という言葉を独特な方法で読み替えした造語だよ。
「経」という文字の由来はサンスクリット語で、本来の意味は「いと」。そこで、「蔵」を訓読みした「くら」と組み合わせて「いとくら」となったわけだね。
仏教と深いつながりを持つ言語をさり気なくリンクさせてタイトルに織り込むテクニックが見事だよね!
墓じまい
最近メディアなどで耳にするようになった造語といえば「墓じまい」。これは「お墓」と片付けて終わりにする「仕舞い」をあわせた表現で、先祖代々のお墓を処分して更地にする手続きのことだね。
少子高齢化の影響によってお墓を継ぐ人がいなかったり、子どもや孫がみんな遠方に住んでいてお墓の管理が難しかったりという理由から、「墓じまいをしよう」と考える人が増えているよ。ただし、「墓じまい」をして取り出した遺骨に関しては、簡単に処分をすることができないから、市役所などへ事前に問い合わせて確認しておくことが大切だね。
一般的には他の場所へ納骨する「改装」か、自宅で保管する「手元供養」を選ぶ人が多いよ。また、トラブルを避けるためにこれまで管理をしてくれた寺院の人へ「墓じまい」をする理由について丁寧に説明することも大切だね。
まとめ
「仏教」と聞くと、葬儀などの時にお坊さんの読経を聞くという、イベント限定的なイメージを持つ人が多いよね。長い伝統を持っているのは凄いこととはいえ、それが周囲との距離感を生み出してしまっては元も子もない。
そこで、「葬式や法事の時に見るもの」といったイメージや偏った印象を変えて、一般の人から仏教をより身近な存在と感じてもらうために、わかりやすい表現方法として造語を活用するケースが増えてきているんだ。
これは浄土宗に限らず、さまざまな宗派で取り組みが行われているよ。近所にあるお寺の標語などを見て「これはもしかして造語なのかな?」と思ったら、ちょっと立ち寄って住職さんにお話を伺ってみるのもきっといい経験になるよね!
造語の関連用語について詳しく知りたいそこのあなた!「【保存版】造語の関連用語まとめ」をご覧ください。
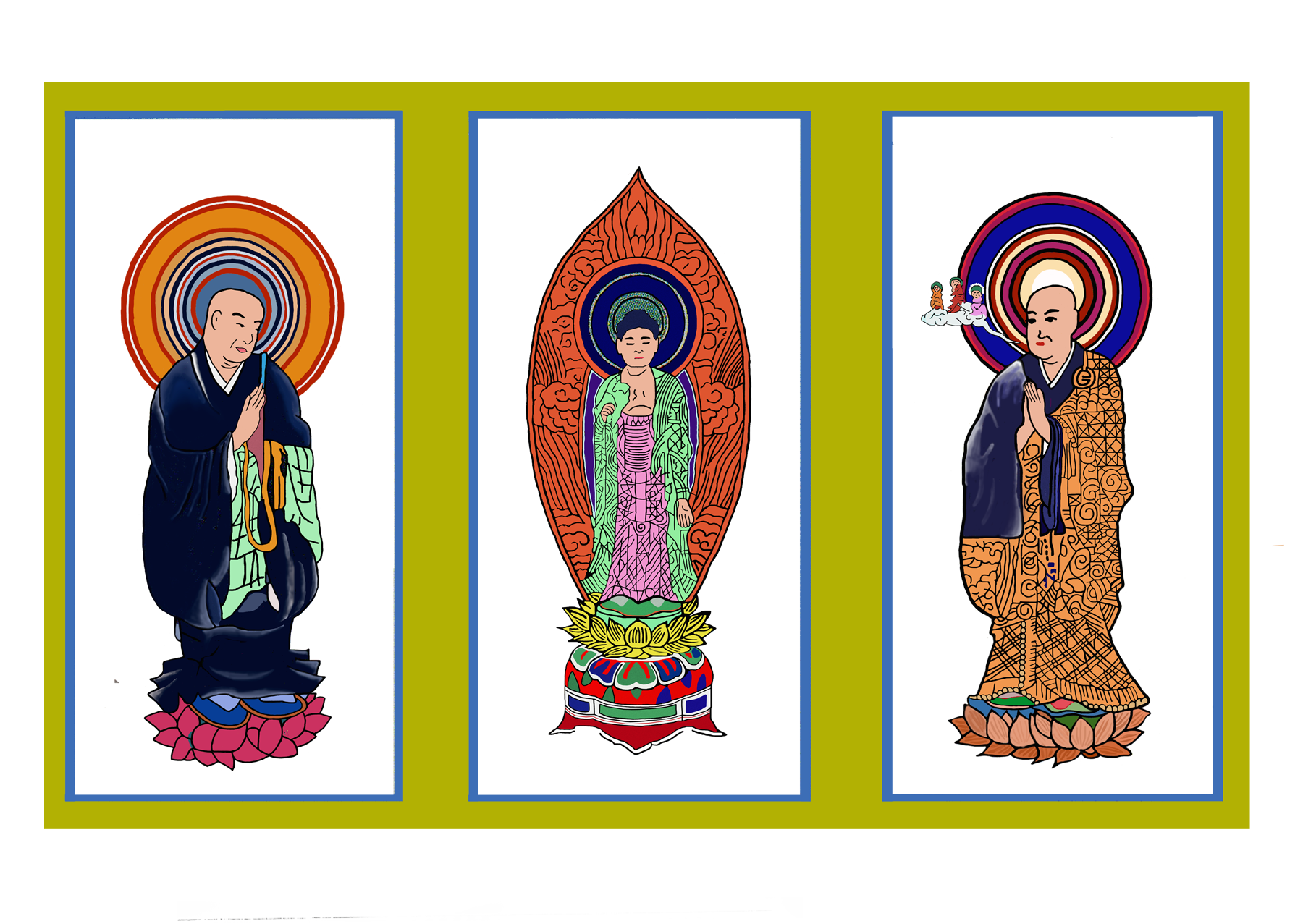
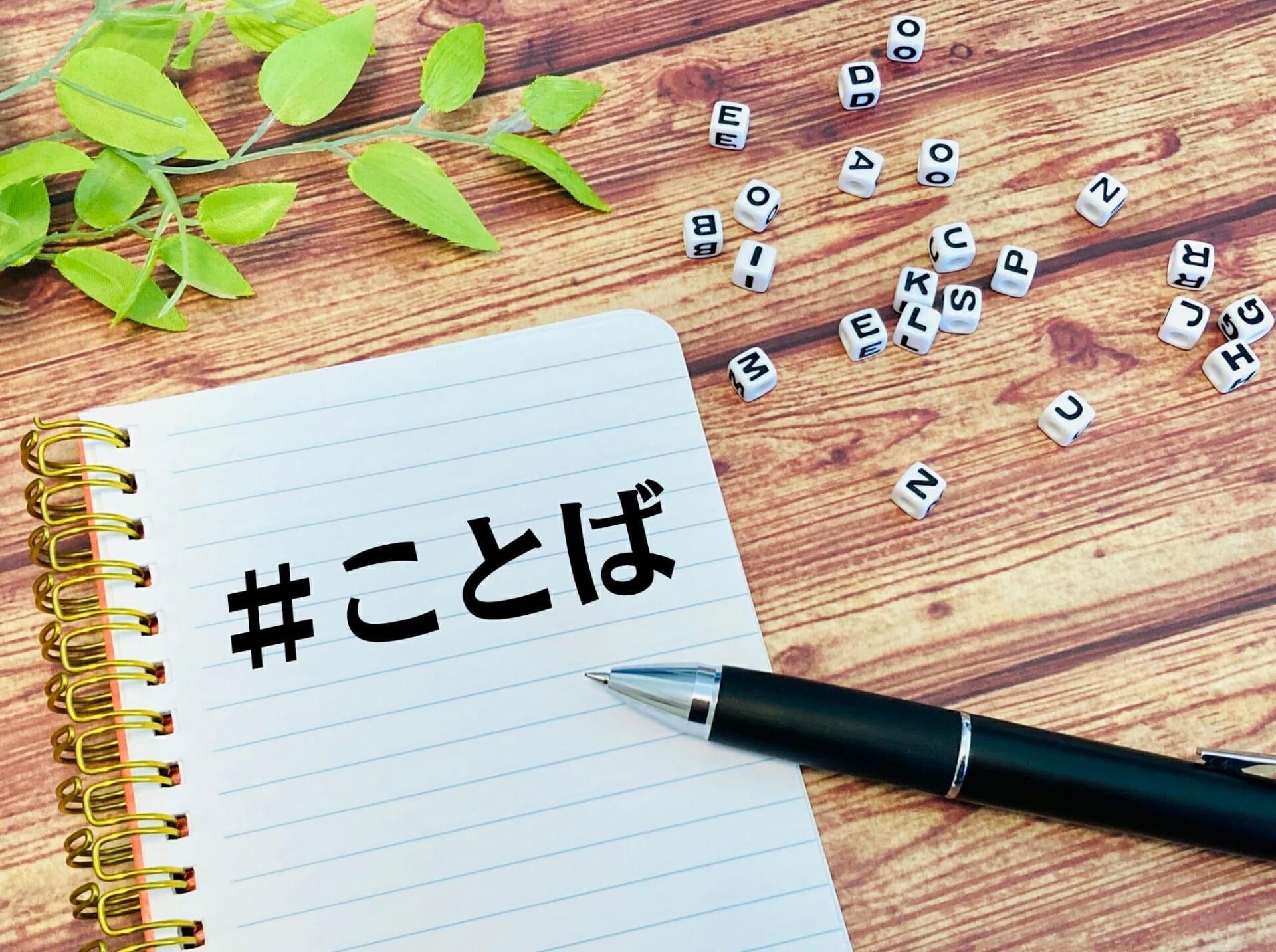
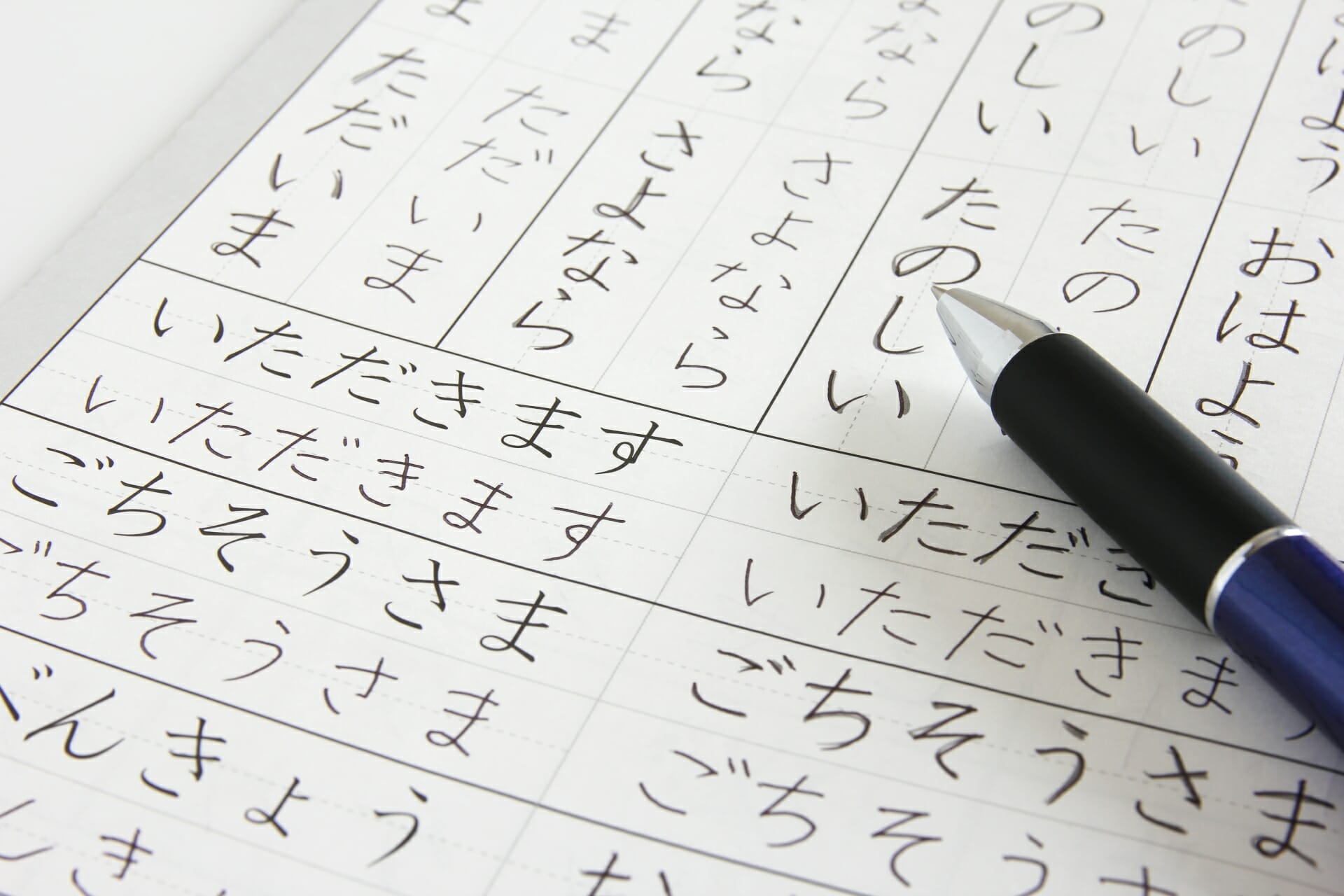

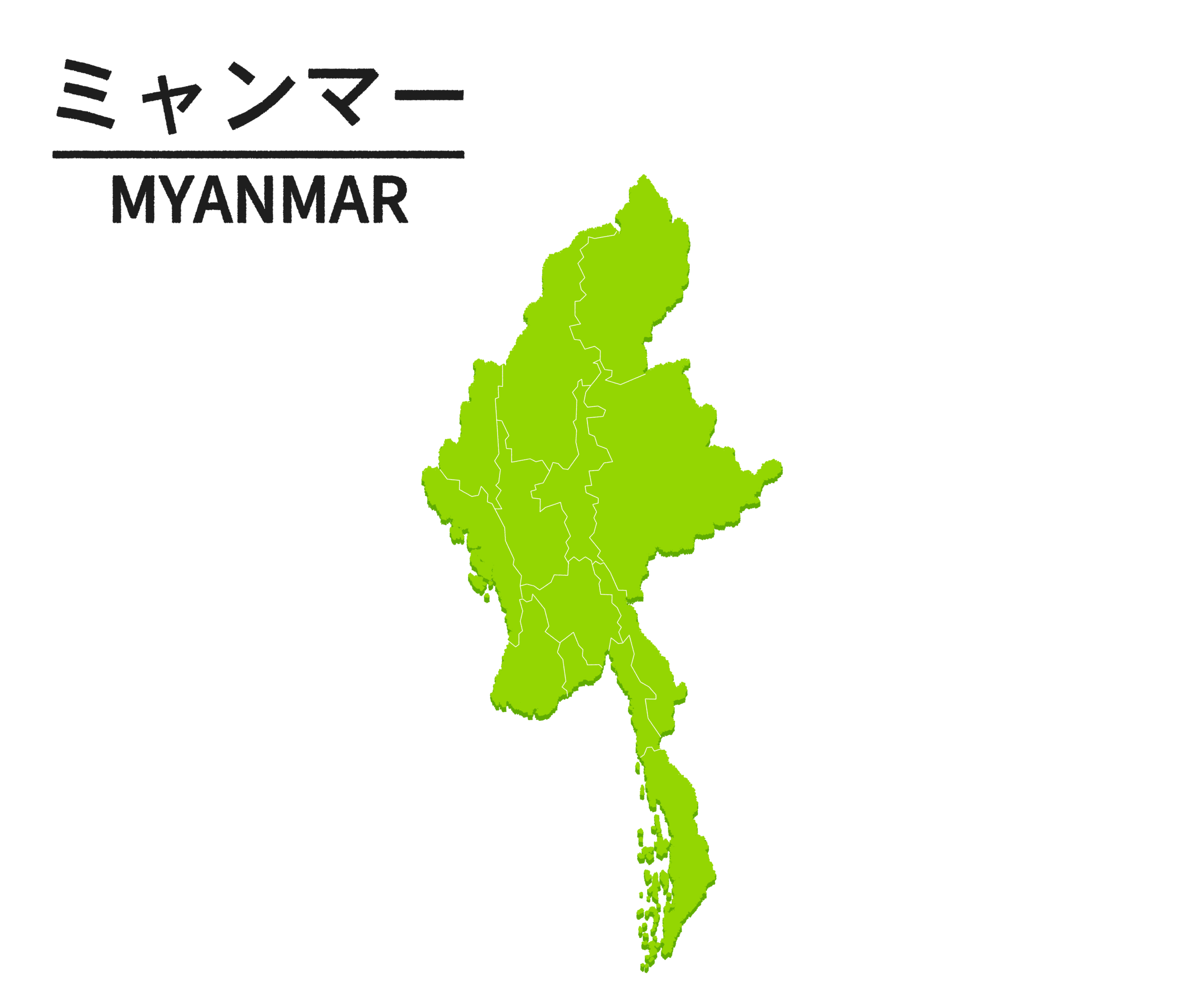
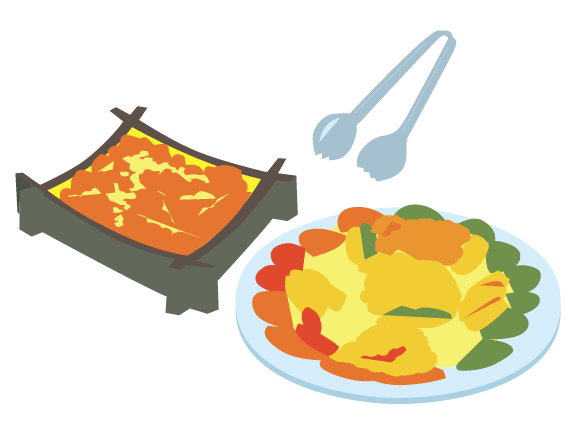


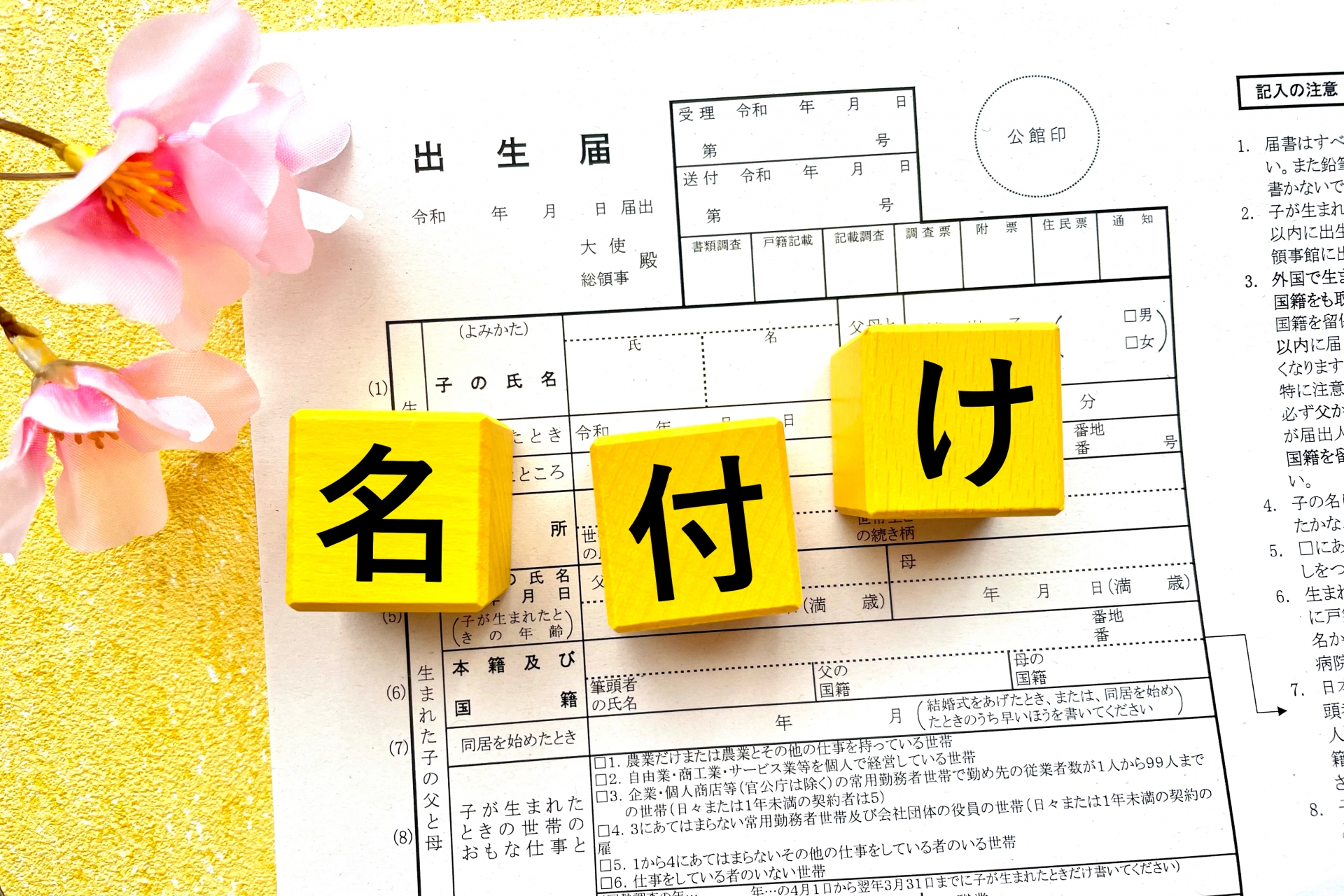
コメント