造語は記憶に残りやすいというメリットがあることから、日常会話だけでなくCMや広告などビジネスの分野でも広く活用されているよね。ただ、造語が頻繁に生まれているのはとりわけ学生たちの会話なんだ。
授業の前後で交わされる会話の中には、ウィットに富んだ造語がたくさんあって実に面白い!哀愁を感じさせるものからややブラックなものまで、イマジネーションに溢れる若者たちの造語を文法的な観点から分類しつつ見てみよう!
プラス法から生まれた造語
EdTech|プラス法から生まれた造語
プラス法とは、2つの言葉をつなぎ合わせて新しい1語を作るという方法のこと。代表例として「EdTech」が挙げられるよ。これは高校や大学の教育に関して経済産業省から発表された造語で、「Education(教育)」と「Technology(テクノロジー)」をプラスした表現だね。
授業を充実させるために、テクノロジーをいっそう活用して講義のレベルアップを図るべきというコンセプトを示していて、情報関連の授業でも耳にすることがあるはずだよ。表現そのものが短くてシンプルだから言わんとすることはすぐに分かっていいよね。
口からマーライオン|プラス法から生まれた造語
「口からマーライオン」は大学生の間で使われているプラス法の造語だね。マーライオンと聞くと、大抵の人はシンガポールのシンボルマークで、口から水が勢いよく噴き出している様子をイメージするよね。
そこにあえて「口から」という表現をプラスすることで、「飲み過ぎた人が勢いよく嘔吐している様子」という意味を持たせているよ。前日にお酒を飲み過ぎて授業中調子が悪いということを遠回しに伝えることが可能な造語だね。
ピー逃げ|プラス法から生まれた造語
授業の出席に関連して生まれたプラス法の造語としては「ピー逃げ」もあるよ。これは授業の出席確認をICカードなどで実施している学校で使われている表現だね。
ICカードをかざしたときに端末が発する「ピッ」という読み取り音と、授業を受けずにどこかへ行ってしまう「逃げる」を組み合わせた言葉で、出欠確認の手続きだけ済ませたらそのまま講義を受けずに去ってしまう行為を指しているよ。
内容そのものはあまり褒められたものではないとはいえ、造語としては1つの動詞にオノマトペをうまくプラスした見事な仕上がりだね。
大学後期高齢者|プラス法から生まれた造語
「大学後期高齢者」もプラス法から生まれた学生用の造語だね。高齢者は65歳以上75歳未満の前期と、75歳以上の後期に分けられるよね。だから、大学後期高齢者という表現は大学の最上級生である4回生を指す表現だよ。
直接的な表現をあえて使わず、日本という国が抱える深刻な社会問題と紐づけてみたところにどことなく儚さや憂いが感じられるね。
フルタン|プラス法から生まれた造語
「フルタン」は響きからイメージしやすい造語だね。「十分に、満杯の」を意味する英単語「フル(Full)」と日本語の「単位」を組み合わせた言葉で、1年間で取得可能な単位、もしくは卒業に必要な単位をすべて取得し終わった学生を指して用いられるよ。
もうフルタンだから今年は授業にほとんど行かなくても大丈夫、というように使われているね。
就職無理学部|プラス法から生まれた造語
「理工学部系の学部は就職の内定がもらいにくい」という学生たちの持つ苦悩から生まれた造語もあるよ。「就職は無理」と「理系学部」という言葉を組み合わせた「就職無理学部」という表現だね。
親不孝学部|プラス法から生まれた造語
同じような意味合いの造語として、「親不孝」と「工学部」を組み合わせた「親不孝学部」というのもあるよ。3回生になって就職活動が始まり、各企業の募集要項や周囲の内定状況を見ていく中で、理系の学部を選んだことをなんとなく後悔し始める様子が思い浮かぶようだね。
就職が思うように決まらず親に心配をかけてしまっているという複雑な思いも見え隠れするようだ。そう考えると、どちらも20代前半の若者を表す短い表現なのに、どことなく中高年層の悲哀や哀愁をも感じさせる造語と言えるよね。
あそ文系、バラ経、楽商、あほう学部|プラス法から生まれた造語
文系の学部には理工学系とは対照的な造語があるよ。それが「あそ文系」だね。これは「遊ぶ」に「文系」をプラスした表現で、大学生活を満喫している文系の学部に所属する学生のことを指しているよ。
文系の学部に関しては「パラダイス」と「経済学部」を組み合わせた「パラ経」や、「楽々勝利」と「商学部」をドッキングした「楽商」など、ポジティブで楽しさを感じさせる造語がとても多いんだ。
就職活動に関しても文系の方が比較的有利とされているから、そうした気持ちの余裕が造語のパターンや内容にも表れているといえるね。こうした基本的な風土の違いを羨ましく、あるいは妬ましく感じた理系の学生が生み出したとされる造語として「阿呆」と「法学部」をあわせた「あほう学部」というものがあるよ。
入院生活|プラス法から生まれた造語
修士課程や博士課程を目指す大学院生に関連した造語としては「入院生活」というものがあるよ。「入院」と「大学院」、そして「生活」という3つの単語を見事にプラスした表現だ。論文作成にひたすら打ち込んでいるため、ほとんど外出ができない状態を上手く言い表しているよね。
論文提出の締め切りが近くなった院生は、寝る間を惜しんで作業に打ち込んでいるためいつも体調が悪そうという意見もあるから、経験者からすると「入院」という表現は意外としっくりくるのかもしれないね!
語尾変化法から生まれた造語
ラグい
語尾変化法とは、名詞の末尾に「い」や「る」をつけて形容詞や動詞に変化させる方法のこと。代表的なものとしては「ラグい」が挙げられるね。
授業中にPCの動作が不安定になったり、インターネットの回線速度が落ちて動画の再生速度が落ちてしまったりするとき、英語の「lag(進行が遅い)」の末尾に「-い」をつけたこの表現がよく使われているよ。
エモい
「エモい」は年代を問わず広く使われている造語だよね。英単語の「Emotion(感情)」を短縮系にして、その語尾に「-い」をつけることで、「感動的な、心を揺さぶるような」という意味で使われているよ。
ただし、学生の間ではいつもポジティブな意味合いではなく、ガッカリしたときや強いストレスを感じた時などネガティブな感情を表現するタイミングでも使われることが度々あるんだ。
例えば、模試の結果が良くなかったり、就職活動がうまくいかなかったりするときにも「エモい」を使うケースがあるということだね。
ザキる、バミる
語尾に「-る」を付けた語尾変化法の主な造語としては、「ザキる」や「バミる」があるよね。どちらもお店の名前と組み合わせることで「お店を利用する」という動詞に変化しているんだ。
「ザキる」はコンビニエンスストアのデイリーヤマザキ、「バミる」はファミリーレストランのバーミヤンだね。高校や大学の近辺で営業しているお店に関しては、造語が作られやすいよね。
ただ、他の大手コンビニやファミレスでは、語呂や語感の良さが関係しているからか、同じような造語がまだ生み出されていないよ。
トイラー、ナイバー、内バー、ガイバー
最近では英語の「-er」をつける語尾変化法も増えているね。特定の名詞に対してこの語尾変化をさせることで、特定の行動をする、もしくは特徴を持つ人を意味するようになるよ。
有名なのは「トイラー」や「ナイバー」の2つ。「トイラー」は「トイレ」に「-er」を付けた造語で、学校に来るとひたすらトイレへいく生徒のことを指しているよ。
一方、「ナイバー」は「内部」に「-er」の語尾をプラスした造語。私立の高校や大学では、幼稚園や小学校からずっとエスカレーター式で進学してくる生徒がいるよね。それら内部進学をしてきた学生のことを指して用いられている表現なんだ。
漢字表記で「内バー」という使い方もあるよ。一方で、外部生のことを「ガイバー」と呼ばないのは興味深いポイントだね。
頭文字法から生まれた造語
MEXCBT
頭文字法とは、長い表現や複数の単語に関してそれぞれの頭文字を取り、それを組み合わせて新しい単語を作る方法のこと。フォーマルなものとしては「MEXCBT」が挙げられるね。これは文部科学省が推進している新しいオンライン授業システムのことだね。
これまで一般的だったストリーム配信だけではなく、高校卒業認定などの資格まで取れるようにサポートしてくれる画期的なシステムだ。名称のもとになっているのは、「Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (文部科学省)」と「Computer Based Testing(PCによる試験のシステム)」の2つで、これらの頭文字をあわせて「MEXCBT」となっているよ。
システムの導入はすでに進められているから、学生もオンライン学習に関する授業などで耳にすることが増えていくはずだよ。
GIGAスクール構想
同じく文部科学省が考案したフォーマルな頭文字法の造語としては「GIGAスクール構想」があるね。「GIGA」は通信速度に関する表現ではなく、「Global and Innovation Gateway for All(グローバルな人材を生み出す入り口)」という言葉の頭文字をあわせたもの。
義務教育を受けるすべての子供たちが情報通信技術に触れられる機会を設けることで、世界に通用する人材を生み出そうという取り組みのことを指しているよ。GIGAは覚えやすい響きなので生徒たちにもわかりやすいね。
PTA
学生たちにより身近な頭文字法の造語といえば「PTA」だよね。小中学校では頻繁に耳にする言葉ではあるものの、実際に何の略かと聞かれたらあまり知られていないこの表現。実は「Parent(父母)」「Teacher(教師)」「Association(団体)」の3単語からそれぞれ頭文字を取った造語なんだ。
PTAが目指しているのは学校に通う子どもたちの育成をサポートすることで、それを見守る大人たちが一致団結できる組織を設けましょうという意図で作られたんだよ。
MTG、NR
「MTG」や「NR」も日常会話でよく登場する、比較的カジュアルな造語だ。「MTG」は「Meeting(ミーティング)」の子音3文字を組み合わせた言葉で、意味も変わらずミーティングだよ。この表現は学生だけでなく会社でも広く使われるようになっているよね。
一方、「NR」は英語の否定形「Not」とネットから生まれたスラング「リア充」の頭文字をそれぞれ合わせたものだよ。「リア充」は「現実の生活が充実している人」のことだから、「NR」は毎日の生活が残念ながら充実していない人を指しているわけだね。
より限定的な用法として、交際相手がいない人のことを意味するケースもあるよ。
回想法
これは、単語そのものはまったく変化していない一方、場面によってその言葉の意味するところが本来の用途とは異なっているというパターンの造語だね。
サボテン
例えば「サボテン」という言葉。園芸に関する会話の中で出てくれば文字通り植物のサボテンのことだよね。一方、特定の異性に関して話している女子学生の間でこの表現が出てくると意味が大きく変わってくるんだ。
具体的には「観賞に適したイケメン」という意味になる。文字通りのサボテンは遠目に見ていると可愛いけれど、実際にはとげがあるので直接触ることはためらわれるよね。
同じように、サボテンと呼ばれる男性は、ルックスは良いものの性格や話し方にやや難があるので、遠目から見ているだけに留めておくべき存在と見られているわけだね。これはややダークな響きも含むなかなか秀逸な表現と言えるね。
自然エネルギー
「自然エネルギー」も同様の回想法で作られた造語だね。この単語だけを聞けば、大抵の人は太陽光エネルギーや風力エネルギーを思い浮かべるよね。一方、授業や講義を評価する表現方法としてこの言葉が用いられる場合には、「ぽかぽかとした暖かい日差しのように眠気を誘う授業」という、先生からすると非常に残念な意味になるんだ。
有名な忍者のバトル漫画にも登場するこの言葉を授業後に学生たちが使っていたら、担当していた先生は授業スタイルの見直しが必要かもしれないね!
まとめ
若者は感性が豊かだから知性を感じさせるユニークな造語が生まれやすい。生活スタイルが変化すると、それに伴って造語の表現方法も変化するというのも面白いよね。また、地方ごとに存在するローカルな造語を他の人と共有するというのも大学生ならではの楽しみだね!
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。
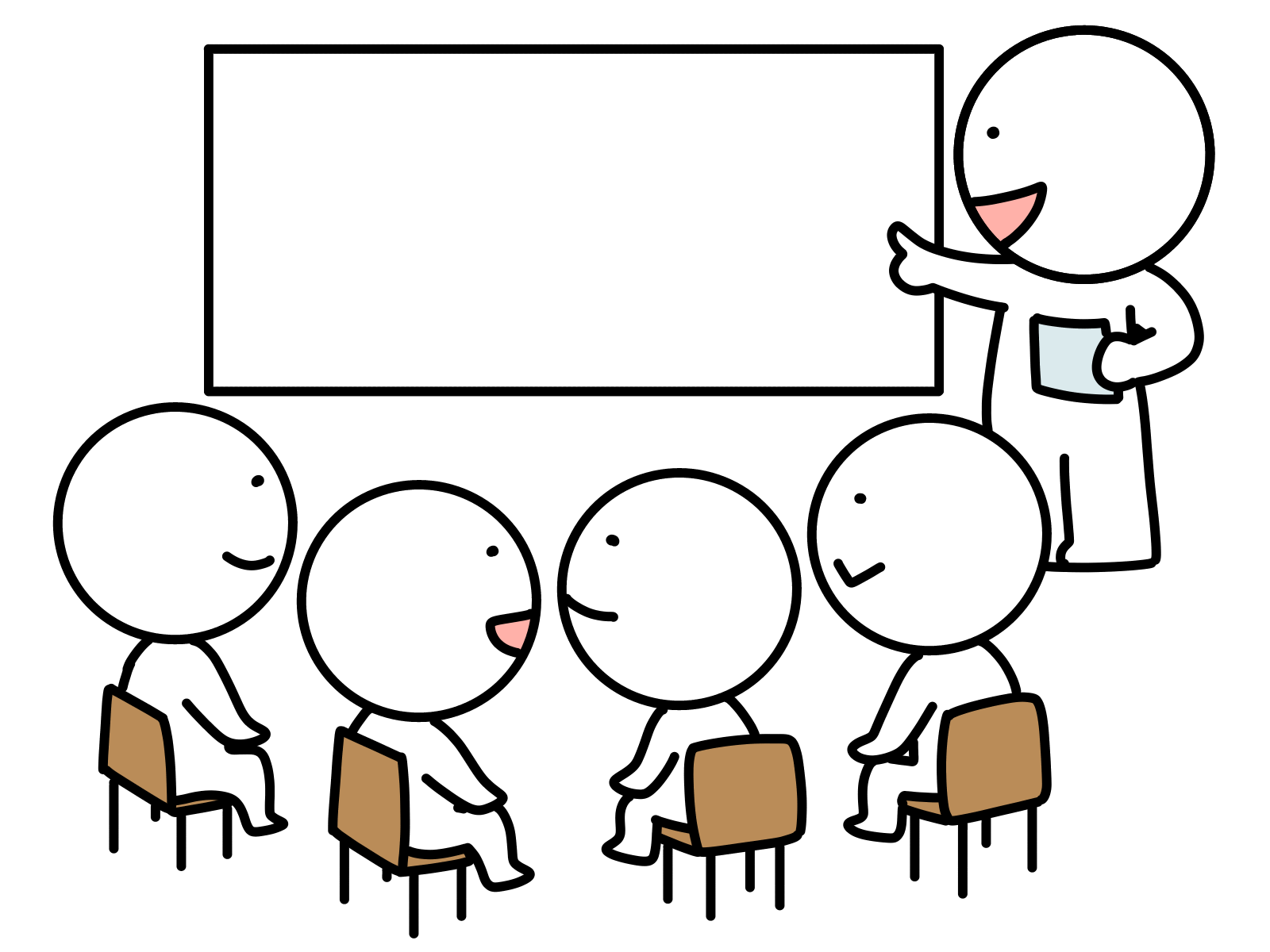



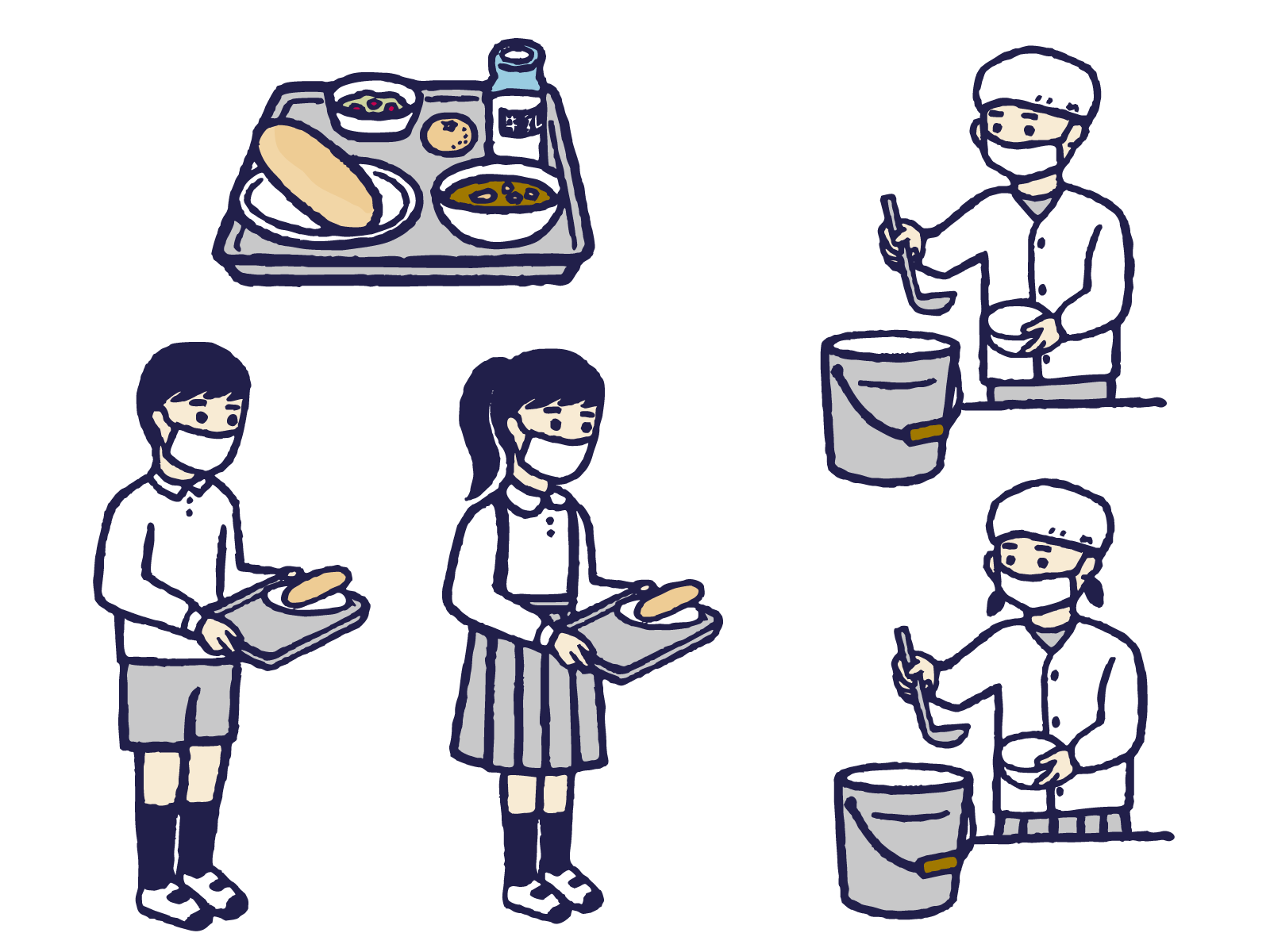
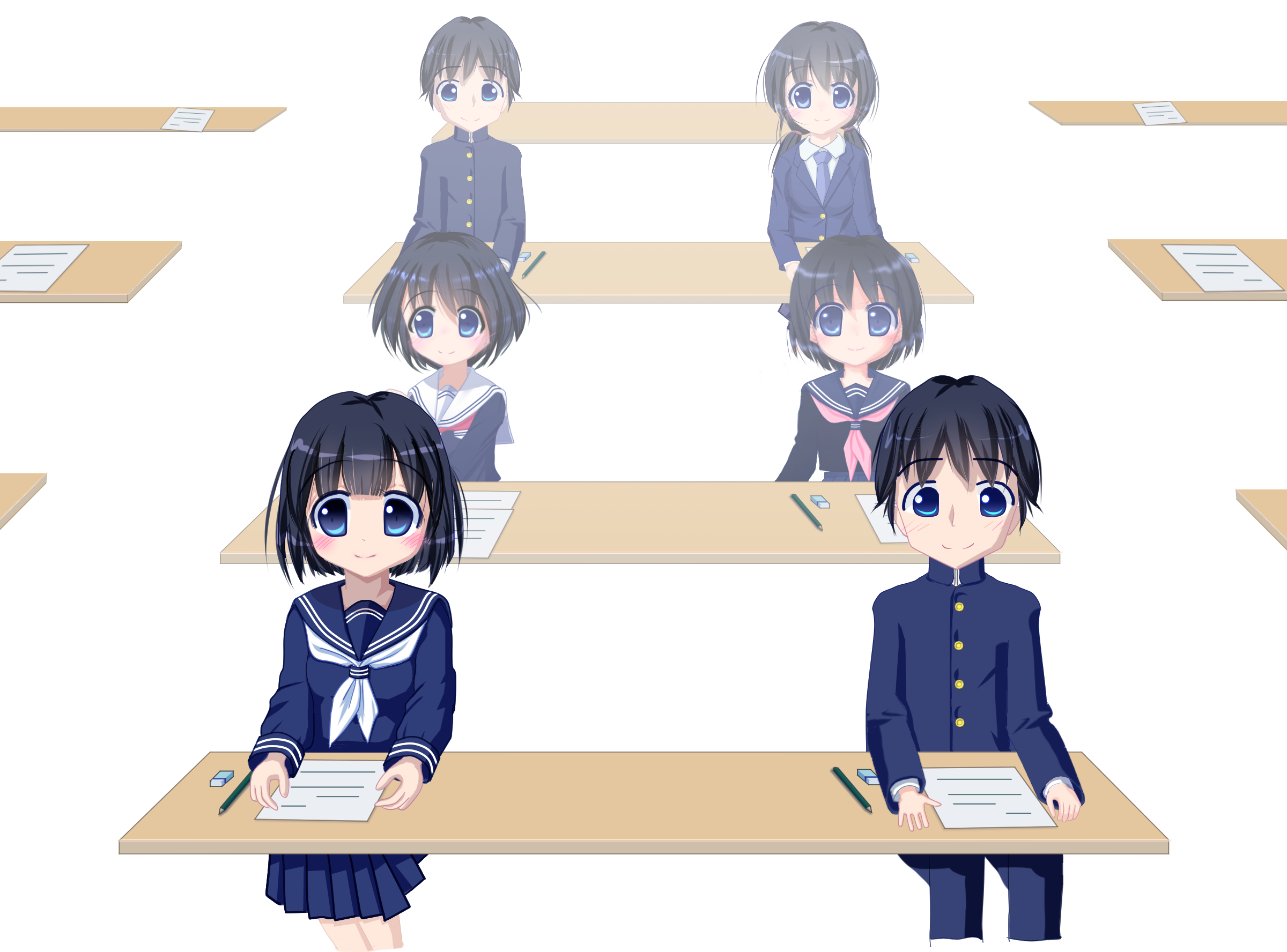
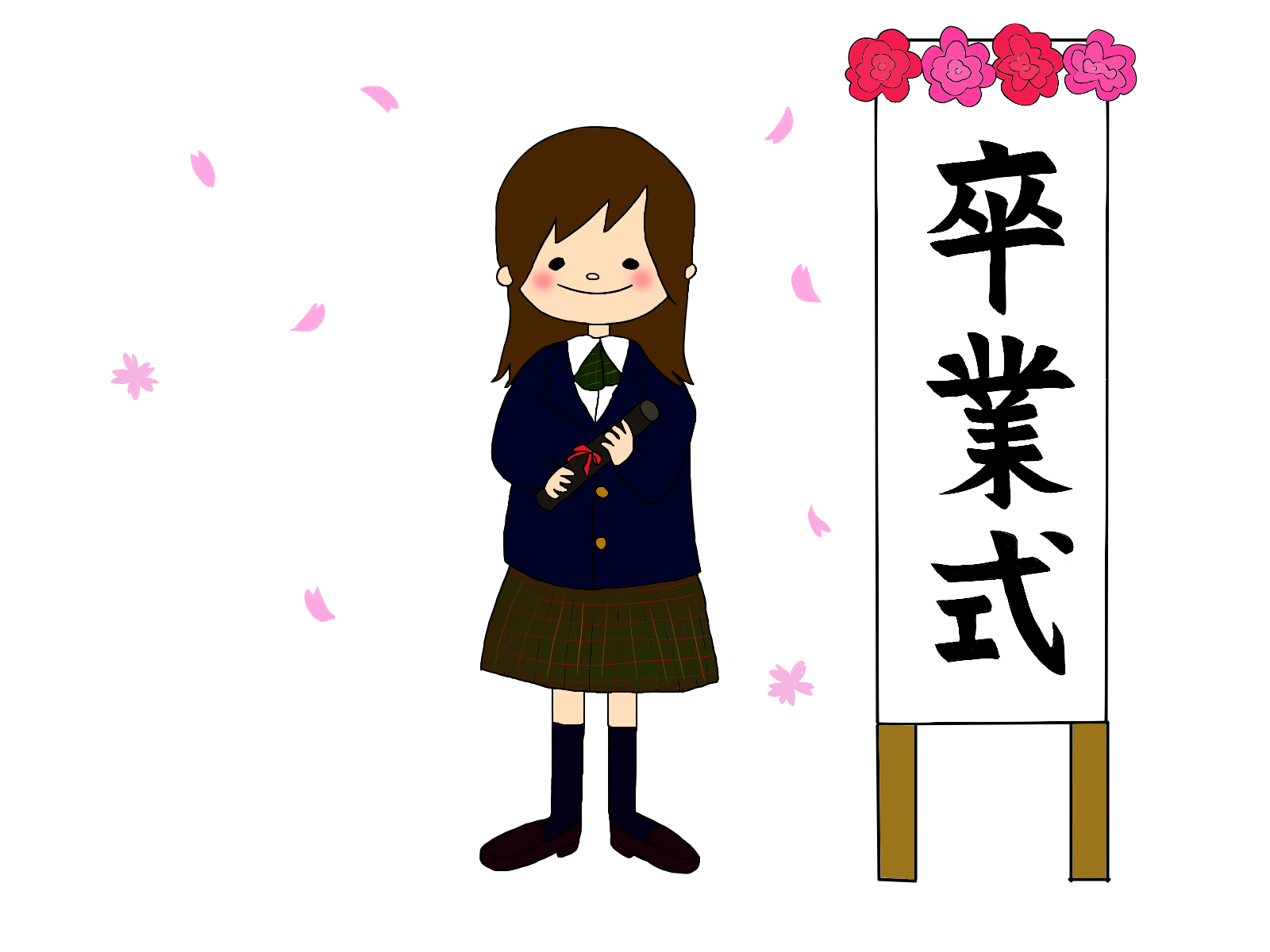

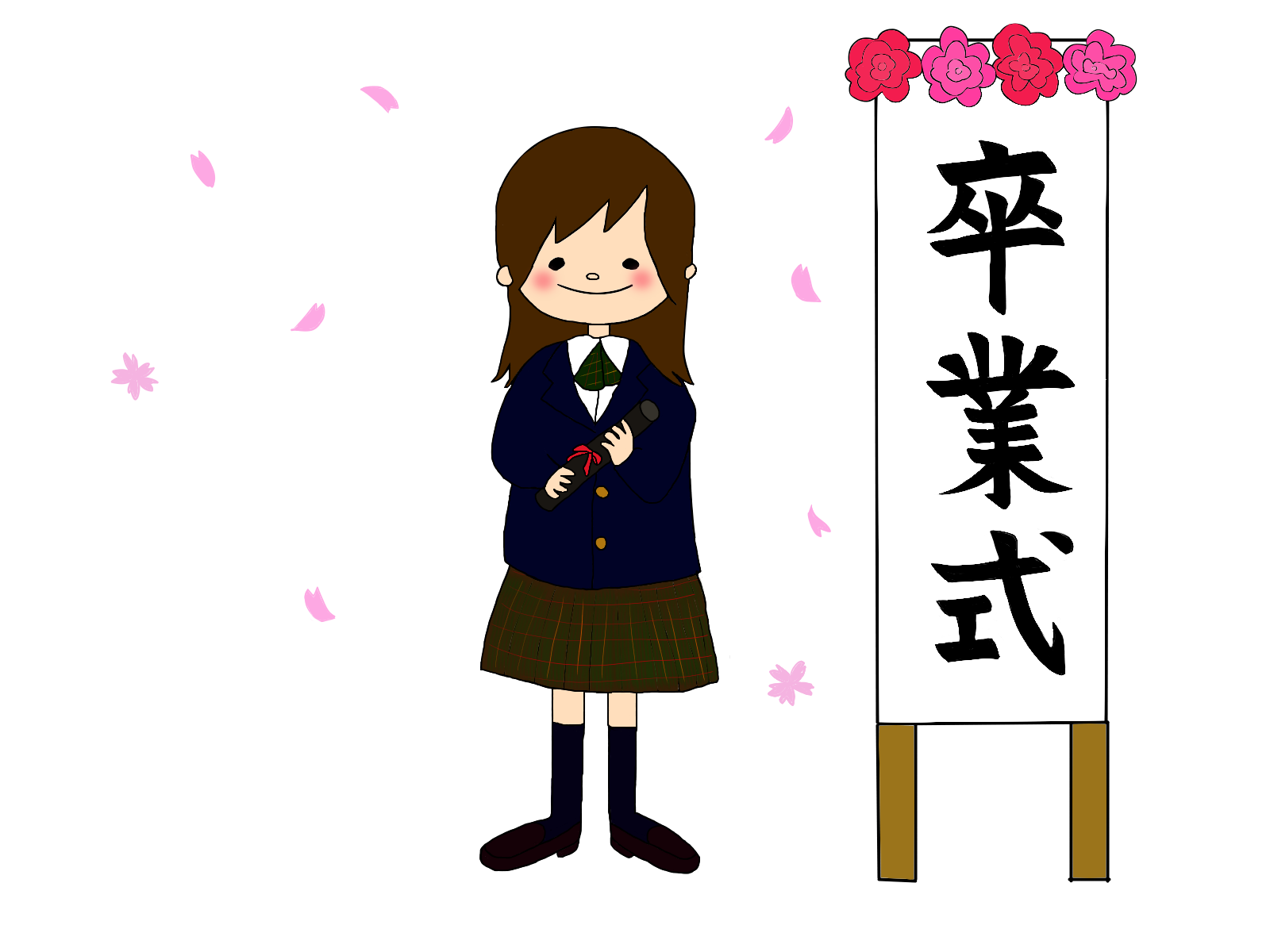
コメント