学生時代に給食のお世話になった人もいるだろうね。昔はシンプルなものが多かったけれども、最近では多様化しているみたい。ビーフストロガノフのような外国の料理が出ることもあるらしくて、うらやましい限りだね。
最近では学校だけでなく、介護関係の施設でも給食サービスは提供されているよ。ところでこの給食業界では、業界用語ともいえるような造語がいろいろとあるね。
だから給食関係で仕事をしている以外の人が耳にしても何のことかちんぷんかんぷんなんてことも。
日本全国どこでも使われる給食用語
給食の業界では専門用語や業界用語のようなものがいろいろとあるね。そもそも「給食」という言葉自体も、日本に昔からある言葉じゃないんだ。当初は「学校給食」と呼ばれる造語で、この言葉が出現したのは1889(明治22)年のこと。
山形県鶴岡市に大督寺というお寺があったんだけれども、この中に私立忠愛小学校という学校があったんだ。ここに通う子供の中には生活が苦しい子もいたんだ。そこでそんな子供たちにひもじい思いをさせないように、無償で昼食を学校のほうで用意したらしい。
これが学校給食のルーツって言われているよ。その後1923(大正12)年には国が学校給食を奨励するようになって、日本各地に広まっていったんだ。
学校給食は平成17年度から施行されている
栄養教諭も給食に携わったことのある人じゃないとあまり聞かない言葉じゃないかな?平成17年度から施行されている制度で、食に関する指導を推進するにあたっての中核的な役割を担っているよ。
食に関する指導を行う人のことで、大学で所定の単位を取得したら免許を取得できるよ。ちなみに栄養教諭の配置は地方公共団体や設置する人の判断によって行われるんだ。
かみかみ給食
かみかみ給食は給食業界ならではの造語だね。よく噛んで食べる給食のことで、するめや入り豆などの歯ごたえのある、よく噛まないと呑み込めないようなものを定期的に献立に出す方式のことだね。よく噛まないといけない食材を料理に盛り込むだけでなく、よく噛んで食べるように先生などが指導することも必要だよ。
30代以上の人の場合、「かみかみ給食」という言葉自体聞いたことがないという人もいるかもしれないね。かみかみ給食は最近出てきた言葉なんだ。背景として、子供たちの食習慣の変化が関係しているよ。最近の子供たちは柔らかい食べ物を好みがち。
よって顎がなかなか発達しなくて、歯の生えるスペースがなかなか確保できないんだ。その結果、歯並びの悪い子供が増えてきているね。かみ合わせに問題があると、脳の発達にマイナスの影響をもたらすといわれているんだ。
そこでよく噛んで、しっかり顎を発達させるように子供たちに指導する必要があるわけ。
全国学校給食週間
全国学校給食週間というものがあるのを知っているかな?大正時代から学校給食は日本全国に徐々に広がっていったんだけれども戦争中にいったん中断になったんだ。食糧不足になってしまったからね。
しかし戦後1947(昭和22)年1月に都市部の小学校を中心に学校給食が復活したんだ。戦後はいまだに日本国内では食糧難だったから、学校給食を独力で用意するのは困難だった。
そこでGHQから支給される物資や「ララ物資」と呼ばれるアメリカの事前組織による海外援助事業として贈られたものでまかなったんだ。
ララ物資
ララ物資もいわゆる造語だね。アメリカ協議会というアメリカの宗教団体を中心に立ち上げられた事前組織があったんだ。アメリカ協議会では1946年6月に特に日本や沖縄、朝鮮への救援事業を行うための特別委員会を立ち上げることになったんだ。その名前を「Licensed Agencies for Relief in Asia」ね。日本語に訳すと「アジア救援公認団体」といった感じかな?この頭文字をとると「LARA」になるよね。つまり「ララ」と呼ばれるようになったわけ。
その後1950(昭和25)年から1月24日から30日までの1週間を「全国学校給食週間」と定めたんだ。全国学校給食週間の間中は学校給食に関する感謝や将来の発展を祈念するためのイベントが日本全国で開催されているよ。
脂肪エネルギー比
学校給食は栄養バランスの取れたメニューを提供することも重視されているね。特に学校給食では、給食を通じて子供の健全な成長を促しているからね。そこで重視される専門用語として「脂肪エネルギー比」があるよ。脂肪エネルギー比とは摂取した食品をエネルギーベースで、脂肪の占める割合のことを表しているよ。
摂取する熱量を100とした場合、タンパク質は12~13・脂肪20~30・炭水化物57~68に保つのが好ましいとされているね。学校給食では脂肪エネルギー比が25~30%の範囲に収まるように、献立の調整を行っているよ。
脂肪を過剰摂取することになれば、子供たちが肥満体形になってしまうからね。
食育
近年食育という造語も注目されていて、給食が食育で重要な役割を担っているね。「食事」と「教育」を組み合わせた造語になるかな。自分で職の選べる自己管理能力を育てることで、それぞれが自分の健康を守っていけるような食生活を送れるように子供を教育することだ。
ちなみに教育には「知育」「徳育」「体育」の3つがあるといわれているね。食育はこの3つの教育のさらに基礎に位置付けられているよ。さらに平成17年6月には「食育基本法」も成立されているね。
国民が一生健全な心身を培って、豊かな人間性をはぐくむために食育を推進させるための法律だよ。このように国を挙げて食育を重視し、推進させているんだ。その中でも給食は重要な役割を果たしていることになるね。
トレイサビリティ
トレイサビリティも給食関連の造語といえるね。「足跡を追う」という意味の「トレース」と「できること」を意味する「アビリティ」を組み合わせた造語だね。日本語に訳すと「追跡可能性」になるかな。流通から生産現場までさかのぼって食品の履歴を知ることだね。
やはり子供の食べるものである以上安全性という観点から、給食の世界でもトレイサビリティは重視してほしいよね。
特定原材料
特定原材料も給食関連の造語といえるね。特定原材料とはアレルギーを起こしやすい食べ物のことだよ。具体的には小麦・そば・卵・乳製品・ピーナッツの5品目が特定原材料に指定されているよ。
子供の中にはもしかするとアレルギーを持っていることもあるかもしれないよね。その場合、そのような原料は避けて給食を作る必要が出てくるわけだ。ちなみに特定原材料に準ずる推奨品目というものもあるよ。こちらは特定原材料ほどではないけれども、過去に一定の頻度でアレルギー発症の事例のある食べ物が含まれるんだ。
具体的にはアワビ・イカ・エビ・オレンジ・カニ・キウイ・ビーフ・クルミ・鮭・サバ・大豆・チキン・マツタケ・モモ・ヤマイモ・リンゴ・ゼラチン・バナナの20品目が該当するよ。
バイキング方式、カフェテリア方式
給食というと料理が盛られて、自分の席で食するのが一般的だよね。しかし近年では新しい給食の方式も取られているよ。例えばバイキング方式を採用している学校も出てきているよ。バイキング方式とはいわゆるバイキングと一緒だね。
大皿に料理が盛られているので、子供たちが自由に食事をとるスタイルだよ。バイキング方式を導入している学校は増加傾向だね。より効果的な食育効果が期待できるからだよ。
子供たちが自由に食事をとることができるので、栄養バランスや量をコントロールする力を培える効果だね。学校によっては、カフェテリア方式と呼んでいるところもあるね。どちらも基本的には同じ意味だよ。
ロハス
給食の世界では「ロハス」も近年重視されつつあるよ。ロハスとはLohasと書き、「lifestyles of health and sustainability」の頭文字をとった造語だよ。
自分の健康だけでなく、環境問題をはじめとした社会問題についても関心を持って、日々の生活を送るスタイルだね。
給食のスタイルもいろいろ
近年では給食のスタイルも多種多様になってきているね。多様化の結果、造語も新しく出てきているよ。
行事給食
例えば行事給食という言葉が学校によっては使われることもあるよ。年間通じていろいろな行事があるよね。ひな祭りや端午の節句、七夕など日本国内の伝統的な行事もあるし、ハロウィーンやクリスマスなどの海外の行事もあるよね。
クリスマスは海外の行事だけれども、国内でもすっかり定着したね。そこでその行事にふさわしい給食を提供する試みが進められているよ。行事食が家庭で作られる機会が少なくなっているので、伝統伝承の場として学校給食の果たす役割が大きくなっているね。
交流給食
交流給食といったイベントが試みられているところもあるね。交流給食とは、いろいろな人たちと一緒に食事のできる場を提供する試みだね。従来であれば、クラスメイトと一緒に教室で食事をとったよね。
でも異なるクラスだったり異なる学年の生徒と一緒に食事をすることになるね。中には小学校と中学校といった感じで学校の枠を超えたイベントを企画しているところもあれば、保護者と一緒に食事をするスタイルの交流給食を進めているところもあるね。
このようにいろいろな人たちと一緒に給食をともにすることで、コミュニケーションを深めていくことが目的なんだ。
身内だけでわかる給食の造語もある
ここまでは日本全国で広く定着している給食の造語だったね。でもそのほかにもその職場だけで通用するような独自の言葉を使っているケースもあるよね。
実は学校給食の現場でもこのような職場単位で使われている隠語のようなものがあるみたい。インターネットでは「うちだけで使っている専門用語」についていろいろと紹介されているよ。
コロコロ
例えば角切りすることを「コロコロ」という職場があるみたいだね。そして賽の目切りにすることを「小さくコロコロ」っていうらしいんだ。
さらにざく切りする場合には「ザクザク」というところもあるみたいだよ。ネットを見てみると「コロコロ」とか「ザクザク」といった言葉は結構使っている職場は多いみたいだね。
ぴったり、ぶかぶか
あと手袋について自分たちだけがわかる造語を使っている給食の現場もあるみたいだね。ラテックス手袋やエンボス手袋を使っている現場が多いよね。しかしいちいちその名前を言うのが面倒なので、職場によってはラテックス手袋のことを「ぴったり」、エンボス手袋のことを「ぶかぶか」って呼んでいるところもあるそうだよ。
ただしその人いわく「わからない人がいて混乱する」ということだから、正式名称で呼んだほうが逆にいいかもね。
ちゃんとした袋、シャカシャカ袋
ビニール袋で2種類の異なるものを取り扱っている学校給食の現場もあるみたいだね。そこで一つは「ちゃんとした袋」もう一つは「シャカシャカ袋」って呼んでいる現場もあるよ。
サラピン、渡鬼
そのほかには漂白石鹸に「サラピン」と呼ばれるものを使っている現場では「泉ピン子」と呼んでいるという話もネットで紹介されていたよ。「ピン」つながりだったんでしょうね。
さらに中には泉ピン子からさらに発展して、「渡鬼」と呼んでいる人もいるのだとか。
流行語にノミネートされる場合も
黙食
給食に関連する造語の中には時として流行語になることもあるよ。2021年の流行語大賞の候補の中で「黙食」がノミネートされたよ。黙食はニュースやワイドショーなどでもしばしば取り上げられていたから、なんとなく意味を知っている人も多いかもね。
黙食とは読んで字のごとくで、黙って食事をすることという意味の造語だね。コロナ禍の中で、会食をする機会が減少したね。マスクを外して食事をしながら会話をすると、どうしても飛沫が飛んじゃう。
もし相手が新型コロナに感染していれば、周りの人も感染してしまうわけ。そこで黙って食事をすることが推奨されるようになった。学校の給食でも取り入れられたよね。
流行語になるものもある給食関連の造語
給食関連の造語はここで見てきたようにいろいろとあるよね。黙食に代表されるように、流行語になるようなものもあるよ。その一方で、給食を作っている現場でしか通用しないような独自の造語が飛び交っているところもあるみたいだね。
給食は子供たちにとっては、健やかに成長するために欠かせないもの。給食関連の造語についても覚えておくと、今後給食現場で働くときにプラスになるかも?
学校関連の造語について詳しく知るには、「造語症の方向けの学校の一覧~専門学校や留学などの多彩な選択肢や授業料についても」をどうぞ。
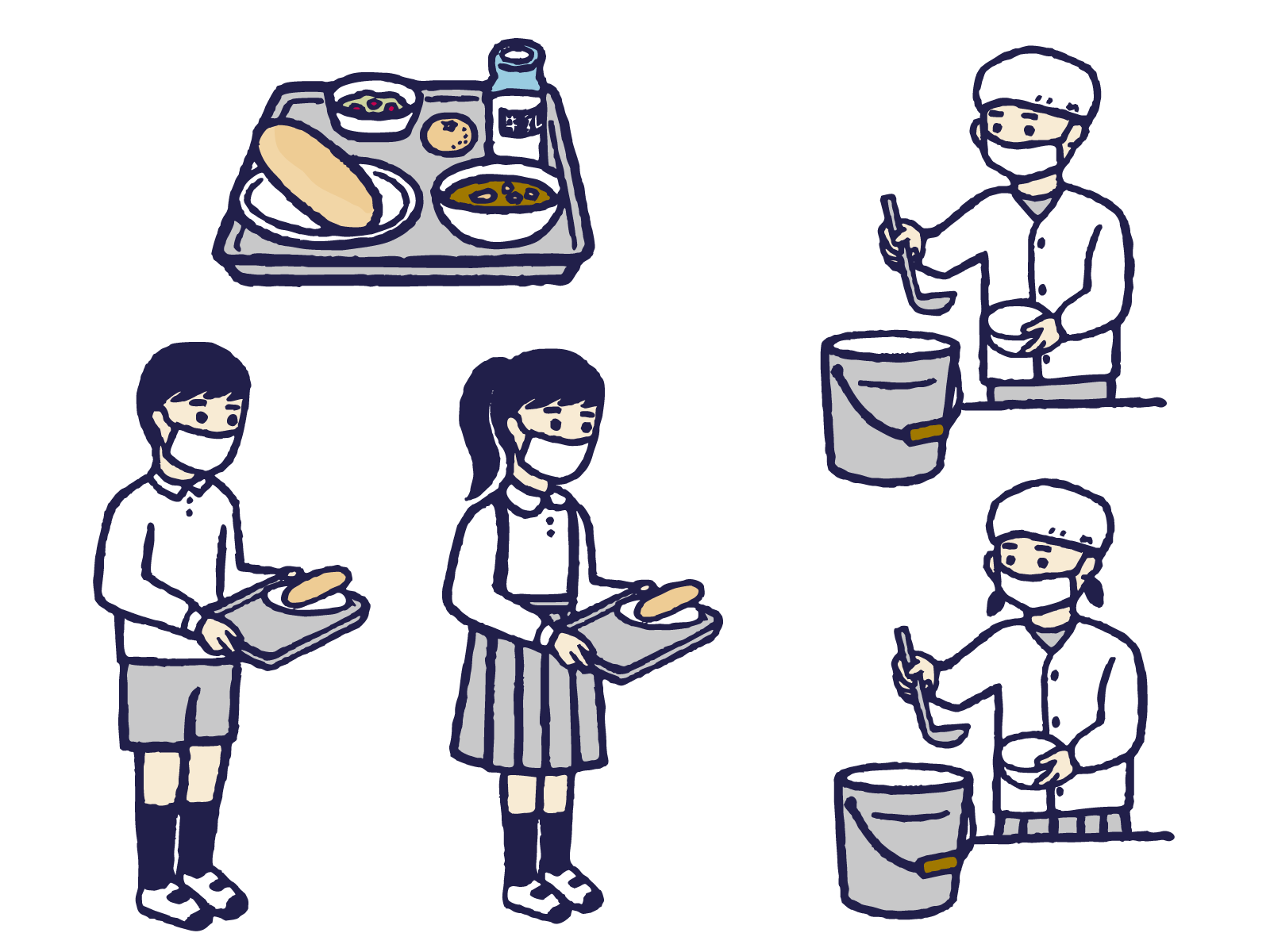



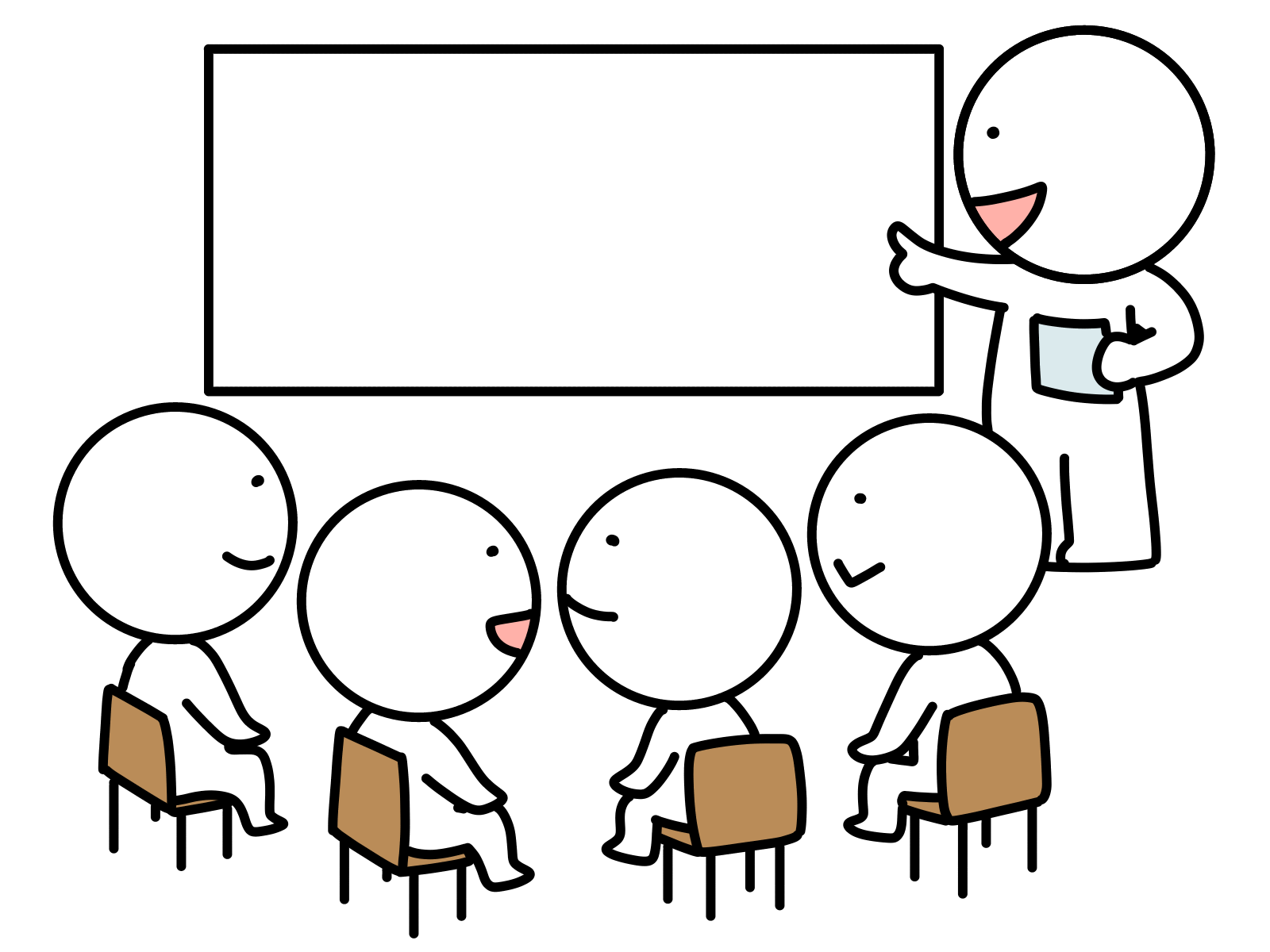
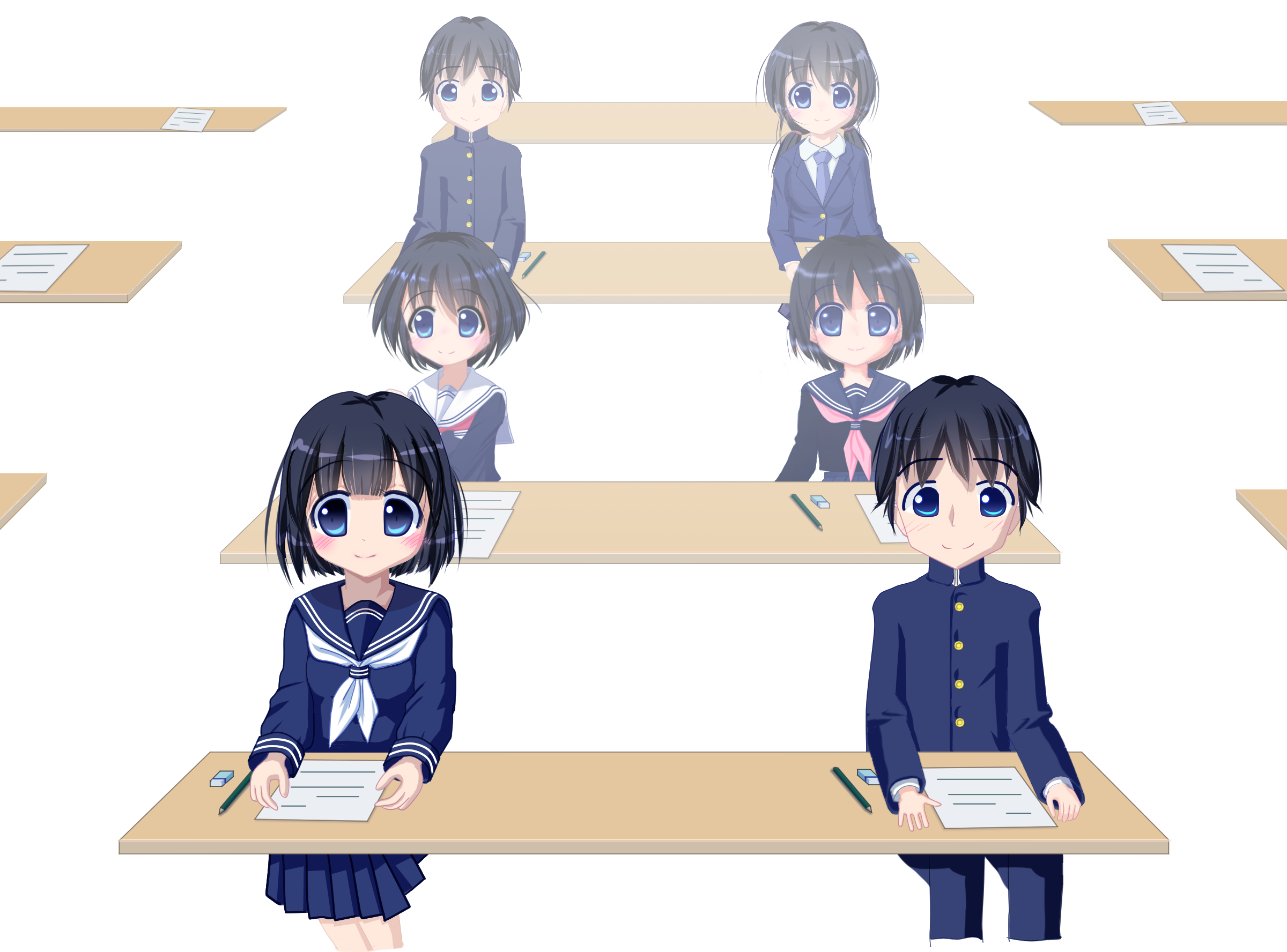
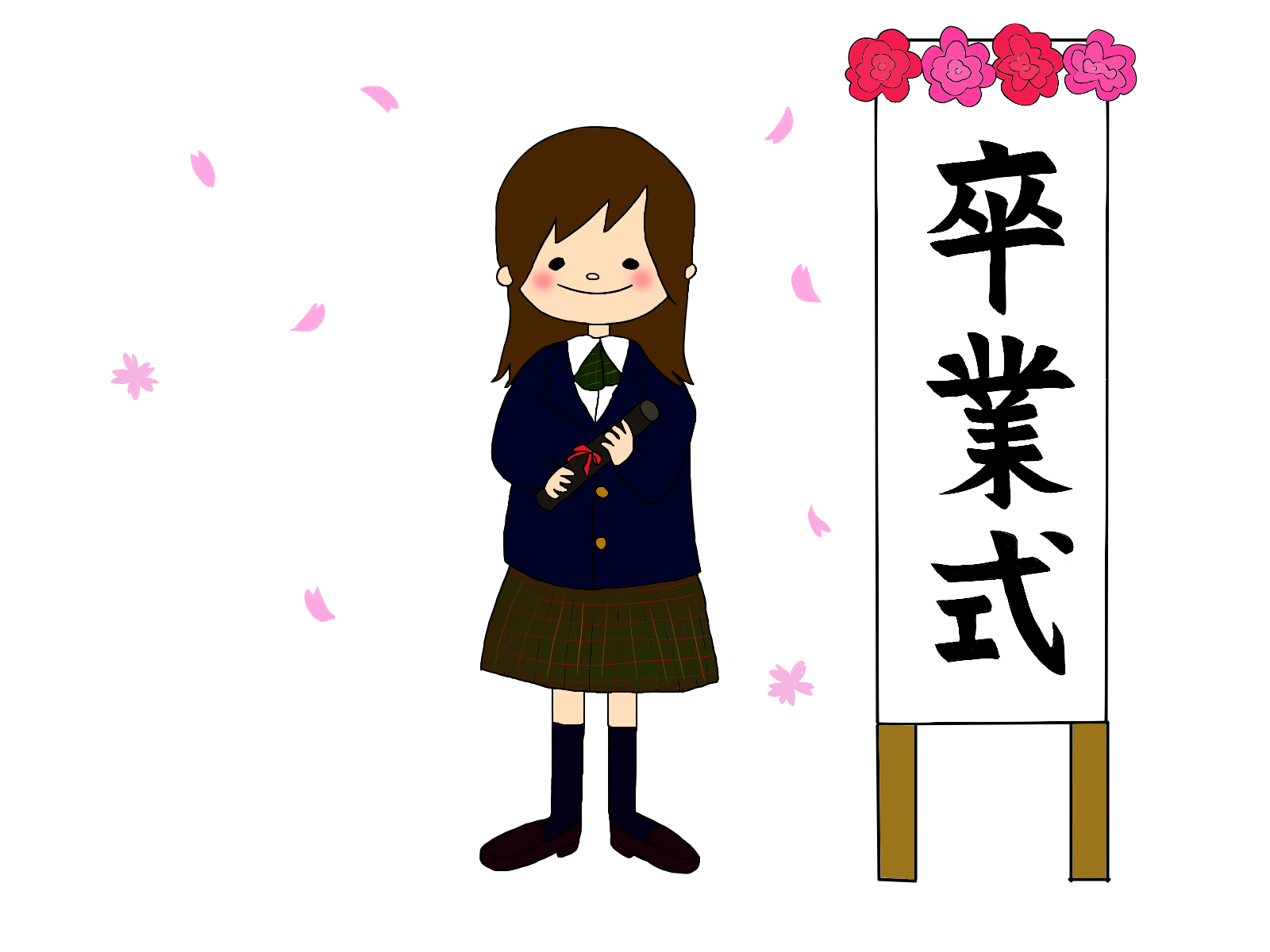

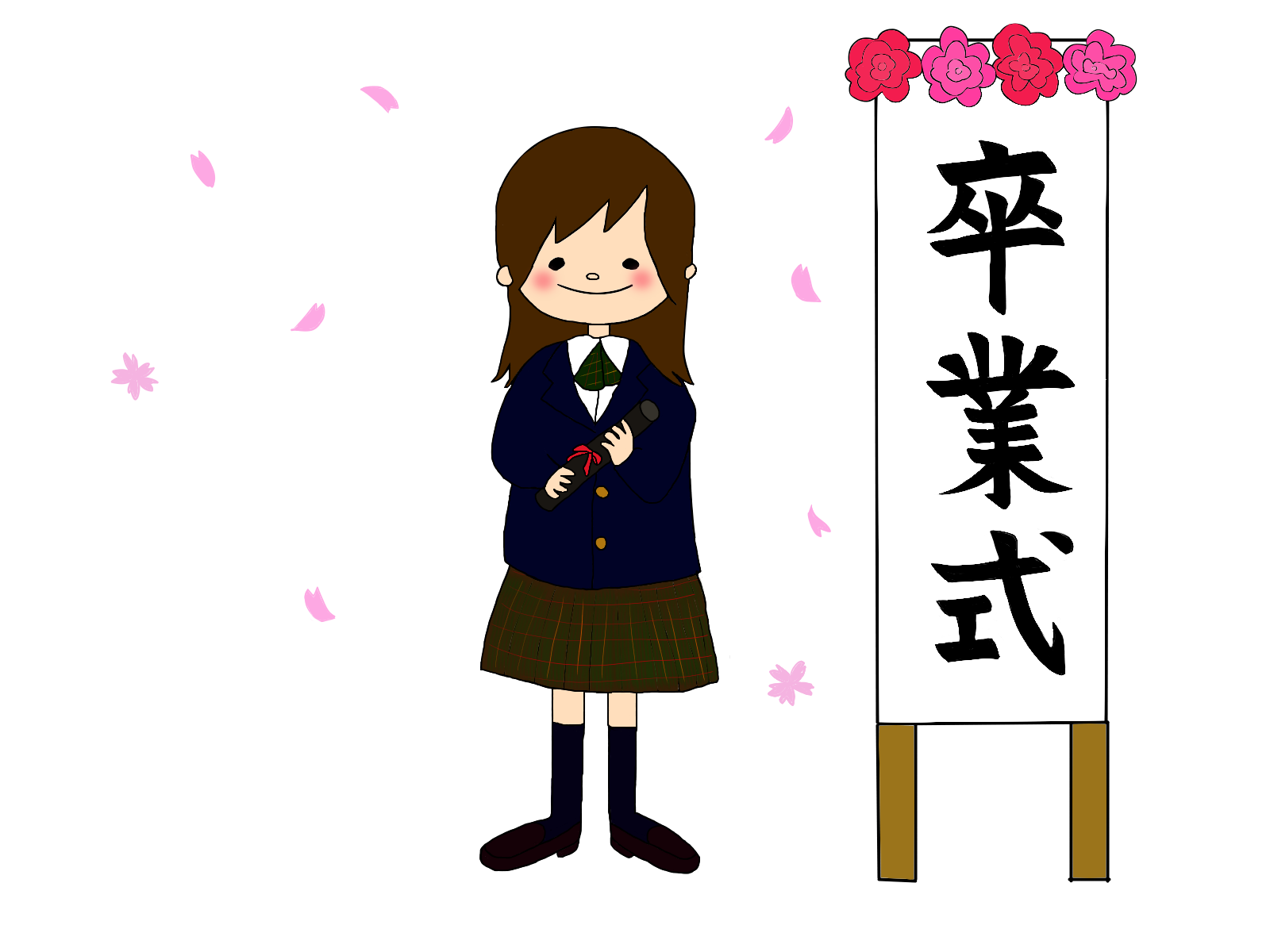
コメント